 |

|
|
鉄分の多い食品・食べ物と含有量一覧 | |

 | 鉄分を多く含む食品 | ||
鉄は肉類や魚介類や海藻類などに多く含まれます。肉類は特に牛肉に鉄分は多いです。レバーも鉄分が豊富です。魚介類なら煮干しや干しエビ、どじょうや鮎、赤貝などに鉄分が多く含まれます。青のりや岩ノリなどの海藻類、いかり豆やがんもどきなどの豆腐製品、バジルやタイムなどの調味料や抹茶などにも多く含まれます。
鉄は植物性食品に含まれる非ヘム鉄で2〜5%、動物性食品に含まれるヘム鉄で15〜20%と吸収率に大きな差があるので、動物性食品の魚介類や肉類は鉄分をより摂取しやすい食品だといえます。
鉄は植物性食品に含まれる非ヘム鉄で2〜5%、動物性食品に含まれるヘム鉄で15〜20%と吸収率に大きな差があるので、動物性食品の魚介類や肉類は鉄分をより摂取しやすい食品だといえます。
 | 鉄分摂取の推奨量 | ||
成人男女の鉄分推奨量
鉄分の成人男子の推奨量は7.5mgです。成人女子の推奨量は月経なしでは6.5mg、月経ありでは10.5mgです。血液中のヘモグロビンには鉄が多く含まれていて、月経ありでは月経で血が体外へと流出するためその分多めに鉄分を摂取する必要があります。
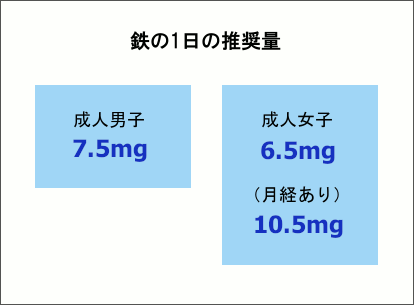
(年代別推奨量はこちら)
鉄分の上限量
鉄には摂取の上限量が定められていますが、成人男性で50mgで成人女性で40mgとその量は非常に多いため、通常の食生活では過剰症になることはありません。サプリメントなどの錠剤を不適切に使用した場合などに過剰摂取が起こる心配があります。
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。
 | 魚類で鉄分の多い食品 | ||
魚類で鉄分を特に摂りやすいものは?
魚類では乾燥食品である煮干しやめざし、くさやなどが栄養素が濃縮されるのでその分鉄分も多く摂れます。丸ごと食べれるあゆやどじょうも鉄分は多く摂れます。
煮干しは手軽にたくさんの鉄分が取れる

煮干しは鉄分が非常に多く、10尾(20g)で3.6mgの鉄分を摂取できます。煮干しは保存性もよく比較的手軽に量を取れるので鉄分補給には最適です。動物性食品なので吸収率も高いです。ただし塩分も多いので摂りすぎには注意が必要です。10尾だと塩分は0.87gになります。ちなみに上の画像は煮干しです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 煮干し | 18.0mg | 10尾20g(20g) | 3.6mg |
はぜの佃煮も鉄分が多い
はぜの佃煮は料理のお供として食べられることの多い食品で、大さじ1杯(10g)で1.2mgの鉄分を摂取できます。やや塩分が多いので摂りすぎには注意が必要です。大さじ1杯分だと塩分は0.5gほどです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| はぜの佃煮 | 12.4mg | 大さじ1杯10g | 1.2mg |
どじょうは丸ごと食べれて鉄分もとれる
どじょうは丸ごと食べれて量も摂りやすいので、一度の食事で効率的に鉄分を摂取できます。ドジョウは10尾(80g)で4.5mgの鉄分を摂取できます。どじょうは柳川鍋、汁物、てんぷら等にして食べられます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| どじょう | 5.6mg | 10尾80g(80g) | 4.5mg |
鮎は特に天然物に鉄分が多い

あゆも1個体あたりの重量があるので、一度の食事で効率的に鉄分を摂取できます。下表の鮎(焼き)は内臓を含めない数値ですが、鮎は内臓に特に鉄分が多く含まれています。100gあたりだと焼きで63.2mg、一尾分に換算すると内臓は5gほどなので、鉄分は3.2mgにもなります。鮎の塩焼きなどでは内臓も一緒に食べることも多いですが、一緒にとれば鉄分は合計で1尾辺りで4.5mgも摂取できます。
ちなみにこれは天然の鮎での数値で、養殖物だと鉄分の含有量も少なくなります。養殖の鮎だと1尾分で鉄分の量は0.5mgで、内臓分は0.9mg、合わせると1.4mgと養殖物の3分の1程度の鉄分の量になります。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| あゆ(焼き) | 5.5mg | 1尾55g(25g) | 1.3mg |
| あゆ内臓(焼き) | 63.1mg | 1尾分5g | 3.2mg |
| あゆ(焼き・内臓込み) | 1尾分 | 4.5mg | |
| あゆ養殖(焼き) | 2.0mg | 1尾55g(25g) | 0.5mg |
| あゆ養殖内臓(焼き) | 19.0mg | 1尾分5g | 0.9mg |
| あゆ養殖(焼き・内臓込み) | 1尾分 | 1.4mg |
めざしは塩分の取りすぎに注意
めざしはイワシを塩漬けにして乾燥させたものです。数尾まとめてわらなどで目を貫いて乾燥させるのでこの名がついています。めざしは鉄分が多く量も摂りやすいのですが、塩分も多いので摂りすぎには注意が必要です。めざしは4尾(可食部52g)で塩分は1.9g含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| めざし(焼き) | 4.2mg | 4尾60g(52g) | 2.2mg |
くさやも塩分の取りすぎに注意
くさやはクサヤモロなどの魚をくさや液につけてから乾燥させたものです。鉄分が多く量も摂りやすいのですが、こちらも塩分も多いので摂りすぎには注意が必要です。くさやは1尾(可食部105g)で塩分が4.3g含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| くさや | 3.2mg | 1枚150g(105g) | 3.4mg |
削り節は一度に使う量が少ない
削り節はカチカチに乾燥させるのでその分栄養素も濃縮されますが、削って使うので一度に使う量も少量で、その分とれる鉄分の量も限られます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 削り節 | 9.0mg | 大さじ2杯1g | 0.1mg |
 | 貝類・えび・軟体類で鉄分の多い食品 | ||
貝類・えび・軟体類で鉄分を特に摂りやすいものは?
貝類の中では特に特にタニシが鉄分が豊富で、シジミや赤貝、ほっきがい、えすかるご、アサリなども鉄分は多いです。エビ類では干しエビが鉄分が豊富です。軟体類だとほやが鉄分が多く含まれます。
たにしは鉄分が非常に豊富

たにしは昔は各地でよく食べられていたようですが、最近では食べる機会も減ってきています。茹でたものをそのまま食べたり、みそ煮や和え物、みそ汁などに利用します。鉄分の含有量が高く、量もとりやすいので鉄分の補給先としても適しています。たにしは10個(21g)で4.1mgの鉄分を摂取できます。ちなみに上の画像はたにしの佃煮です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| たにし | 19.4mg | 10個30g(21g) | 4.1mg |
ほやも鉄分が摂りやすい食品

ほやは刺身や酢の物などにしてよく食べられます。食べる際は包丁で固い上皮をはがして柔らかい中身を食べます。さばくのもそれほど手間はかかりません。ほやや鉄分が非常に豊富でまた量も摂りやすいので、鉄分を摂取しやすい食品の一つです。ほやは1個分で2.6mgの鉄分を摂取できます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ほや | 5.7mg | 1個230g(46g) | 2.6mg |
干しエビは少量でも鉄分が豊富

干しえびは1個単位の重量は小さいものの、鉄分が多く含まれるため多くの鉄分を摂取できます。干しエビは大さじ1杯(8g)で鉄分が1.2mg摂取できます。カルシウムも非常に豊富です。ちなみに上の画像は干しエビです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 干しえび | 15.1mg | 大さじ1杯(8g) | 1.2mg |
シジミは鉄分が豊富
しじみといえばお味噌汁にすればおいしい出汁が取れ、絶品のシジミ汁が味わえますが、鉄分も非常に豊富です。しじみ20個なら鉄分は1.2mg摂取できます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| しじみ | 8.3mg | 20個60g(16g) | 1.2mg |
赤がいも鉄分が多い
赤がいは名前の通り身が赤い色を帯びていて、貝類には珍しく血色素としてヘモグロビンを持っています。赤がいも鉄分が豊富で1個で1.2mgの鉄分を摂取できます。赤がいは寿司だねや刺身、酢の物、焼き物、汁物、煮物などに利用されます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 赤貝 | 5.0mg | 1個100g(25g) | 1.2mg |
ほっきがいも鉄分を取りやすい
ほっきがいはうばがいとも呼ばれ、茹でると紅色になるのが特徴です。刺身や寿司だね、酢の物、焼き物、汁物、炊き込みご飯などに利用されます。ほっきがいも1個で鉄分が3.1mgと多いので、鉄分摂取にはおすすめの食品の一つです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ほっきがい | 4.4mg | 1個200g(70g) | 3.1mg |
エスカルゴも鉄分が多く量も摂りやすい
エスカルゴは食用のカタツムリのことで、ローマ時代から食べられてきました。日本では水煮缶詰などがよく市販されています。鉄分も多く量も1缶で4.9mgもとれるので、鉄分を摂取しやすい食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| エスカルゴ(水煮缶詰) | 3.9mg | 1缶125g | 4.9mg |
このわたも鉄分が多い
このわたはナマコの腸管を塩漬けにしたもので、こちらも鉄分が多く含まれます。大さじ1杯で0.7mgの鉄分を摂取できます。一方ナマコ自体には100gでの鉄分含有量は0.1mgとほとんど含まれていません。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| このわた | 4.0mg | 大さじ1杯(17g) | 0.7mg |
アサリも鉄分が豊富
アサリも鉄分が豊富な食品の一つです。あさり10個で1.2mgの鉄分を摂取できます。あさりは汁物や酒蒸し、バター炒め、漁り飯、酢の物などにして食べられます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| あさり | 3.8mg | 10個80g(32g) | 1.2mg |
 | 肉類で鉄分の多い食品 | ||
摂るなら豚や鶏ではなく牛肝臓で

肝臓は鉄分の含有量も多く1回で量も取れるので、たくさんの鉄分を摂取することが出来ます。豚肝臓一切れ(30g)で鉄分が3.9mg、鶏肝臓一個(40g)で鉄分が3.6mg摂取できます。
ただし妊娠中は豚や鶏のレバーの摂取は控えたほうがいいでしょう。ビタミンAの多い食品・食べ物と含有量一覧を見てもらってもわかると思いますが、豚や鶏のレバーにはビタミンAであるレチノールが非常にたくさん含まれています。レチノールは過剰に摂取すると胎児の奇形発生のリスクが高まることが知られています。豚や鶏のレバーは1切れでも上限量を超えてしまうので妊娠中の鉄分補給が目的でもこうした食品の摂取は控えたほうがいいでしょう。
肝臓でも牛肝臓の場合は、レチノールの量も豚や鶏と比べると控えめなので、摂取するなら牛肝臓の方がいいでしょう。牛肝臓は1切れ(40g)で鉄分が1.6mg摂取できます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 豚肝臓 | 13.0mg | 1切れ30g | 3.9mg |
| 鶏肝臓 | 9.0mg | 1個40g | 3.6mg |
| 牛肝臓 | 4.0mg | 1切れ40g | 1.6mg |
牛肉は特に赤身部分に鉄分が豊富
牛肉は鳥や豚にくらべて鉄分の含有量が多いです。特に赤身の部分に鉄分が豊富です。例えば国産牛の肩ロース100gだと鉄分は0.7mgですが赤肉の部分に限れば2.4mg含まれています。サーロインは全体だと0.9mgですが赤身部分は2.0mgの鉄分が含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 牛肩ロース | 0.7mg | 100g | 0.7mg |
| 牛肩ロース赤肉 | 2.4mg | 100g | 2.4mg |
| 牛サーロイン | 0.9mg | 100g | 0.9mg |
| 牛サーロイン赤肉 | 2.0mg | 100g | 2.0mg |
牛肉の鉄分の多い部位は?

牛肉の部位で見ると100gあたりで牛もも肉と牛ひれ肉が鉄分が2.5mgと多く、次いで牛ひき肉2.4mg、牛バラ肉1.4mg、牛ランプ肉1.4mg、牛かた肉0.9mg、サーロイン0.9mgと続きます。ちなみに上の画像は牛ひれ肉です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 牛ひれ肉 | 2.5mg | 厚1cm1枚100g | 2.5mg |
| 牛もも肉 | 2.5mg | 薄1枚70g | 1.7mg |
| 牛ひき肉 | 2.4mg | 卵大ひとかたまり50g | 1.2mg |
| 牛ばら肉 | 1.4mg | 薄1枚50g | 0.7mg |
| 牛らんぷ肉 | 1.4mg | 薄1枚70g | 0.9mg |
| 牛かた肉 | 0.9mg | 薄1枚50g | 0.4mg |
| サーロイン | 0.9mg | 薄1枚50g | 0.4mg |
コンビーフも鉄分を取りやすい

コンビーフも鉄分が豊富で量も摂りやすい食品です。コンビーフ1缶(100g)で鉄分が3.5mg摂取できます。コンビーフとは塩漬けした牛肉を高温高圧で加熱し、ほぐして味付けをしたものです。缶詰でよく販売されています。塩分が100g当たり1.8gと多いので、取りすぎには注意が必要です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| コンビーフ缶詰 | 3.5mg | 小1缶100g | 3.5mg |
ビーフジャーキーも鉄分が豊富

ビーフジャーキーも鉄分が豊富です。ビーフジャーキーは1枚あたり5gほどで、一袋50gでは3.2mgの鉄分が摂取できます。ただしこちらも食塩が一袋当たり2.4gと多いので摂りすぎには注意が必要です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ビーフジャーキー | 6.4mg | 1袋50g | 3.2mg |
その他肉類で鉄分の多い食品
牛や豚、鶏以外では馬や鴨、やぎやシカ肉も鉄分が豊富に含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| いなご(佃煮) | 4.7mg | 10尾15g | 0.7mg |
| 馬肉 | 4.3mg | 刺身一切れ15g | 0.6mg |
| 鴨肉 | 4.3mg | 薄1枚40g | 1.7mg |
| やぎ肉 | 3.8mg | 厚1cm1枚100g | 3.8mg |
| 鹿肉 | 3.1mg | 厚1cm1枚100g | 3.1mg |
| フォアグラ(ゆで) | 2.7mg | 厚1cm角6cm45g | 1.2mg |
| いのしし肉 | 2.5mg | 薄1枚15g | 0.7mg |
 | 卵類で鉄分の多い食品 | ||

卵に含まれる鉄分は卵黄部分に集中していて、卵白にはまったく含まれていません。ただし卵黄に含まれるリンたんぱく質と鉄分ががっちりと結合しているため、吸収率はそれほど高くないと考えられています。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 卵黄 | 6.0mg | 1個分18g | 1.1mg |
| うずら卵 | 3.1mg | 1個10g(9g) | 0.3mg |
| ピータン | 3.0mg | 1個100g(55g) | 1.7mg |
 | 藻類で鉄分の多い食品 | ||
青のりは少量でも鉄分がたくさん摂れる

焼きのりやほしのり、味付け海苔は鉄分の含有量は多いのですが、一度に摂取できる量がすくないので鉄分の補給先としてはそれほど効率的では有りません。あおのりはもともとの鉄分含有量が非常に多いので、食品としての摂取量が少なくても鉄分を多く摂取することが出来ます。青のりは大さじ1杯(2g)と少量でも1.5mgの鉄分を摂取できます。青のりは焼きそばやお好み焼き、パスタやたこ焼きなどに振りかけたり、てんぷら粉に混ぜて磯部揚げなどにして利用されます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| あおのり(素干し) | 77.0mg | 大さじ1杯2g | 1.5mg |
| 焼きのり | 11.4mg | 10枚3g | 0.3mg |
| ほしのり | 10.7mg | 1枚3g | 0.3mg |
| 味付け海苔 | 8.2mg | 10枚3g | 0.2mg |
いわのりも鉄分を摂取しやすい
いわのりも素干し1枚(10g)で鉄分が4.8mgとかなりの量を摂取できます。こちらも藻類の中でもかなり鉄分を摂取しやすい食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 岩のり(素干し) | 48.3mg | 1枚10g | 4.8mg |
ほしひじきは鉄釜利用で鉄分アップ

ほしひじきも100gあたり58.2mgと鉄分が非常に多く含まれている食品として有名です。しかしこれは調理の際に使う鉄釜から染み出る鉄分の影響が大きいため、これをステンレス釜で調理した場合、鉄分の量は100gあたり6.2mgと大きく減少します。鉄分をしっかりと摂取したいならほしひじきは鉄釜を利用するようにしましょう。
ひじきは水で戻したものをゆでて調理します。茹でるとかさが7倍ほどになります。ひじきの煮物1人前では水で戻したひじきの重量は70gほどです。ひじきはゆでた状態では鉄分の量は100gあたり2.7mgまで落ちます。1人前だと1.9mgほどです。それでもひじきの煮物から摂取できる鉄分の量は結構なものです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ほしひじき(乾・鉄釜) | 58.2mg | 大さじ1杯4g | 2.3mg |
| ほしひじき(乾・ステンレス釜) | 6.2mg | 大さじ1杯4g | 0.2mg |
| ほしひじき(ゆで・鉄釜) | 2.7mg | 1人前70g | 1.9mg |
| ほしひじき(ゆで・ステンレス釜) | 0.3mg | 1人前70g | 0.2mg |
 | 豆類で鉄分の多い食品 | ||
きなこは摂取量が限られる
豆類は全般的に鉄分がよく含まれている食品群です。特にきな粉は鉄分がたくさん含まれています。きな粉を使った代表的な料理といえばきな粉もちですが1個あたりのきな粉の使用量は大さじ1/2ほどです。粉末で利用するためそれほど量を摂取することはできません。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| きな粉(全粒大豆) | 8.0mg | 大さじ1杯7g | 0.6mg |
| きな粉(脱皮大豆) | 6.2mg | 大さじ1杯7g | 0.4mg |
フライビーンズは鉄分が摂りやすい

フライビーンズはそら豆を種皮が付いたまま油で揚げて味付けしたものです。別名いかり豆とも言います。フライビーンズ10粒(20g)で1.5mgの鉄分を摂取できます。比較的量も摂りやすいので鉄分を摂取しやすい食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| フライビーンズ | 7.5mg | 10粒20g(20g) | 1.5mg |
おたふく豆も鉄分が摂りやすい

おたふく豆は皮が付いたそら豆を砂糖煮にしたものです。10粒(70g)で鉄分は3.7mgあるので、こちらも鉄分を摂取しやすい食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| おたふく豆 | 5.3mg | 10粒70g(70g) | 3.7mg |
がんもどきも鉄分が豊富

大豆の加工食品でおでんの具材としてもよく見かけるがんもどきも鉄分を摂取しやすい食品です。がんもどきは水を切って潰した豆腐に野菜、昆布、ぎんなん、ゴマ等を混ぜたものを油で揚げて作ります。がんもどき1個(100g)で鉄分が3.6mg摂取できます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| がんもどき | 3.6mg | 1個100g(100g) | 3.6mg |
糸引き納豆も鉄分が摂りやすい

糸引き納豆も鉄分の取りやすい食品です。1パック(50g)で1.7mgの鉄分を摂取できます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 糸ひき納豆 | 3.3mg | 1パック50g | 1.7mg |
その他豆類で亜鉛の多い食品
ほかにもグリンピースや湯葉(生)、油揚げ、こし餡なども鉄分が豊富な食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| グリンピース(揚げ豆) | 5.4mg | 大さじ1杯10g | 0.5mg |
| 湯葉(生) | 3.6mg | 1枚30g | 1.1mg |
| 油揚げ | 3.2mg | 1枚30g(30g) | 0.9mg |
| こしあん | 2.8mg | 大さじ1杯20g | 0.6mg |
フィチン酸で鉄分の吸収率が低下
また豆類や穀類にはリン酸化合物であるフィチン酸が含まれていて、このフィチン酸は鉄や亜鉛などのミネラルとくっついて体内での吸収率を下げてしまう働きもあります。ただしフィチン酸は動物性たんぱく質を一緒にとるとミネラルへの影響を小さくすることが出来るので一緒に摂取するといいでしょう。
 | 種実類で鉄分の多い食品 | ||

種実類は全般に鉄分はそれなりに含まれていますが、1粒あたりの重量が1g前後と少ないものが多いため、なかなか量を摂取しづらい食品群です。種実類だけで鉄分を十分に摂取するのはなかなか難しいといえます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ごま(いり) | 9.9mg | 大さじ1杯6g | 0.6mg |
| カシューナッツ(フライ) | 4.8mg | 10粒15g(15g) | 0.7mg |
| ひまわりの種 | 3.6mg | 大さじ1杯9g | 0.3mg |
| ピスタチオ(いり) | 3.0mg | 10粒8g(4g) | 0.1mg |
| アーモンド(フライ) | 2.9mg | 10粒14g(14g) | 0.4mg |
| くるみ(いり) | 2.6mg | 1個4g(4g) | 0.1mg |
 | 穀類で鉄分の多い食品 | ||
ポップコーンは鉄の含有量も多く食事でも量をとりやすい食品です。小麦胚芽はごはんにかけたり、クッキーの材料に混ぜて使います。
同じ含有量でも鉄の吸収率では植物性食品は動物性食品には劣ります。


| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 小麦胚芽 | 9.4mg | 大さじ1杯8g | 0.8mg |
| ポップコーン | 4.3mg | 1袋70g | 3.0mg |
| 焼きふ(観生ふ) | 3.3mg | 1個3g | 0.1mg |
 | 調味料類で鉄分の多い食品 | ||
みその種類では豆みそが他のみそよりも鉄が多く含まれています。みそ汁1杯で使うみその量は大体大さじ1杯なので、豆みそを使ったみそ汁1杯だと1.2mgの鉄分が摂取できます。バジルやセージ、タイムなどの香辛料は使う量は極少量ですが非常に多くの鉄分が含まれているため、たくさんの鉄分を摂取できます。


| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| バジル | 120.0mg | 小さじ1杯2g | 2.0mg |
| タイム | 110.0mg | 小さじ1杯2g | 2.2mg |
| セージ | 50.0mg | 小さじ1杯3g | 1.5mg |
| カレー粉 | 28.5mg | 大さじ1杯6g | 1.7mg |
| 豆みそ | 6.8mg | 大さじ1杯18g | 1.2mg |
| 甘みそ | 3.4mg | 大さじ1杯18g | 0.6mg |
| 麦みそ | 3.0mg | 大さじ1杯18g | 0.5mg |
 | その他食品で鉄分の多い食品 | ||
野菜類で鉄分の多い食品
パセリやよもぎ、えだまめは鉄の含有量は多いものの、一度に摂取できる量が少ないので、鉄分の補給先としてはあまり効率的では有りません。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| パセリ | 7.5mg | 1本5g(5g) | 0.4mg |
| よもぎ(ゆで) | 3.0mg | 一掴み18g | 0.5mg |
| えだまめ(ゆで) | 2.5mg | 10鞘25g(13g) | 0.3mg |
茶類で鉄分の多い食品
和菓子などでもよく使われる抹茶は鉄のそもそもの含有量が多いため、大さじ1杯ふりかけるだけでも1.0mgの鉄分を摂取できます。

| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 抹茶(粉末) | 17.0mg | 大さじ1杯6g | 1.0mg |
砂糖及び甘味類で鉄分の多い食品
砂糖及び甘味類は全般に鉄分はほとんど含まれませんが黒砂糖には鉄分が多く含まれます。ただし大さじ1杯で9gなので使う量にもよりますがそれほど一度にたくさんの鉄分を摂取できるものでもありません。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 黒砂糖 | 4.7mg | 大さじ1杯9g | 0.4mg |
 | 鉄分の主な働き | ||
鉄分には次のような働きがあります。
鉄分は赤血球内のヘモグロビンの構成成分です。鉄は酸素と結びつきやすいのでその働きを利用し、ヘモグロビンは肺で酸素を受け取り、各種組織へと酸素を運搬する働きがあります。このように体内での酸素運搬には鉄分は欠かせない栄養素なのです。鉄分が不足するとヘモグロビンの合成に影響が出るため鉄欠乏性貧血を引き起こします。
筋肉は体内でも特に酸素の消費量が多く、このため筋肉細胞内にはミオグロビンという酸素を貯蔵しておくたんぱく質があります。ミオグロビンの中にも鉄が含まれます。ミオグロビンはヘモグロビンから酸素を受け取って貯蔵して起き、必要に応じて貯蔵しておいた酸素が消費されます。
鉄は肝臓内でP-350と呼ばれる酵素の構成成分として体外から侵入してきた毒物の分解に関与します。
活性酸素は細菌やウイルスを攻撃する免疫機能を担っていて本来体に必要なものですが、その量が増えすぎると正常な細胞にも攻撃し始めます。そのため活性酸素除去酵素が増えすぎた活性酸素を除去する働きを担います。鉄は活性酸素除去酵素であるカタラーゼやスーパーオキシドジスムターゼの構成成分としてその働きに関与します。
摂取した糖質や資質、たんぱく質は、体内で代謝されエネルギー源であるATP(アデノシン3リン酸)が作られます。鉄分はATPが作られる電子伝達系において、その構成成分としてATPの生成に関与します。
貧血を予防する
鉄分は赤血球内のヘモグロビンの構成成分です。鉄は酸素と結びつきやすいのでその働きを利用し、ヘモグロビンは肺で酸素を受け取り、各種組織へと酸素を運搬する働きがあります。このように体内での酸素運搬には鉄分は欠かせない栄養素なのです。鉄分が不足するとヘモグロビンの合成に影響が出るため鉄欠乏性貧血を引き起こします。
筋肉内で酸素の貯蔵
筋肉は体内でも特に酸素の消費量が多く、このため筋肉細胞内にはミオグロビンという酸素を貯蔵しておくたんぱく質があります。ミオグロビンの中にも鉄が含まれます。ミオグロビンはヘモグロビンから酸素を受け取って貯蔵して起き、必要に応じて貯蔵しておいた酸素が消費されます。
肝臓での解毒作用
鉄は肝臓内でP-350と呼ばれる酵素の構成成分として体外から侵入してきた毒物の分解に関与します。
活性酸素の除去
活性酸素は細菌やウイルスを攻撃する免疫機能を担っていて本来体に必要なものですが、その量が増えすぎると正常な細胞にも攻撃し始めます。そのため活性酸素除去酵素が増えすぎた活性酸素を除去する働きを担います。鉄は活性酸素除去酵素であるカタラーゼやスーパーオキシドジスムターゼの構成成分としてその働きに関与します。
ATPの生成に関与
摂取した糖質や資質、たんぱく質は、体内で代謝されエネルギー源であるATP(アデノシン3リン酸)が作られます。鉄分はATPが作られる電子伝達系において、その構成成分としてATPの生成に関与します。
 | ヘム鉄が吸収率が高い理由 | ||
ヘム鉄は受容体で効率的に吸収される
ヘム鉄はポリフィリンと呼ばれるたんぱく質に囲まれた中の中心に鉄が存在するという構造をしていて、その中心にある鉄がヘム鉄とよばれます。小腸にはヘム鉄を取り込むための受容体があり、効率的に吸収されます。摂取したヘム鉄がそのままシンプルに吸収されるので吸収効率が高いわけです。
非ヘム鉄はヘム鉄より吸収までの段階が多い
一方非ヘム鉄の場合、胃酸で鉄イオンへと遊離(分離)された後、鉄イオンである三価鉄から小腸で吸収されやすい二価鉄へと還元される必要があります。これには小腸粘膜にある還元酵素の助けを借りる必要があります。このように食品から摂取して吸収されるまでにヘム鉄よりも段階を経る必要があるため吸収率にも差が出てしまうわけです。
非ヘム鉄は他の成分の影響も受けやすい
また非ヘム鉄の場合は吸収されるまでにほかの成分の影響もうけやすくなっています。例えばビタミンCやクエン酸といった還元作用のある成分により吸収効率が促進されたり、穀物のフィチン酸や茶のタンニン酸、卵黄のホスビチン、ホウレン草やココアのシュウ酸などと結合することでイオン化が妨げられ、吸収効率が低下したりします。
 | 鉄分を摂取する上でのポイント | ||
鉄分が不足しやすいのは?
鉄分は特に成長期の男女で需要量が増加するので欠乏しないようにしっかりと摂取することが大事です。また女性は月経により体外に血液とともに鉄分も流出してしまいます。また妊婦も胎児の成長や授乳に鉄分がその分多く必要となります。月経時の女性や妊婦も鉄分の不足には注意が必要です。それ以外でもひどい出血を伴うけがや消化管内の潰瘍やポリープによる出血も鉄欠乏の一因となります。こうした方は鉄分をしっかりととるとともにそもそもの原因であるけがや病気を治すことも大事です。
潜在性鉄欠乏症に注意
体内での鉄分には赤血球のヘモグロビンや筋肉内のミオグロビンなどに存在する機能鉄と、肝臓や脾臓で蓄えられている貯蔵鉄があります。ヘモグロビンは体内で酸素運搬に関わる非常に重要なもので、けがや生理などでの出血や鉄分の摂取不足により鉄が不足した場合には、まずは機能鉄ではなく貯蔵鉄が消費されていきます。ヘモグロビンなどの機能鉄の量は維持されるのでこの時点では貧血などの鉄欠乏症があらわれません。
しかしながら症状が現れていないとはいえ、体内での鉄が足りずに貯蔵鉄が切り崩されている状態です。この状態を潜在性鉄欠乏症といいます。症状が現れるのはかなり進んだ状態なので、けがや生理など貧血の要因を抱えている方は、普段からしっかりと鉄分の摂取を心がけておくことが大事だといえます。
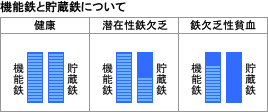
月経過多の女性は鉄剤の利用も
女性は平時と月経時では成人女性で推奨量が4mgほど違います。平時なら推奨量は6.5mgですが月経時は10.5mgになります。これは通常の月経時を想定したもので月経過多で通常の倍以上の80mL以上の経血を伴った場合は、鉄分の推奨量は16mgにまで増やされます。この量を通常の食事から摂取するのはなかなか困難です。そのため鉄剤などの利用が必要となりますが、まずは基礎疾患の有無などの確認も必要となるので医師の診断と指導を受けたうえで行うようにしましょう。
 | 鉄の吸収・活性を促すビタミン・ミネラル | ||
ビタミンC
鉄にはヘム鉄と非ヘム鉄があり、腸管での吸収率は非ヘム鉄で2〜5%、ヘム鉄で15〜20%と大きな開きがあることはすでに上記でも述べてきました。ビタミンCはこの吸収率の劣る非ヘム鉄の吸収効率を高める働きがあります。
非ヘム鉄は三価鉄と呼ばれる状態から二価鉄へと変化して小腸上皮から吸収されますが、三価鉄から二価鉄への還元には小腸粘膜にあるDcyt1と呼ばれる酵素が必要です。ビタミンCにはDcyt1と同様三価鉄を二価鉄へと還元する働きがあります。これにより還元が進み非ヘム鉄の吸収効率があがります。実際にいくつかの実験結果でもビタミンCを混ぜた食事と鉄を一緒にとると鉄の吸収率が上がることも報告されています。ビタミンCの多い食品は以下で解説しています。
ビタミンCの多い食品
銅
鉄はアポトランスフェリンと呼ばれる鉄輸送たんぱく質と結合することで各種臓器へと運ばれます。アポトランスフェリンと鉄が結合するためにはセルロプラスミンと呼ばれる酵素が必要で、この酵素の補酵素として働くのが銅です。銅が不足すると十分にセルロプラスミンが働かなくなり、鉄とアポトランスフェリンとの結合も滞るので、各臓器への鉄輸送が停滞し、鉄欠乏性の貧血を引き起こします。鉄がしっかりと各臓器へと運ばれるためには銅もしっかりと取ることが大事なのです。銅の多い食品については以下で解説しています。
銅の多い食品
 | 鉄の吸収・活性を促すその他の要素 | ||
動物性たんぱく質
動物性食品に含まれるたんぱく質には植物性食品に含まれる非ヘム鉄の吸収率をよくする働きがあります。非ヘム鉄も効率よく摂取したいなら動物性食品といっしょに摂取するといいでしょう。
クエン酸、リンゴ酸
果物などに多く含まれているクエン酸やリンゴ酸もそのキレート作用により鉄の吸収率をよくする働きがあります。キレートとはミネラルを包み込んで吸収しやすい形にする反応のことです。
 | まとめ | ||
吸収率が高い分動物性食品がおすすめ
すでに最初にも述べましたが、動物性食品に含まれるヘム鉄のほうが植物性食品に含まれる非ヘム鉄よりも吸収率が高いので、同じ程度の量なら動物性食品から取るヘム鉄のほうが鉄の補給先としては優れているといえます。動物性食品で鉄が多いのは魚介類や肉類で、量も取りやすいことから補給先としても非常に適しています。
動物性食品で鉄分の多い食品
肉類では牛肉の特に赤身の部分に多く含まれ、馬、鴨、やぎ、鹿肉などにも鉄分は多く含まれます。魚介類では干しエビや煮干し、はぜの佃煮、めざし、くさやといった干物や乾物、つくだ煮料理などに多く含まれます。またどじょうや鮎、タニシ、赤貝、ほっきがい、ほやといった食品にも多く含まれます。
植物性食品は藻類やバジル、タイムなどに多い
植物性食品なら青のりや岩のりなどの藻類に非常に多くの鉄分が含まれます。干しヒジキも鉄分が豊富な食品の一つです。他にもバジルたタイムなどの粉末にも鉄分は豊富に含まれます。ゴマやカシューナッツなどの種実類にも鉄分は豊富に含まれますが、一度にとれる量が少量なのでその分鉄分の摂取量も少なくなります。豆類にも鉄分はふくまれますが、鉄分の吸収を阻害するフィチン酸の影響で吸収率はおちます。動物性食品と比べて吸収率の落ちる植物性食品ですが、ビタミンCと一緒に摂取することで吸収効率が高まります。
鉄を特にとりやすい食品
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| たにし | 19.4mg | 10個30g(21g) | 4.1mg |
| 煮干し | 18.0mg | 10尾20g(20g) | 3.6mg |
| どじょう | 5.6mg | 10尾80g(80g) | 4.5mg |
| あゆ(焼き) | 5.5mg | 3尾165g(75g) | 3.9mg |
| 赤貝 | 5.0mg | 3個300g(75g) | 3.6mg |
| ほっきがい | 4.4mg | 1個200g(70g) | 3.1mg |
| くさや | 3.2mg | 1枚150g(105g) | 3.4mg |
| 豚肝臓 | 13.0mg | 1切れ30g | 3.9mg |
| 鶏肝臓 | 9.0mg | 1個40g | 3.6mg |
| ビーフジャーキー | 6.4mg | 1袋50g | 3.2mg |
| 馬肉 | 4.3mg | 刺身5切れ90g | 3.0mg |
| 鴨肉 | 4.3mg | 薄2枚80g | 3.4mg |
| 牛肝臓 | 4.0mg | 2切れ80g | 3.2mg |
| やぎ肉 | 3.8mg | 厚1cm1枚100g | 3.8mg |
| 鹿肉 | 3.1mg | 厚1cm1枚100g | 3.1mg |
|
参考文献
7訂日本食品成分表2016 5訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表 日本人の食事摂取基準2015年版 スタンダード栄養食物シリーズ基礎栄養学 新赤本第6版家庭の医学 オールガイド食品成分表 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
|
最終更新日 2021/03/26 |
微量ミネラルの多い食品・食べ物一覧
 |
亜鉛の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
銅の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
マンガンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ヨウ素の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
セレンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
クロムの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
モリブデンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
コバルトの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
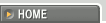
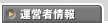
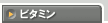
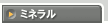
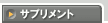
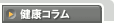



 微量ミネラル
微量ミネラル
