 |

|
|
銅の多い食品・食べ物と含有量一覧

 | 銅を多く含む食品 | ||
銅は魚介類、種実類、豆類などによく含まれます。魚介類なら干しエビやエスカルゴ、しゃこ、ホタルイカ、いいだこ、ワタリガニなどに、種実類ならブラジルナッツ、ヒマワリの種、カシューナッツなどに、豆類なら糸引き納豆などに銅が多く含まれます。他にも牛レバーも銅が非常に多く含まれる食品の一つです。
ここではまずは銅の主な働きと推奨量について見ていき、各食品群ごとに銅の多い食品を詳しく見ていくことにします。
ここではまずは銅の主な働きと推奨量について見ていき、各食品群ごとに銅の多い食品を詳しく見ていくことにします。
 | 銅の主な働き | ||
酵素を通して様々な生理作用に関わる
銅は酵素の構成成分として様々な生理反応と関わります。銅がかかわる酵素によってもたらされる作用には活性酸素の除去や免疫機能の維持、エネルギー代謝や血液凝固の促進、神経伝達物質の生成、生殖機能の維持などがあります。
鉄の吸収とヘモグロビンの合成に関与
銅は腸管での鉄の吸収促進と、体内での鉄の運搬に関与します。銅が不足すると鉄の吸収や運搬も滞ります。その結果、鉄を材料とするヘモグロビンの合成も滞ります。ヘモグロビンは酸素の運搬を担うので、ヘモグロビンの合成が滞ると貧血が起こります。
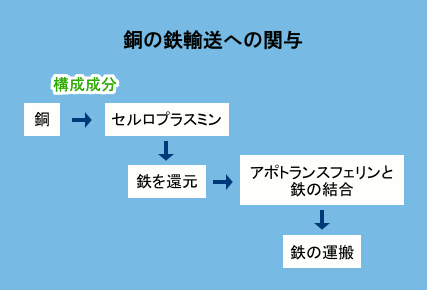
メラニン色素合成に関与
銅はメラニン色素の合成にも関与します。このため銅が不足するとメラニン色素の合成が滞り、色素沈着が低下して髪の毛や皮膚の色が薄くなります。
 | 銅摂取の推奨量、上限量 | ||
日本食事摂取基準では銅の1日の推奨量は成人男性が0.9mgに、成人女性が0.7mgと定められています。銅は日本人の1日の平均摂取量でも推奨量を満たしており、通常の食生活であれば不足することはまれです。
銅は通常の食生活であれば過剰摂取に至ることはありませんが、サプリメントなどで大量に摂取した場合には過剰摂取となる可能性があります。そのため1日の耐容上限量が7mgと定められています。
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。
銅は通常の食生活であれば過剰摂取に至ることはありませんが、サプリメントなどで大量に摂取した場合には過剰摂取となる可能性があります。そのため1日の耐容上限量が7mgと定められています。
|
銅成人男子目安量:0.9mg 銅成人女子目安量:0.7mg |
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。
 | 魚介類で銅の多い食品 | ||
魚介類で特に銅を摂取しやすいもの
魚介類は特に動画多く含まれる食品群です。中でも貝やエビ、イカやタコには銅が多く含まれます。干しエビやしゃこ、エスカルゴ、ほたるいか、いいだこ、するめ、わたりがに、さざえは量も摂りやすく銅の摂取に優れた食品です。
干しエビは銅が豊富

干しエビは100g当たりの銅の含有量が非常に多く、食事でとれる量が少量でもたくさんの銅を摂取できます。干しエビは中華料理で使われることが多く、そのまま食べてもおいしいです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 干しエビ | 5.17mg |
大さじ1杯8g 大さじ2杯16g |
0.41mg 0.82mg |
しゃこは銅を特に摂取しやすい
しゃこも銅の含有量が高く、また量も摂りやすいので銅を摂取しやすい食品です。しゃこは寿司だねやてんぷらなどにして食べられます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| しゃこ(ゆで) | 3.46mg | 1個30g | 1.03mg |
エスカルゴも銅が多い
エスカルゴは食用カタツムリのことでヨーロッパで昔から食べられてきたものです。日本では水煮にした缶詰などがよく市販されています。炒めたりそのままサラダやスープに入れてもおいしいです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| エスカルゴ(水煮缶詰) | 3.07mg | 1缶125g | 3.83mg |
ホタルイカも銅が豊富
ホタルイカも銅が豊富で量も摂りやすい食品です。ホタルイカは生食の煮物や佃煮、乾物、酢味噌あえなどにして食べられます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ほたるいか | 2.97mg |
1杯5g 5杯25g |
0.14mg 0.74mg |
いいだこも銅が摂りやすい
たこの中ではいいだこが特に銅が豊富です。いいだこは体長20cmほどの小ぶりなたこです。銅も多く量も摂りやすいので非常の銅を摂りやすい食品です。体長が60cm〜1mほどのまだこは銅の含有量はそれほど多くはありません。ただし量が取れる分こちらも銅を摂取しやすい食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| いいだこ | 2.96mg | 1杯60g | 1.77mg |
| まだこ | 0.30mg | 足1本150g | 0.45mg |
わたりがにも銅が多い

わたりがに(がざみ)銅が多く含まれ、食事としても量がとりやすいです。わたりがにはゆでたり焼いて食べるとおいしいです。からは比較的柔らかく食べやすいです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| わたりがに(がざみ) | 1.10mg | 1杯200g(70g) | 0.77mg |
するめも銅が豊富

するめも銅が豊富で量も摂りやすい食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| するめ | 0.99mg | 1枚100g | 0.99mg |
かきも銅を摂りやすい

かきも銅を摂りやすい食品です。生ガキ、酢ガキ、フライ、炒め物、なべ物などにして食べられます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| かき | 0.89mg |
1個60g(15g) 4個240g(60g) |
0.13mg 0.53mg |
その他魚介類でビタミンKが多い食品
上にあげた魚介類は100g当たりの銅の含有量も高く、食事として量も摂りやすいものです。以下であげる食品でサクラエビやいくらは100g当たりの銅の含有量は高いものの、食事として量を摂りづらいものです。たにしやさざえにかんしては上の魚介類ほどではありませんが比較的銅を摂れる食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| さくらえび(素干し) | 3.34mg | 大さじ1杯3g | 0.10mg |
| たにし | 1.90mg | 10個30g(21g) | 0.40mg |
| さざえ(焼き) | 0.73mg |
1個25g 2個50g |
0.18mg 0.36mg |
| いくら | 0.73mg | 大さじ1杯17g | 0.12mg |
 | 種実類で銅の多い食品 | ||
種実類で特に銅を摂取しやすいもの
種実類は100gあたりで銅の含有量が高いものもおおいですが、一度の食事でそれほどたくさん摂れるものでもないので、摂取できる銅の量にも限りがあります。そんな中ブラジルナッツ、カシューナッツ、ヒマワリの種は少量でも比較的たくさんの銅を摂取することができます。
ブラジルナッツは銅を摂りやすい

ブラジルナッツはアーモンドにも似た風味があり、日本ではブラジルからの輸入品が多いです。銅の含有量も高く少量でも銅を摂りやすい食品です。。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ブラジルナッツ(フライ) | 1.95mg | 10粒30g | 0.58mg |
カシューナッツも銅が豊富
カシューナッツもブラジルが原産で、おつまみとしても比較的スーパーなどでもよく見かけます。こちらも銅の含有量が多く少量でも量も摂りやすい食品です。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| カシューナッツ(フライ) | 1.89mg |
10粒15g 20粒30g |
0.28mg 0.56mg |
ひまわりの種も銅が多い

ひまわりの種も銅を摂取しやすい食品です。こちらも大きなスーパーなどでは比較的よく見かけます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ひまわりの種 | 1.81mg | 大さじ1杯9g 大さじ3杯27g |
0.16mg 0.48mg |
その他種実類で銅が多い食品
以下の食品は上の食品ほどではありませんが種実類で100gあたりでの銅の含有量の高い食品です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ごま(いり) | 1.68mg | 大さじ1杯6g | 0.10mg |
| かぼちゃの種(いり) | 1.26mg | 大さじ1杯10g | 0.12mg |
| くるみ(いり) | 1.21mg |
1粒5g 4粒20g |
0.6mg 0.24mg |
| ピスタチオ(いり) | 1.15mg | 10粒8g(4g) | 0.04mg |
| アーモンド(フライ) | 1.11mg | 10粒14g | 0.15mg |
 | 肉類で銅の多い食品 | ||

肉類ではレバーに特に銅が多く含まれます。中でも牛肝臓には一切れでも非常にたくさんの銅を摂取することができます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 牛肝臓 | 5.30mg | 1切れ40g | 2.12mg |
| フォアグラ | 1.85mg | 1切れ45g | 0.83mg |
| 豚肝臓 | 0.99mg | 1切れ30g | 0.29mg |
 | 豆類で銅の多い食品 | ||

豆類ではフライビーンズ(いかり豆)や湯葉(生)糸引き納豆に銅が多いです。この中だと納豆が比較的銅を摂りやすいです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| きなこ | 1.12mg | 大さじ1杯6g | 0.06mg |
| フライビーンズ | 0.77mg | 10粒20g | 0.15mg |
| 湯葉(生) | 0.70mg | 1枚30g | 0.21mg |
| 糸引き納豆 | 0.61mg | 1パック50g | 0.30mg |
 | 香辛料で銅の多い食品 | ||
香辛料ではバジル、とうがらし、こしょうなどが100gあたりで銅の含有量が高いですが、使う量が少量なので摂れる銅の量も限られます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| バジル | 1.99mg | 小さじ1杯2g | 0.04mg |
| とうがらし | 1.20mg | 小さじ1杯2g | 0.02mg |
| こしょう | 1.00mg | 小さじ1杯2g | 0.02mg |
 | まとめ | ||
魚介類は銅を摂りやすい
魚介類、なかでもかにやいか、えびや貝類には胴も多く、食事として量も摂りやすい食品がたくさんあります。干しエビやえすかるご、わたりがにやしゃこ、ホタルイカなどどれも一度にたくさんの銅を摂取することができます。
種実類も銅が多い
種実類も銅の含有量が非常に高いです。中でもブラジルナッツやヒマワリの種、カシューナッツは一度にたくさんの銅を摂取することができます。他にも牛レバーも銅が非常に多い食品の一つです。
銅を特にとりやすい食品
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 干しエビ | 5.17mg | 大さじ2杯16g | 0.82mg |
| しゃこ(ゆで) | 3.46mg | 1個30g | 1.03mg |
| エスカルゴ(水煮缶詰) | 3.07mg | 1缶125g | 3.83mg |
| ほたるいか | 2.97mg | 5杯25g | 0.74mg |
| いいだこ | 2.96mg | 1杯60g | 1.77mg |
| わたりがに(がざみ) | 1.10mg | 1杯200g(70g) | 0.77mg |
| するめ | 0.99mg | 1枚100g | 0.99mg |
| かき | 0.89mg | 4個240g(60g) | 0.53mg |
| ブラジルナッツ(フライ) | 1.95mg | 10粒30g | 0.58mg |
| カシューナッツ(フライ) | 1.89mg | 20粒30g | 0.56mg |
| ひまわりの種 | 1.81mg | 大さじ3杯27g | 0.48mg |
| 牛肝臓 | 5.30mg | 1切れ40g | 2.12mg |
| フォアグラ | 1.85mg | 1切れ45g | 0.83mg |
 | 銅の成人推奨量 | ||
銅の1日の推奨量は成人男子で0.9mg、成人女子で0.7mgです。銅は年齢とともに推奨量も増えていき、男性は15〜17歳と65〜74歳までが最も高くて0.9mgになります。女性は12〜14歳までが0.8mgと最も高くてそこから70歳未満まで銅の推奨量は変わりません。上限量は男女とも7mgに定められています。
 銅の年代別食事摂取基準
銅の年代別食事摂取基準
| 年齢 | 男性(mg) | 女性(mg) | ||||||
|
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
| 0〜5 (月) | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - |
| 6〜11 (月) | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - |
| 1〜2 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | - |
| 3〜5 | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - |
| 6〜7 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - |
| 8〜9 | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - |
| 10〜11 | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - |
| 12〜14 | 0.7 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.8 | - | - |
| 15〜17 | 0.8 | 0.9 | - | - | 0.6 | 0.7 | - | - |
| 18〜29 | 0.7 | 0.9 | - | 7 | 0.6 | 0.7 | - | 7 |
| 30〜49 | 0.7 | 0.9 | - | 7 | 0.6 | 0.7 | - | 7 |
| 50〜64 | 0.7 | 0.9 | - | 7 | 0.6 | 0.7 | - | 7 |
| 65〜74 | 0.7 | 0.9 | - | 7 | 0.6 | 0.7 | - | 7 |
| 75以上 | 0.7 | 0.8 | - | 7 | 0.6 | 0.7 | - | 7 |
| 妊婦 | +0.1 | +0.1 | - | - | ||||
| 授乳婦 | +0.5 | +0.6 | - | - | ||||
※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2020年版)
各指標の見方について
|
参考文献
七訂食品成分表2016 五訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表 日本人の食事摂取基準2015年版 日本人の食事摂取基準(2020年版) オールガイド食品成分表2017 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
|
最終更新日 2021/03/26 |
微量ミネラルの多い食品・食べ物一覧
 |
鉄分の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
亜鉛の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
マンガンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ヨウ素の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
セレンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
クロムの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
モリブデンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
コバルトの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
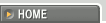
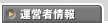
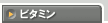
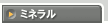
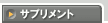
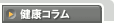



 微量ミネラル
微量ミネラル
