 |

|
|
リン脂質とは、脂質について3

 | 複合脂質とは | ||
前回は脂質の1つ単純脂質について見てきましたが、今回は複合脂質について取り上げることにします。単純脂質の1つ中性脂肪(トリアシルグリセロール)は生体内で最も多く存在する脂質ですが、複合脂質は生体膜を構成する成分として生体膜内に高濃度に存在します。複合脂質にはリン脂質と糖脂質の2種類がありますが、今回はリン脂質についてみていくことにします。
 | リン脂質とは | ||
リン脂質の構造と働き
リン脂質とは脂肪酸とアルコールにリン酸、さらにはその他の物質が化合してできたものです。化合するアルコールの種類によってグリセロールと化合するものをグリセロリン脂質、スフィンゴシンと化合するものをスフィンゴリン脂質と呼びます。リン脂質はワックス状の固体であり、生体膜の二重層を形成したり、脂質の運搬を担います。
■リン脂質の分類
| リン脂質 | グリセロリン脂質 | ホスファチジン酸 | |
| ホスファチジルコリン | |||
| ホスファチジルエタノールアミン | |||
| ホスファチジルセリン | |||
| ホスファチジルイノシトール | |||
| スフィンゴリン脂質 | スフィンゴミエリン | ||
リン脂質と単純脂質の違い
中性脂肪などの単純脂質は脂肪酸と各種アルコールの化合物で、リン脂質は脂肪酸と各種アルコールにさらにリン酸やその他の物質が結合したものをいいます。単純脂質にくわえてさらにその他の物質とも化合するので複合脂質とも言います。
 | リン脂質の生体膜の形成 | ||
リン脂質は水と油をなじませる
リン脂質には水になじむ性質のある親水性の部分と水をはじき油となじむ性質のある疎水性の部分の両方を持ち、これを両親媒性といいます。ドレッシングなどは時間がたつと水と油の層に別れて使うときによく振らないといけませんが、リン脂質が含まれるマヨネーズは常に水と油が層になることなく混合しています。リン脂質には水と油をなじませる働きがあるので、それぞれが分離することなく混ざり合うのです。このような働きを乳化作用といいます。
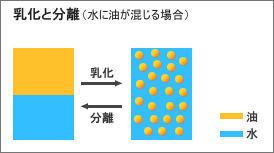
リン脂質は生体膜の二重層を形成
リン脂質はすでに述べた通り親水基(頭部)と疎水基(尾部)があり体液中では頭部が外側を向き尾部が内側をむくと言う形で生体膜の二重層(脂質二重層)を形成しています。これが生体膜の基本構造となります。
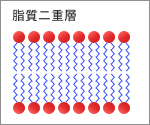
 | リン脂質のミセルや脂質二重層の形成 | ||
ミセルの形成
リン脂質を有機溶媒に溶かし、その少量を水に垂らすと、親水性基(頭部)を水面に接し、疎水性基(尾部)が空気中にさらされる形で横に並んで配置されます。これをかき混ぜると尾部同士を接して頭部が外側に来る形で円状にまとまっていきます。これをミセルといいます。
脂質二重層の形成
水に小さな穴が開いた隔壁を置くと、その隔壁を挟んで隔壁面に疎水性部(尾部)が接し、外側に親水性部(頭部)が来る形で横に並び、脂質二重層という膜を形成します。これが生体膜の基本構造になります。
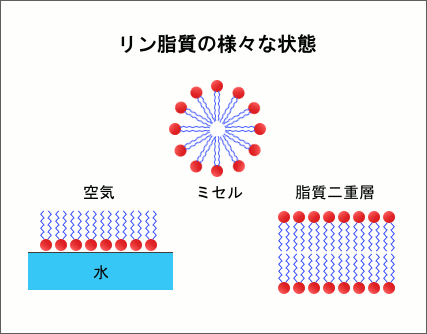
 | ホスファチジルコリン(phosphatidylcholine PC) | ||
ホスファチジルコリンの構造
ホスファチジルコリン(別名レチシン)はグリセロールに飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸がそれぞれ1つ付き、残りの1つの置換基にリン酸が結合したホスファチジン酸がその前駆体であり、リン酸にさらにコリンが結合することでホスファチジルコリンとなります。下の構造式だとホスファチジン酸のR1とR2の部分が飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸で、赤文字であらわした部分がリン酸です。リン酸と結合する物質はコリン以外にも様々でそれぞれで性質が異なります。
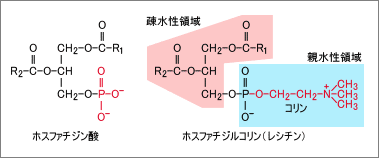
疎水性領域と親水性領域
ホスファチジルコリンに限らずリン脂質はグリセロールや脂肪酸の部分の疎水性領域と、リン酸や水溶性の塩基であるコリンの部分が結合して両親媒性を獲得しています。すなわち水と油をなじませる働きを得ているわけです。水溶性の塩基にはコリンの他エタノールアミンやセリン、イノシトールなどが知られています。ちなみに塩基については塩(えん)って何、酸と塩基の違いについてで詳しく解説しています。
ホスファチジルコリンの働き
レチシンは体内の各組織に広く分布し、リン脂質の中で最も多く存在します。生体内に存在する総リン脂質中の30〜50%はレチシンで、血清中のリン脂質中だと66%はレチシンです。レチシンは肝臓での脂質代謝や脂質の運搬、リン酸基の供給源などの役割を担います。
乳化作用で食品にも使われる
リン脂質のレチシンは卵黄や大豆から抽出される成分として有名で、レチシンは油と水をなじませる乳化作用からチョコレート、マヨネーズ、アイスクリーム、菓子類などの食品加工にも利用されています。また医薬品の界面活性剤としても利用されています。
 | リゾホスファチジルコリン(lysophosphatidylcholine LYSO) | ||
リゾホスファチジルコリンはホスファチジルコリン(レチシン)の脂肪酸が一つ外れたもので、その他の部位はレチシンと同様のリン脂質です。一般にはリゾレチシンと呼ばれます。リゾレチシンには溶血作用や筋肉の収取の阻害作用などが知られています。血清中のリン脂質の9.4%はリゾレチシンです。
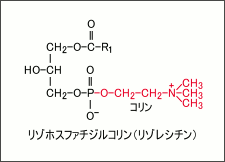
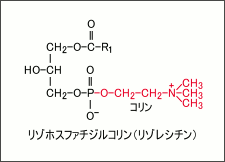
 | ホスファチジルエタノールアミン(phosphatidyleethanolamine PE) | ||
ホスファチジルエタノールアミン(別名ケファリン)はホスファチジン酸のリン酸基にエタノールアミンがエステル結合してできたものです。動物組織中にはホスファチジルコリンについで二番目に多いリン脂質です。主に血小板に存在し血液凝固因子の1つとして働きます。また体内で新しい組織が作られる際の無機リン酸基の供給源としても働きます。
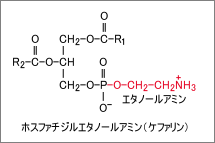
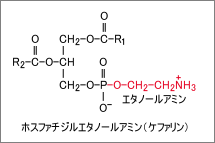
 | ホスファチジルセリン(phosphatidylserine PS) | ||
ホスファチジルセリン(別名セファリン)はホスファチジン酸のリン酸基にアミノ酸のセリンが結合したものです。
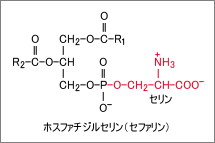
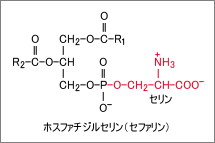
 | ホスファチジルイノシトール(phosphatidylinositol PI) | ||
ホスファチジルイノシトールはホスファチジン酸のリン酸基にミオイノシトールが結合したリン脂質です。ホスファチジルイノシトールにはミオイノシトールに2つのリン酸が付いたホスファチジルイノシトール2リン酸もあり、ホスファチジルイノシトール2リン酸は分解過程でイノシトール3リン酸を生成します。イノシトール3リン酸は細胞間のシグナル伝達における第二メッセンジャーとして働く物質です。
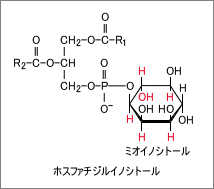
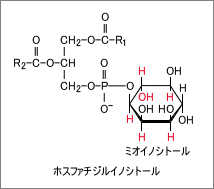
 | スフィンゴミエリン(sphingomelin SPH) | ||
スフィンゴミエリンの構造
アミノアルコールのスフィンゴシンと脂肪酸はアミド結合と呼ばれる方法で結合し、この状態をセラミドといいます。セラミドにさらにリン酸とコリンが結合したものをスフィンゴミエリンと呼びます。
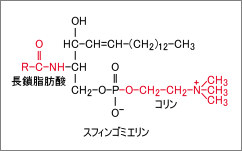
スフィンゴミエリンの働き
スフィンゴミエリンは脳や神経組織に多く含まれ、その名が示すとおり神経線維のミエリン鞘の構成成分でもあります。また細胞内の種々の膜の脂質二重層にも含まれます。また血清中のリン脂質の21%はスフィンゴミエリンです。
|
参考文献
栄養科学シリーズNEXT 生化学 基礎栄養学 栄養・健康化学シリーズ 生化学 わかりやすい生化学 絵とき 生化学入門 有機化学 (わかる化学シリーズ) 栄養学の基本がわかる事典 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
| 最終更新日 2018/01/31 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
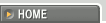
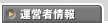
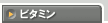
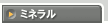
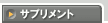
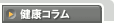



 脂質
脂質
