 |

|
|
免疫について1

 | 免疫とは | ||
|
今回から数回に分けて免疫について見ていくことにします。 免疫とは、外来の病原体や様々な物質(抗原)を、生体内に存在しない異物と判断して、それを排除する機構のことです。 |
 | 免疫の分類 | ||
|
免疫は大きく自然免疫系と獲得免疫系とに分類できます。それぞれの免疫系は互いに相互作用的に機能しています。 ■自然免疫 外部からの病原体に対する最初の障壁。 特異性は低く、広範に病原体に対処する。 感染を繰り返しても、抵抗力に変化はない。 ■獲得免疫 特異性が高い。 一度感染するとその病原体を記憶してそれを排除し、次また感染した場合迅速に対処して抵抗力を高める。 自然免疫系、獲得免疫系は共に、物理的防御因子、液性因子、細胞性因子の3つの要素に分類できます。
|
 | 物理的防御因子 | ||
| 物理的防御因子とは自然免疫系の一種で皮膚や粘膜、繊毛などを指し、外部の病原体に対する最初のバリアーとなります。皮膚は数層の角化細胞からなる頑丈な障壁で、粘膜の上皮も皮膚ほどではありませんが強力なバリアーとなります。 |
 | 自然免疫系の液性因子 | ||
自然免疫系の液性因子は「分泌液中の液性因子」と「血液中の液性因子」の2つに分類されます。分泌液中の液性因子は物理的障壁において、病原体などの感染を防ぎます。
血液中の液性因子は体内に侵入した病原体に作用します。
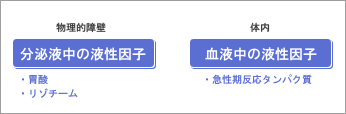
 胃酸 胃酸pH値が1〜2と強酸性の胃酸により、微生物の大部分は死滅します。  リゾチーム リゾチーム唾液や気道の粘膜中に含まれるリゾチームは、ある種の細菌の細胞壁を分解する溶菌酵素の一種です。  急性期反応タンパク質 急性期反応タンパク質感染による炎症性反応に呼応して、血液中に急激に増加する一連のタンパク質群。  CRP(C反応性タンパク質) CRP(C反応性タンパク質)細菌表面を覆い、補体や貪食細胞の作用を助ける。(オプソニン作用)  補体 補体補体とは約20種のタンパク質群からなる複雑な反応系です。それ自体に溶菌作用を持ち、オプソニン作用や貪食細胞の感染部位への集合など様々な機能を持ちます。  インターフェロン インターフェロンウイルスに感染した細胞から分泌され、未感染の細胞の抵抗性を増強する。ナチュラルキラー細胞の活性化作用もある。 |
 | 自然免疫系の細胞性因子 | ||
| 貪食作用などにより、病原体を非特異的(様々な成分を幅広く異物として検出)に排除する。貪食細胞やナチュラルキラー細胞などがある。個々の細胞の詳細については次回の講で述べることにします。 |
 | 細胞性因子とは | ||
| 次に細胞性因子について見て行きます。今回紹介するリンパ球、単球、顆粒球、肥満細胞はみな白血球の一種です。白血球は細胞内に核を持ち、血小板には核がありません。なお文章中にも出てくる抗原や抗体についての詳しい解説は次回取り上げます。 |
 | 免疫担当細胞 | ||
|
免疫担当細胞(白血球)は骨髄に存在する血液性幹細胞に由来します。幹細胞とは指令を受け様々な細胞へと変身、分化する細胞です。血液性幹細胞は骨髄細胞系とリンパ球系の2つの系統に分化します。 ■免疫担当細胞の起源と種類
|
 | リンパ球系細胞 | ||
リンパ球系の細胞にはT細胞とB細胞があります。これ以外にもナチュラルキラー細胞などの第3群に属するリンパ球もあります。T細胞は骨髄で前駆細胞が作られ胸腺で成熟して生成されます。B細胞とナチュラルキラー細胞は骨髄や胎生肝で生成されます。
 T細胞 T細胞T細胞は細胞表面にあるたんぱく質の種類により、ヘルパーT細胞、細胞障害性T細胞、遅延型反応性T細胞とに分類されます。 T細胞表面には抗原に対する受容体(T細胞受容体)があります。この受容体は遊離している抗原を認識することは出来ず、他の細胞の表面に存在する抗原のみ認識する事ができます。この細胞は抗原提示細胞といい、抗原を処理してT細胞の受容体へと伝達する橋渡しの役目を担います。  ヘルパーT細胞 ヘルパーT細胞B細胞や細胞障害性T細胞、NK細胞などの活性化に作用し、免疫反応全体の調整役として働く。 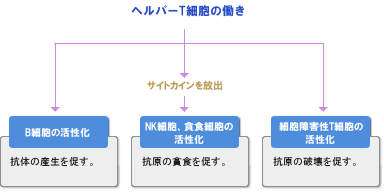
 細胞障害性T細胞 細胞障害性T細胞標的細胞表面上の抗原を認識して、特異的に作用して細胞を破壊する。別称はキラーT細胞。  遅延型反応性T細胞 遅延型反応性T細胞必要以上の抗体の産生を防ぐために、ヘルパーT細胞、B細胞の働きを抑制する。  B細胞 B細胞抗体(免疫グロブリン)を生成します。抗体には分泌されるものと、細胞表面に存在して抗原に対する受容体として機能するものがあります。後者は抗原提示細胞としても機能します。  NK細胞(natural killer cell) NK細胞(natural killer cell)ウイルスは自分自身で増殖できない変わりに、感染した細胞の遺伝子複製機構を利用して自己のコピーを作ります。したがってウイルスが増殖して周囲の細胞に感染する前に、ウイルス感染細胞を破壊する必要があります。 NK細胞はウイルスに感染した細胞表面に存在する特異性のタンパク質を認識して、破壊する働きがあります。NK細胞は細胞障害性T細胞の亜種の1つです。 |
 | 骨髄細胞系細胞 | ||
 単球 単球分化してマクロファージとなる。細菌の貪食作用の他、抗原の一部を細胞表面に提示して、T細胞の抗原受容体へと伝達する抗原提示細胞としても働き、免疫活動の活性化を促す。  顆粒球と肥満細胞 顆粒球と肥満細胞顆粒球には好中球、好酸球、好塩基球があり、白血球全体の60%〜70%を占めます。好中球と好酸球、好塩基球と肥満細胞はそれぞれよく似た働きをします。  好中球 好中球貪食作用。細胞内にある加水分解酵素による細菌の処理。  好酸球 好酸球貪食作用。細胞内にある細胞障害性タンパク質による細菌の処理。  好塩基球、肥満細胞 好塩基球、肥満細胞細菌の処理機能の他、放出されるヒスタミンや神経伝達物質がしばしばアレルギーの原因となります。  血小板 血小板巨核球を由来とし、血液凝固作用のほか、炎症作用にも関与する。 |
|
参考文献
わかりやすい生化学 栄養・健康化学シリーズ 生化学 栄養科学シリーズNEXT 生化学 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
| text by 2005/12/09 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
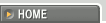
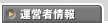
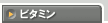
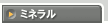
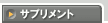
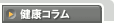


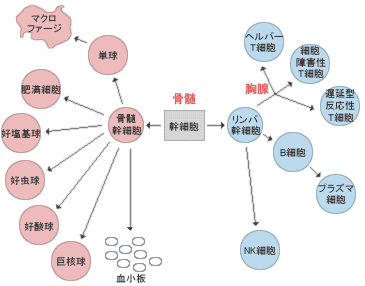

 生化学
生化学
