 |

|
|
疲労とビタミン、エネルギー代謝とビタミン

 | はじめに | ||
| 今回は疲労と栄養分、とりわけビタミンとの関係についてみていきたいと思いますが、まずは、疲労とはどういったものなのか、つぎに疲労と関係の深いエネルギー代謝の仕組みについてみていきます。最後にエネルギー代謝とビタミンとの関係について取り上げます。 |
 | 疲れの原因 | ||
|
疲れというのはいくつかの原因が考えられます。ある病気の症状として出てくる場合を除けば、大きく3つに分類できます。その3つとはエネルギー代謝の乱れ、疲労物質である乳酸の蓄積、ストレスです。
1、エネルギー代謝 エネルギー代謝を行うクエン酸回路が十分に回らなくなると、中間物質であるピルビン酸やアセチルCoAが行き場を失い、たまり始めます。そうするとピルビン酸では無酸素状態での分解(嫌気性分解)がおこり乳酸を生成、アセチルCoAは脂肪合成へと進んでしまいます。 乳酸が溜まってくればそれだけ疲労感も出てくることになります。 2、乳酸の蓄積 激しい運動では酸素を必要とする好気性分解だけではエネルギー生産が間に合わないため、酸素を必要としない嫌気性分解が起こりエネルギーを生産して、その際の最終産物として乳酸が発生します。 乳酸は血液を通って全身を循環し、肝臓でその80%が再度グリコーゲンに合成され、残りの20%が水と二酸化炭素に分解されますが、一部は筋肉に蓄積します。 激しい運動をしたあとやエネルギー代謝が十分に働かないときなどには、多くの乳酸が発生して血液の乳酸濃度も上昇します。そうするとph値が酸性に傾いて、種々の酵素群の働きが鈍り体調を崩して疲れを感じるようになります。また筋肉に蓄積する乳酸の量も増えて筋肉疲労を引き起こします。 疲れを残さないようにするには十分な休養と睡眠、栄養補給が大切です。休養時、睡眠時はエネルギー消費も少なく、必要な酸素量も減るのでその分乳酸の代謝に酸素が当てられ、その量が減少し、疲労回復につながります。またマッサージも効果的です。収縮した筋肉をほぐしてやることで、血液の流れが良くなり、乳酸の排出が進みます。 普段から運動していない人は血管も未発達なため、乳酸などの疲労物質の排出効率も悪く、疲労がたまりやすく、抜けにくい状態にあります。適度な運動を心がけることで、疲労がたまりにくく、抜けやすい体へと体質が改善します。 3、ストレス |
 | エネルギー代謝の仕組み | ||
|
体内に摂取された栄養分は、解糖、クエン酸回路、電子伝達という3つの段階を経て、エネルギーであるATPが作られます。
1、解糖 2、クエン酸回路 クエン酸回路はミトコンドリア内のマトリックスで主に行われます。またクエン酸回路(Tri-Carboxylic Acid)はその頭文字をとってTCAサイクルとも呼ばれます。 3、電子伝達 エネルギーを作り出す代表的な化学反応は、細胞内にあるミトコンドリア内でおこるクエン酸回路です。電子伝達ではクエン酸回路によって作られるエネルギーを利用して、ADP(アデノシン2リン酸)分子1個に、リン酸基1個を結合させてATP(アデノシン3リン酸)を作ります。細胞はこの結合がきれてATPがADPに戻る際に発生するエネルギーを利用します。 電子伝達はミトコンドリアの内膜で行われます。 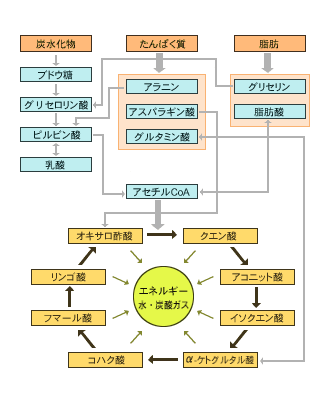
|
 | ATPの生成 | ||
|
高エネルギーリン酸化合物であるATPがどのようにして作られるのかについてもう少し詳しく見て行きます。まず解糖系やTCAサイクル、脂肪酸のβ-酸化の過程で脱水素酵素の働きにより基質から水素が放出されます。基質とは酵素の働きによって化学反応が触媒される物質です。触媒とはそれ自体は変化せず、対象物質の生理反応を促進させる物質です。β-酸化については飽和脂肪酸の酸化で、基質や酵素については酵素について1で詳しく解説しています。 こうして放出された水素はビタミンのナイアシン(NAD:ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド)やビタミンB2(FAD:フラビン・アデニンジ・ヌクレオチド)が受け取り、それぞれNADH、FADH2となって細胞内のミトコンドリア内膜にある電子伝達系に送られ、エネルギー源であるATPが生産されます。 |
 | 電子伝達系の意味 | ||
| クエン酸回路などから放出された水素を受け取るのはNADやFADですが、NADは電子を一つ失ってイオン化してNAD+となっています。NAD+とFADが水素を受け取る物質として機能します。FADはそのまま2つの水素原子を受け取ってFADH2となりますが、NAD+は水素原子は一つだけ受け取り電子は二つ分受け取るので、NADHと遊離した水素イオン(H+)となります。水素イオンはNADHでは一つしか受け取っていませんが二つの電子はどちらも受け取っています。この電子を電子伝達系で受け渡していくことでエネルギー源であるATPが生成されるのでこの系を電子伝達系といいます。 |
 | 電子伝達系の仕組み | ||
電子伝達系ではNADHはNAD+とH+と2つの電子に、FADH2はFADと2H+と2つの電子に転換され、いづれも2つの電子が3つの複合体を経由し、その際ATPが生産されます。複合体は4種類あり、2つはNADHとFADH2で共通していて、残りの2つはそれぞれNADHとFADH2で異なります。複合体の種類は以下の通りです。
NADHは1、3、4の複合体を電子が経由する際ATPが生成され、FADH2は2、3、4の複合体を電子が経由する際ATPが生成されます。電子は最後O2に受け渡されそれが水素イオンと結合して水(H2O)となります。このように電子伝達系では酸素(O)が必要となるため、電子伝達系のことを呼吸鎖ともいいます。 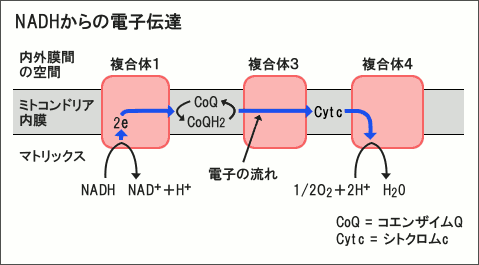 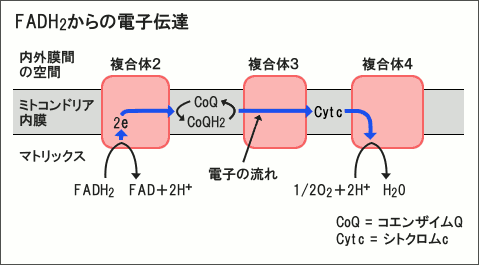
|
 | 電子伝達系でのATPの生産 | ||
|
電子伝達系のあるミトコンドリアは外膜、内膜、マトリックスという層に分かれています。内膜をはさんで外膜・内膜間とマトリックスでは含まれる水素イオン(H+)に濃度差があります。NADHやFADH2発の電子(e+)が電子伝達系の複合体を経由する際、電子からエネルギーが放出され、そのエネルギーを使ってマトリックス側から外膜・内膜間側に水素イオン(H+)が輸送されます。 そうすると外膜・内膜側の水素濃度が高くなるので、外膜・内膜間側から水素がマトリックス側へと流入しようとします。その際にF0・F1ATPシンターゼと呼ばれる複合ユニットからなる通り道を通過しなければなりません。そのユニットを水素イオンが通過するとユニット内で変化が生じ、まずはF0部が変化し、続いてF1部が変化して、ADPとリン酸からATPを生成します。このような仕組みでNADHやFADH2発の電子が複合体を経由する際にATPが生成されるのです。 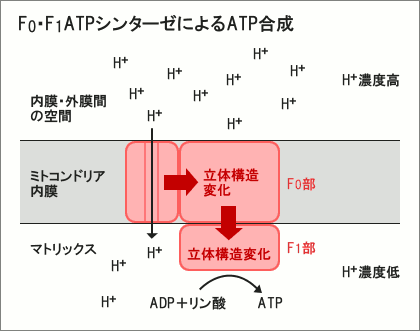 ちなみにFADH2で経由する複合体で2の複合体を経由する際に電子から発せられるエネルギーの量は水素を輸送するために十分なエネルギー量ではないので、ここではATPの生産は行われません。このためATPの合成量もNADH1分子で3ATPなのに対し、FADH2では2ATPとなります。 |
 | 電子伝達系以外でのATPの生産 | ||
| 電子伝達系でのATP生産以外にもグルコースからピルビン酸までの代謝過程でも二か所でATPが生成され、クエン酸回路のα-ケトグルタル酸からコハク酸の代謝過程でもATPが生成されます。 |
 | ビタミンとエネルギー代謝 | ||
|
ビタミンはエネルギー代謝が円滑に行われるためになくてはならない栄養素です。エネルギー代謝に必要なビタミンはビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ニコチン酸(ナイアシン)、ビタミンB6、ビタミンB12、パントテン酸)で、役割はそれぞれに異なりますがどれがかけても十分なエネルギー代謝を行うことはできません。エネルギー代謝がうまく働かなければ疲労感も増してきます。それだけビタミンの役割というのは重要なのです。それでは各ビタミンの働きについてみていきます。
ビタミンB1 ● α-ケトグルタル酸 → コハク酸 ビタミンB2 ● たんぱく質の代謝物質アラニンのピルビル酸への代謝に必要。 ● ピルビン酸 → アセチルCoA ● たんぱく質の代謝物質グルタミン酸からα-ケトグルタル酸への代謝に必要。 ● 解糖系、クエン酸回路、β-酸化で発生した水素を受け取り電子伝達系まで進む ビタミンB6 ● たんぱく質の代謝物質グルタミン酸からα-ケトグルタル酸への代謝に必要。 ビタミンB12 ● コハク酸 → フマール酸 ● リンゴ酸 → オキサロ酢酸 ニコチン酸(ナイアシン) ● たんぱく質の代謝物質アラニンのピルビル酸への代謝に必要。 ● ピルビン酸 → アセチルCoA ● 脂肪酸 → アセチルCoA ● コハク酸 → フマール酸 ● リンゴ酸 → オキサロ酢酸 ● グルタミン酸 → α-ケトグルタル酸 ● 解糖系、クエン酸回路、β-酸化で発生した水素を受け取り電子伝達系まで進む パントテン酸 ● 脂肪酸 → アセチルCoA ● α-ケトグルタル酸 → コハク酸 |
|
参考文献
医療従事者のための機能性食品 「ビタミン伝説」の真実 基礎栄養学 健康・栄養科学シリーズ 基礎栄養学 スタンダード栄養・食物シリーズ 基礎栄養学第3版 スタンダード栄養・食物シリーズ 基礎栄養学 サプリメントデータブック よくわかる栄養学の基本としくみ 身体に必要なミネラルの基礎知識 栄養・健康科学シリーズ生化学 よくわかる生理学の基本としくみ わかりやすい生化学 栄養科学シリーズNEXT生化学 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
| 最終更新日 2016/09/21 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
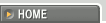
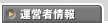
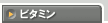
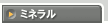
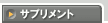
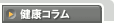



 健康コラム
健康コラム
