 |

|
|
葉酸の多い食品・食べ物と含有量一覧

 | 葉酸を多く含む食品 | ||
葉酸は野菜や肉類全般に多く含まれます。これらは量も取りやすいので葉酸を摂取しやすい食品群だといえます。海藻は食事としてとれる量は少量ですが、含有量自体が非常に多いのでこちらも葉酸を摂取しやすい食品です。
他にもドリアンやアボガドといった果物やひよこまめ、生うに、ひまわりの種、小麦胚芽、玉露(抽出液)などにも葉酸は多く含まれます。特に玉露は飲み物なので手軽に葉酸を摂取することができおすすめです。
今回はまずは葉酸の働きや1日の摂取の推奨量を見ていき、各食品群ごとに葉酸が多く含まれる食品を解説します。さらに葉酸を摂取するうえでのポイントや、葉酸不足に注意したいケースなどについても取り上げます。
他にもドリアンやアボガドといった果物やひよこまめ、生うに、ひまわりの種、小麦胚芽、玉露(抽出液)などにも葉酸は多く含まれます。特に玉露は飲み物なので手軽に葉酸を摂取することができおすすめです。
今回はまずは葉酸の働きや1日の摂取の推奨量を見ていき、各食品群ごとに葉酸が多く含まれる食品を解説します。さらに葉酸を摂取するうえでのポイントや、葉酸不足に注意したいケースなどについても取り上げます。
 | 葉酸の主な働き | ||
葉酸には次のような働きがあります。
核酸には遺伝情報を格納し、遺伝情報をもとに様々なたんぱく質を合成する働きがあり、生命を維持していく上で欠かせないものです。葉酸はこの核酸の合成にかかわります。
葉酸はアミノ酸の一種であるホモシステインをメチオニンへと変換するのに働きます。ホモシステインの血中濃度が高まると動脈硬化や狭心症、心筋梗塞のリスクが高まることが知られています。葉酸は血中のホモシステイン濃度を低下させる働きがあるのでこれら疾患の予防にも効果を発揮します。
ビタミンB6やビタミンB12もホモシステイン濃度を低下させる働きがあるのでこれらビタミンも一緒に取るとより効果的です。
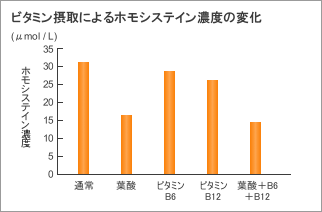
葉酸は核酸の合成に関与しますが、葉酸が欠乏して核酸の合成が滞ると赤血球の合成にも影響が出て、赤血球の分裂が十分に進まないまま異常に成熟してしまう巨赤芽球性貧血を発症してしまいます。
赤血球の数自体は減少しサイズの大きな赤血球ばかり作られてしまうので酸素運搬能力が低下して貧血症状を引き起こします。巨赤芽球性貧血の予防のためにも葉酸をしっかりと摂取することが大切です。
核酸は細胞の分裂、増殖、成熟には欠かせないものです。細胞分裂が活発な成長期の子供や胎児を抱える妊婦には特に必要となる栄養素です。このため日本食事摂取基準でも妊婦には通常の成人女性の倍の量を摂取することを推奨しています。
妊娠初期に見られる胎児の神経管閉鎖障害の発症に葉酸の摂取が効果的であるというデータが欧米を中心に多数報告されていて、妊娠前からサプリメントなどで葉酸を摂取することが推奨されています。
粘膜も細胞分裂が盛んな部位で葉酸も多く存在しています。葉酸が不足すると消化管内の粘膜にも影響が出て、下痢や食欲不振から始まり、口内炎や舌炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などを発症します。
核酸の合成に働く
核酸には遺伝情報を格納し、遺伝情報をもとに様々なたんぱく質を合成する働きがあり、生命を維持していく上で欠かせないものです。葉酸はこの核酸の合成にかかわります。
動脈硬化の予防
葉酸はアミノ酸の一種であるホモシステインをメチオニンへと変換するのに働きます。ホモシステインの血中濃度が高まると動脈硬化や狭心症、心筋梗塞のリスクが高まることが知られています。葉酸は血中のホモシステイン濃度を低下させる働きがあるのでこれら疾患の予防にも効果を発揮します。
ビタミンB6やビタミンB12もホモシステイン濃度を低下させる働きがあるのでこれらビタミンも一緒に取るとより効果的です。
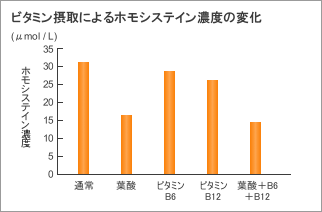
巨赤芽球性貧血の予防
葉酸は核酸の合成に関与しますが、葉酸が欠乏して核酸の合成が滞ると赤血球の合成にも影響が出て、赤血球の分裂が十分に進まないまま異常に成熟してしまう巨赤芽球性貧血を発症してしまいます。
赤血球の数自体は減少しサイズの大きな赤血球ばかり作られてしまうので酸素運搬能力が低下して貧血症状を引き起こします。巨赤芽球性貧血の予防のためにも葉酸をしっかりと摂取することが大切です。
成長や妊娠の維持
核酸は細胞の分裂、増殖、成熟には欠かせないものです。細胞分裂が活発な成長期の子供や胎児を抱える妊婦には特に必要となる栄養素です。このため日本食事摂取基準でも妊婦には通常の成人女性の倍の量を摂取することを推奨しています。
妊娠初期に見られる胎児の神経管閉鎖障害の発症に葉酸の摂取が効果的であるというデータが欧米を中心に多数報告されていて、妊娠前からサプリメントなどで葉酸を摂取することが推奨されています。
粘膜の健康を保つ
粘膜も細胞分裂が盛んな部位で葉酸も多く存在しています。葉酸が不足すると消化管内の粘膜にも影響が出て、下痢や食欲不振から始まり、口内炎や舌炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などを発症します。
 | 葉酸摂取の推奨量 | ||
妊婦は葉酸の多めな摂取を
葉酸の成人男女の推奨量は240μgに設定されています。葉酸は細胞分裂に欠かせない核酸の合成に関わるので、細胞分裂が盛んな胎児を抱える妊婦は特に多くの葉酸の摂取が必要になります。このため妊娠中は付加量としてプラス240μg、授乳中は付加量としてプラス100μg摂取することが求められます。
サプリメントでの葉酸摂取には上限量有り
葉酸は通常の食生活であれば過剰症の心配はありませんが、サプリメントなどで大量に摂取した場合には過剰症状の報告が複数なされています。このため日本食事摂取基準では食品などに含まれるプテロイルポリグルタミン酸ではなく、サプリメントなどに含まれるプテロイルモノグルタミン酸を大量に摂取した場合の上限量を定めています。上限量は成人男女で900μgとなっています。
|
葉酸成人男子推奨量:240μg 葉酸成人男子上限量:900μg 葉酸成人女子推奨量:240μg 葉酸成人女子上限量:900μg |
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。
 | 野菜類で葉酸の多い食品 | ||
野菜類で葉酸の摂りやすい食品
野菜は全般に葉酸が多く含まれる食品群です。なかでも100gあたりの葉酸の含有量も多く食品として量もとりやすいのはえだまめ、アスパラガス、なばな、めキャベツ、ケール、ブロッコリー、茎にんにく、そら豆、ほうれん草、春菊、とうもろこしなどです。
えだまめ

枝豆も最近ではコンビニなどでも販売されていて手軽に購入することが出来ます。100gほどのサイズで1人前で売られているようで、100gだと中身の豆の重さは52gほどで葉酸の含有量は135μgになります。おつまみ感覚で手軽に食べれるので葉酸摂取にはおすすめの食品の一つです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| えだまめ(ゆで) | 260μg |
10さや25g(13g) 1パック100g(52g) |
31μg 135μg |
アスパラガス

アスパラガスはゆでたものを3本、4本と食べるのも普通でしょう。アスパラガス3本なら葉酸の量は102μgになります。調理はゆでるよりも油でいためた方がより葉酸を多く摂取できます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| アスパラガス(ゆで) | 180μg |
1本20g(20g) 3本60g(60g) |
34μg 102μg |
| アスパラガス(油いため) | 220μg |
1本20g(20g) 3本60g(60g) |
44μg 132μg |
なばな
なばなは菜の花、かぶれなとも言います。和種と洋種があり和種は葉と茎と花を、洋種は茎と葉を利用します。料理では炒め物や和え物、お浸しなどに利用します。料理にもよりますが一人前でだいたい50gほど利用します。100g当たりの含有量も多く、食事として量も取りやすいのでこちらも葉酸を摂取しやすい食品の一つです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 和種なばな(ゆで) | 190μg | 1/4わ49g | 93.1μg |
| 洋種なばな(ゆで) | 240μg | 1/4わ50g | 120μg |
めきゃべつ

めキャベツの炒め物なら1人前で5〜6個は使います。めキャベツが5個なら葉酸の量は110μgになります。ちなみに通常のキャベツの場合は、葉1枚で葉酸は39μgほどになります。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| めキャベツ(ゆで) | 220μg |
1個10g(10g) 5個50g(50g) |
22μg 110μg |
| キャベツ | 78μg |
1玉1000g(850g) 1枚50g |
663μg 39μg |
ケール
ケールは青汁の材料としても有名ですが、欧米ではロールキャベツや炒め物、煮物などにもつかわれる食品です。1人前で1/2枚使ったとして取れる葉酸の量は116μgです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ケール | 120μg |
1枚200g(194g) 1/2枚100g(97g) |
233μg 116μg |
春菊

春菊はごま和えや鍋の具材としてもよく利用される食材です。1人前での使用量はだいたい100gほどで、その場合葉酸を100μg摂取することが出来ます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 春菊(ゆで) | 100μg |
1株24g(24g) 4株96g(96g) |
24μg 96μg |
そらまめ

そらまめは塩茹でにしたものを1カップ100g食べるとして90μgの葉酸を摂取できます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| そらまめ(ゆで) | 120μg | カップ1杯100g(75g) | 90μg |
ブロッコリー
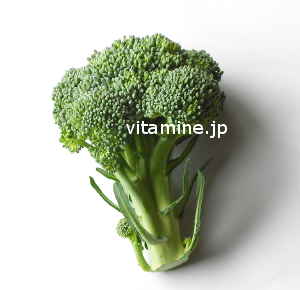
ブロッコリーは塩ゆでしたものにドレッシングをかけてシンプルにいただくことも多い食材で、1人前だと1/2個ほど使用します。その場合葉酸は99μg摂取できます。上の画像のブロッコリーでだいたい160gほどです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ブロッコリー(ゆで) | 120μg |
1個165g(165g) 1/2個83g(83g) |
198μg 99μg |
茎にんにく

茎にんにくはにんにくの芽とも呼ばれ野菜炒めの具材としてもよく使われます。1人前で10本ほど利用するとして葉酸は120μg摂取できます。ちなみに通常のにんにくの場合は葉酸の量は茎にんにくよりも若干少ないです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 茎にんにく(ゆで) | 120μg |
1本10g(10g) 10本100g(100g) |
12μg 120μg |
| にんにく | 93μg | 1かけ10g | 9.3μg |
ほうれんそう

ほうれん草はおひたしや炒め物などの料理によく使います。1人分の使用量は1/2わ程度で、その場合だと葉酸は110μg摂取できます。ほうれん草はゆでた場合よりも油でいためた場合の方が100gあたりで摂れる葉酸の量は多くなります。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ほうれん草(ゆで) | 110μg |
1わ210g(200g) 1/2わ105g(100g) |
220μg 110μg |
| ほうれん草(油いため) | 140μg |
1わ210g(200g) 1/2わ105g(100g) |
280μg 140μg |
とうもろこし

とうもろこしも1本丸ごとたべれば132μgの葉酸をとることが出来ます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| とうもろこし(ゆで) | 86μg | 1本220g(154g) | 132μg |
葉酸は多いが量を摂りにくい野菜
100gあたりでの食品中の葉酸の量は多いものの、そんなに一度にたくさんの量を食べるものでもないため、摂れる葉酸の量が限られる野菜も少なくありません。例えばパセリやネギ、しその葉などです。中には調理法の工夫により量をとれる野菜もありますが、基本は少量での利用が多い野菜をこちらで紹介します。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| パセリ | 220μg | 1本5g(5g) | 11μg |
| クレソン | 150μg | 1わ40g(34g) | 51μg |
| らっかせい(ゆで) | 150μg | 10粒8g(8g) | 12μg |
| サニーレタス | 120μg | 1枚20g(20g) | 24μg |
| おくら(ゆで) | 110μg | 1本10g(9g) | 10μg |
| ヤングコーン | 110μg | 1本10g(10g) | 11μg |
| のびる | 110μg | 10本35g(28g) | 31μg |
| しその葉 | 110μg | 10枚10g(10g) | 11μg |
| 葉ねぎ | 100μg | 1本20g(19g) | 19μg |
 | 果実類で葉酸の多い食品 | ||
果実類で葉酸の摂りやすい食品
ドリアンやアボガド、マンゴーは100gあたりの含有量だけでなく、食事で一度に取れる量も多いので葉酸の摂取先としては非常に優れているといえます。
ドリアン
ドリアンはマレーシア原産の果物で国内ではとげとげの果皮を除いた輸入冷凍物が流通しています。ドリアンの実は5つの房に分かれていて1房がだいたい1人分です。1房で102μgの葉酸を摂取できます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ドリアン | 150μg |
1袋260g(221g) 1房105g(68g) |
332μg 102μg |
アボカド

アボガドは中央アメリカが原産で味はマグロにもにていて、「森のバター」とも評されます。最近では国内での流通量も増え、入手しやすい果物となっています。葉酸は1個分で135μgの葉酸を摂取できます。ちなみに上の画像はアボカドです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| アボガド | 84μg | 1個230g(161g) | 135μg |
ライチー
ライチーは中国やベトナム原産のトロピカルフルーツです。中国の楊貴妃が好んで食べたことも有名です。こちらも葉酸の含有量も多く、量も取りやすい食品です。ライチー5個なら摂れる量はこちらも70μgになります。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ライチー | 100μg |
1個20g(14g) 5個100g(70g) |
14μg 70μg |
イチゴ

いちごも葉酸を摂取しやすい食品です。例えばいちごを5個食べれば摂れる葉酸の量は70μgで、
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| いちご | 90μg |
1個15g(15g) 5個75g(75g) |
14μg 70μg |
マンゴー
マンゴーも葉酸と摂取しやすい食品の一つです。マンゴー1個分で164μgの葉酸を摂取できます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| マンゴー | 84μg | 1個300g(195g) | 164μg |
 | 肉類で葉酸の多い食品 | ||
肝臓やその加工食品は葉酸が非常に豊富

牛、豚、鶏ともにレバーはどれも非常に多くの葉酸が含まれます。鶏肝臓1個40gでも520μgもの量の葉酸を一度に摂取することが出来ます。肝臓(レバー)は甘辛煮や野菜と一緒にいためて食べられることが多いです。1人前だと50g〜100gほど利用します。
スモークレバーは主に豚の肝臓を使った燻製品でお酒のおつまみなどにも利用されます。カットしたものを3枚食べればとれる葉酸の量は141μgになります。
鶏と豚の肝臓はビタミンA過剰症に注意
ただしレバーの中でも鶏肝臓と豚肝臓、豚の肝臓の加工品であるスモークレバーはとりすぎには注意が必要です。ビタミンAの多い食品・食べ物と含有量一覧を見てもらえばわかりますが、この3つの食品には非常に多くのビタミンAが含まれます。
妊婦がビタミンAを過剰に摂取すると奇形発生のリスクが高くなることが報告されています。このため妊婦のビタミンAの耐用上限量は3000μgREに設定されているのですが、鶏肝臓と豚肝臓は1切れで、スモークレバーも2枚分でこの上限量を超えてしまうのです。
葉酸が摂りやすい反面、ビタミンAを摂りすぎてしまうので、妊婦は特に鶏肝臓と豚肝臓、スモークレバーの摂取は控えるか、とっても少量に抑えることが大事です。ただし牛肝臓であれば豚や鳥ほどビタミンAは多くはないので、葉酸を摂取するなら豚や鳥ではなく牛肝臓で摂取するといいでしょう。ちなみに上の画像は牛の肝臓です。
肉類で葉酸の含有量が高く、一度の食事でとれる量も多い食品は以下の通りです。
| 鶏肝臓、牛肝臓、豚肝臓、スモークレバー、フォアグラ |
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 鶏肝臓 | 1300μg | 1個40g | 520μg |
| 牛肝臓 | 1000μg | 1切れ40g | 400μg |
| 豚肝臓 | 810μg | 1切れ30g | 243μg |
| スモークレバー | 310μg | 厚5cm長さ10cm15g | 47μg |
| フォアグラ | 220μg | 厚1cm角6cm45g | 99μg |
| 食品名 | 食品目安量(可食部) | 葉酸含有量 | レチノール含有量 |
| 鶏肝臓 | 1個40g | 520μg | 3900μg |
| 牛肝臓 | 1切れ40g | 400μg | 440μg |
| 豚肝臓 | 1切れ30g | 243μg | 5600μg |
| スモークレバー | 厚5cm長さ10cm15g | 47μg | 2550μg |
| フォアグラ | 厚1cm角6cm45g | 99μg | 450μg |
 | 豆類で葉酸の多い食品 | ||

納豆、ひよこ豆は量も摂れて葉酸を摂取しやすい
きな粉やいかり豆は100gあたりの含有量は多いのですが、一度の食事で取る量が限られているのでそれほど多くの葉酸を一度に摂取できるものでも有りません。納豆やひよこまめは一度の食事で量も取れ、その分葉酸も多く摂取できます。ひよこまめは南欧やインド、中東などの料理でよく使われ、サラダやシチュー、スープ料理などに使われます。日本でも最近では目にする機会も増えてきているようです。
豆類で葉酸の含有量が高く、一度の食事でとれる量も多い食品は以下の通りです。
| ひよこまめ(ゆで) |
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| きな粉 | 250μg | 大さじ1杯7g | 18μg |
| 糸引き納豆 | 120μg | 1パック50g | 60μg |
| いかり豆 | 120μg | 10粒20g | 24μg |
| ひよこまめ(ゆで) | 110μg | カップ1杯130g | 143μg |
 | 藻類で葉酸の多い食品 | ||

海苔は少量でも葉酸がたくさん摂れる
やきのりや味付けのり、いわのりやほしのりなどは一度に使う量は少量ですが、それでも100gあたりの含有量が非常に多いのでたくさんの葉酸を摂取することが出来ます。いわのりには岩場に繁殖する自生のものを板海苔に仕上げたもののほか、そのまま乾燥させたもの(素干し海苔)もあります。素干し海苔は吸い物やみそ汁、ラーメンの具などによく利用されます。ちなみに上の画像は焼きのりです。
昆布やあおさは少量だととれる葉酸の量も少ない
まこんぶやあおのりは葉酸の量は100gで見ると多いのですが、一度の食事で使う量で見ると少量になってしまいます。あおさは酢の物や汁物で使いますが、酢の物1人分だと使う量は5gほどです。こちらも使用量で見ると葉酸の量は少なくなります。
藻類で葉酸の含有量が高く、一度の食事でとれる量も多い食品は以下の通りです。
| いわのり(素干し) |
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| やきのり | 1900μg | 2枚3g(3g) | 57μg |
| 味付けのり | 1600μg | 小10枚3g(3g) | 48μg |
| いわのり(素干し) | 1500μg | 1枚10g(10g) | 150μg |
| ほしのり | 1200μg | 1枚3g(3g) | 36μg |
| あおのり(素干し) | 270μg | 大さじ1杯2g | 5μg |
| まこんぶ(素干し) | 260μg | 角5cm1枚1.5g | 4μg |
| あおさ(素干し) | 180μg | 1袋35g(35g) | 63μg |
 | 魚介類で葉酸の多い食品 | ||
生うには特に葉酸が豊富
魚介類の中でも生うには特に葉酸の多い食品です。うにの軍艦巻き1貫で8gほどのうにを使用するので、2貫、3貫食べるだけでもとれる葉酸の量は58μg、87μgと結構な量になります。加工食品である粒うにや練りうには含まれる葉酸の量は100gあたりそれぞれ98μg、87μgと生うにの3分の1以下に落ちます。
また塩分が非常に多いので摂り過ぎには注意が必要です。粒ウニは大さじ1杯15gで食塩が1.2g、練りウニは大さじ1杯15gで食塩が1.1g含まれます。ちなみに生うにだと1貫分(8g)でも0.05gの塩分量なので生うにの場合は塩分を気にする必要はないでしょう。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 生うに | 360μg |
1貫分8g 3貫分24g |
29μg 87μg |
| 粒うに | 98μg | 大さじ1杯15g | 14μg |
| 練りうに | 87μg | 大さじ1杯15g | 13μg |
ほたてがいも葉酸を摂取しやすい
ほたてがいは量を摂取しやすいので、その分葉酸を取りやすい食品だといえます。ほたてがい1個で87μgの葉酸を摂取できます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ほたてがい | 87μg | 1個200g(100g) | 87μg |
その他葉酸の多い魚介類
イクラは1貫で大さじ1杯ほどつかいます。寿司1貫分だと葉酸の量もたいしたことは有りませんが、何貫も食べれば結構な量になります。例えばいくらの軍艦巻きを3貫食べたとしたら取れる葉酸の量は51μgになります。かずのこも3本食べれば72μgになります。干しあわびは食品一単位辺りの重量がおおいので、その分葉酸もたくさん取れます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| かずのこ | 120μg | 1本20g(20g) | 24μg |
| イクラ | 100μg | 大さじ1杯17g | 17μg |
| ほしあわび | 87μg | 1個70g(70g) | 61μg |
 | 茶類で葉酸の多い食品 | ||
濃いお茶の玉露は抽出液でも葉酸が多い

お茶は粉末状だと葉酸の含有量が非常に高くなりますが、抽出液での計測値ではがくんと下がります。そんな中玉露は抽出液の状態でもかなりの量の葉酸を摂取することが出来ます。
玉露は茶葉の状態では100gあたり1000μg、せん茶は100gあたりで1300μg、紅茶では100gあたりで210μgの葉酸が含まれます。お茶はお湯を入れて抽出液として利用するもので、抽出液となると葉酸の含有量はがくんと落ちます。その量はせん茶は抽出液では100g辺り16μgに、紅茶は100gあたり3μgにまで減少します。
茶葉あたりのお湯の量が玉露は茶葉10gで60ml、せん茶は10gあたり430ml、紅茶は5gあたり360mlと使用するお湯の量が玉露はかなり少ないというのも影響しています。ようは玉露はかなり濃いお茶なので抽出液でも葉酸の量が多いわけです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 玉露 | 1000μg | 10g | 100μg |
| 玉露(抽出液) | 150μg | カップ1杯200g | 300μg |
| せん茶 | 1300μg | 10g | 130μg |
| せん茶(抽出液) | 16μg | カップ1杯200g | 32μg |
| 紅茶 | 210μg | 10g | 21μg |
| 紅茶(抽出液) | 3μg | カップ1杯200g | 6μg |
抹茶は粉末でも葉酸が多い

抹茶は粉末状でも100gあたりの含有量が非常に多いので、一度に使う量が少量でも比較的多くの葉酸を摂取できます。抹茶は飲料以外に和菓子などでもよく使われ大さじ1杯6gでも葉酸を72μg摂取することが出来ます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 抹茶(粉末) | 1200μg | 大さじ1杯6g | 72μg |
緑茶はタンニンが豊富
緑茶類にはタンニンも多く含まれていて、タンニンは鉄と結びついて吸収率を低下させることも知られています。このため貧血気味の方は緑茶を摂りすぎるとかえって症状が悪化してしまう可能性があります。また妊婦は胎児の成長のために鉄分も多く必要なので、葉酸のために緑茶をたくさん摂取したとしても鉄の吸収率が落ちてしまっては元も子もありません。こうした方は緑茶での葉酸の摂取は控えめにした方がいいでしょう。
 | その他食品で葉酸の多い食品 | ||
卵類で葉酸の多い食品

卵では卵黄の部分に葉酸が多く含まれ、卵白の部分にはまったく含まれていません。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 卵黄 | 140μg | 1個分18g | 25μg |
| うずら卵 | 91μg | 1個10g(9g) | 8μg |
種実類で葉酸の多い食品

ひまわりの種やごま、バターピーナッツは100gあたりの含有量自体は多いのですが、一度の食事で取れる量が少ないので、その分葉酸の摂取量も少なくなります。ちなみに上の画像はヒマワリの種です。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ひまわりの種 | 280μg | 大さじ1杯9g | 25μg |
| ごま(いり) | 150μg | 大さじ1杯6g | 9μg |
| バターピーナッツ | 98μg | 10粒8g | 8μg |
穀類で葉酸の多い食品

穀類では小麦胚芽に葉酸が多く含まれます。小麦胚芽はごはんにかけたり、クッキーの材料に混ぜて使いますが、一度に使う量がそれほど多くはないので取れる量も限られてきます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 小麦胚芽 | 390μg | 大さじ1杯8g | 31μg |
 | 葉酸を摂取する上でのポイント | ||
ビタミンB12もしっかりととる
葉酸は体内での代謝過程でメチオニン合成酵素によりメチルテトラヒドロ葉酸からテトラヒドロ葉酸へと変換される場面があります。メチオニン合成酵素はビタミンB12が必要となる酵素です。ビタミンB12が不足するとメチオニン合成酵素がしっかりと働けなくなり、その結果テトラヒドロ葉酸の合成も滞ってしまいます。
テトラヒドロ葉酸はその後DNAの合成に働くため、これが影響を受けると巨大な赤血球が作られ、貧血症状を引き起こす巨赤芽球性貧血を発症します。巨赤芽球性貧血は葉酸の欠乏だけでなく、ビタミンB12の欠乏でも発症するわけです。
葉酸は植物性食品に、ビタミンB12は動物性食品に多く含まれるので、バランスのいい食生活が重要となります。ビタミンB12の多い食品についてはビタミンB12の多い食品・食べ物と含有量一覧で解説しています。
食品中の葉酸は熱や光に弱い
食品に含まれる葉酸は熱や光に弱いので、保存や調理で損失しやすい栄養素です。買ってきた食品は長く置いておかずなるべくなら早めに食べるようにしましょう。保存する際も光の当たる場所ではなく、冷蔵庫や冷暗所で保存しましょう。
 | 葉酸不足に注意が必要な人 | ||
妊婦や授乳婦は欠乏に注意
葉酸は細胞分裂や新陳代謝には欠かせない栄養素なので、成長期の子供や妊婦などに特に必要となります。特に妊婦は活発な細胞分裂を重ねて成長していく胎児を抱えているので葉酸の消費量も多く、欠乏症により貧血などを起こしやすいので注意が必要です。
もともと葉酸はインドのボンベイ地方で妊婦に歩行困難などの貧血症状が多くみられた際に、その原因を特定した結果、発見されたものです。日本の食事摂取基準でもその推奨量は成人女性で240μgですが、妊婦だとさらに240μg追加され480μg摂取するよう推奨されています。授乳婦になると付加値は100μgまで落とされます。妊婦は通常よりもたくさん葉酸を摂取することが求められるわけです。
葉酸の欠乏症である巨赤芽球性貧血ですが、これは赤血球がうまく作られずに通常よりも大きな赤血球が作られることで起こる症状で、酸素運搬能力が低下することにより貧血症状を引き起こします。他にも口内炎や肌荒れといった症状も現れます。
妊娠前後は特に摂取しておきたい
妊婦は妊娠中だけでなく妊娠前後にも特に葉酸の摂取が推奨されます。妊娠初期で受胎後およそ28日で脳や脊髄などに発展する神経管と呼ばれる部分が閉鎖しますが、この過程で異常が起こると神経管閉鎖障害を発症します。この発症に葉酸の欠乏が関係していることが各種の研究報告で明らかにされています。
このため妊娠前1ヶ月から妊娠後3ヶ月までの間はプテロイルモノグルタミン酸が取れるサプリメントなどで葉酸を通常の推奨量に付加して400μg摂取することが推奨されています。
アルコールの取り過ぎにも注意
葉酸欠乏症はアルコール常用者に多く見られ、これらは小腸での葉酸の吸収をアルコールが抑制し、腎臓での再吸収も抑制することが大きな要因だと考えられています。アルコールを大量摂取する場合も葉酸の欠乏には注意が必要です。
 | まとめ | ||
葉酸は野菜全般に多い
葉酸は葉という名前がついている通り、芽キャベツやアスパラガス、パセリをはじめとして野菜全般に多く含まれています。毎日の食事にバランスよく野菜を取り入れることでしっかりと葉酸を摂取することが出来ます。ただし葉酸が多く含まれているのは野菜類だけではありません。
レバーは優れた葉酸の補給源
上でも見てきたとおり100gあたりの含有量が非常に多いのは牛、豚、鶏などのレバー(肝臓)や焼きのり、味付け海苔、岩のりなどの藻類、あとは粉末状の茶葉などです。中でもレバーは量もとりやすいので一度にたくさんの葉酸を摂取することが出来ます。葉酸を多く摂ることが推奨される妊婦においては、レバーは手軽にたくさんの葉酸を摂取できるので、非常に優れた食品であるといえるでしょう。
ただし豚や鶏のレバーはビタミンAの含有量が非常に高く、妊婦では特に奇形発生のリスクが高くなるので摂るのは控えるか少量の摂取に抑えたほうがいいでしょう。牛肝臓であれば豚や鶏ほどビタミンAの含有量は高くないので、摂るなら牛肝臓がおすすめです。
海草もプラスで葉酸摂取量アップ
では海草や茶類ではどうでしょうか。こちらも100gあたりの含有量は多いのですが、一度にとれる量は少量になります。ただし含有量自体が非常におおいので少量でもたくさんの葉酸を摂取することが出来ます。毎日レバーを食べるわけにもいきませんし、普段の献立に海藻類も積極的に取り入れていくことで、妊婦の方でも葉酸をしっかり摂取することが出来るでしょう。
デザートで葉酸摂取
果物の中にも葉酸の多い食品はたくさんあります。3度の食事以外にもデザートとしてマンゴーやドリアン、アボガド、いちご、ライチーなどの果物を摂ることで、さらに葉酸を摂取することが出来ます。
葉酸を特にとりやすい食品
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 鶏肝臓 | 1300μg | 1個40g | 520μg |
| 牛肝臓 | 1000μg | 1切れ40g | 400μg |
| 豚肝臓 | 800μg | 1切れ30g | 243μg |
| スモークレバー | 310μg | 厚5cm長さ10cm3枚45g | 141μg |
| フォアグラ | 220μg | 厚1cm角6cm45g | 99μg |
| いわのり(素干し) | 1500μg | 1枚10g(10g) | 150μg |
| えだまめ(ゆで) | 260μg | 30さや75g(39g) | 93μg |
| めキャベツ(ゆで) | 220μg | 5個50g(50g) | 110μg |
| アスパラガス(油いため) | 220μg |
1本20g(20g) 3本60g(60g) |
44μg 132μg |
| 洋種なばな(ゆで) | 240μg | 1/4わ50g | 120μg |
| ケール | 120μg | 1枚200g(194g) | 233μg |
| そらまめ(ゆで) | 120μg | カップ1杯100g(75g) | 90μg |
| ブロッコリー(ゆで) | 120μg | 1個165g(165g) | 198μg |
| 茎にんにく(ゆで) | 120μg | 10本100g(100g) | 120μg |
| ほうれん草(油いため) | 140μg |
1わ210g(200g) 1/2わ105g(100g) |
280μg 140μg |
| とうもろこし(ゆで) | 86μg | 1本220g(154g) | 132μg |
| ドリアン | 150μg | 1袋260g(221g) | 332μg |
| アボガド | 84μg | 1個230g(161g) | 135μg |
| マンゴー | 84μg | 1個300g(195g) | 164μg |
| ひよこまめ(ゆで) | 110μg | カップ1杯130g | 143μg |
| 玉露(抽出液) | 150μg | カップ1杯200g | 300μg |
 | 葉酸サプリメントの利用 | ||
基本的にはその他の栄養素も同時に取れる食事からの葉酸の摂取が望ましいのですが、妊婦の場合その推奨量は成人女性の倍の480μgになるため、食事だけで十分に取れない場合も考えられます。そうした場合はサプリメントの利用も検討されてみてはいかがでしょうか。
食品中の葉酸はそのほとんどがプテロイルポリグルタミン酸という形で存在していて、小腸でプテロイルモノグルタミン酸に変換され吸収されます。一方サプリメントは最初からプテロイルモノグルタミン酸の形で含まれています。プテロイルモノグルタミン酸はプテロイルポリグルタミン酸よりも約2倍の吸収率があります。
サプリメントは摂取しやすいだけでなく吸収率も高いのです。食品などで十分にとれない場合はサプリメントの利用を検討されるのもいいでしょう。
食品中の葉酸はそのほとんどがプテロイルポリグルタミン酸という形で存在していて、小腸でプテロイルモノグルタミン酸に変換され吸収されます。一方サプリメントは最初からプテロイルモノグルタミン酸の形で含まれています。プテロイルモノグルタミン酸はプテロイルポリグルタミン酸よりも約2倍の吸収率があります。
サプリメントは摂取しやすいだけでなく吸収率も高いのです。食品などで十分にとれない場合はサプリメントの利用を検討されるのもいいでしょう。
|
参考文献
7訂食品成分表2016 五訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表 おいしく健康をつくるあたらしい栄養学 栄養の基本がわかる図解事典 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
|
最終更新日 2020/04/08 公開日 2004/07/04 |
水溶性ビタミンの多い食品・食べ物一覧
 |
ビタミンB1の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンB2の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ナイアシンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
パントテン酸の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンB6の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンB12の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビオチンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンCの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
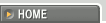
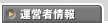
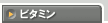
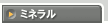
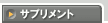
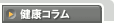



 水溶性ビタミン
水溶性ビタミン
