 |

|
|
ナイアシンの多い食品・食べ物と含有量一覧 | |

 | ナイアシンを多く含む食品 | ||
ナイアシンはカツオ、まぐろ、サバやかじき、さわら、たらこといった魚介類や、肉類、きのこ類、種実類全般に多く含まれます。そこで今回は牛・豚のレバー、鶏肉や豚肉、ビーフジャーキやクジラ肉などの肉類、まつたけやヒラタケ、シメジなどのキノコ類、種汁類のピーナッツなどに多く含まれます。
そこで今回はまずはナイアシンの働きや摂取の推奨量について見ていき、次いで各食品でナイアシンが多く含まれるものを見ていきます。
そこで今回はまずはナイアシンの働きや摂取の推奨量について見ていき、次いで各食品でナイアシンが多く含まれるものを見ていきます。
 | ナイアシンの主な働き | ||
ナイアシンには次のような働きがあります。
ナイアシン(NAD)はビタミンB2とともにたんぱく質の代謝過程である解糖系やクエン酸回路、β-酸化により発生したエネルギー豊富な水素を受け取り、それをミトコンドリア内の電子伝達系というところに運び、そこでエネルギー源となるATPが作られます。このようにナイアシンは体内でのエネルギー生産過程に大きくかかわります。
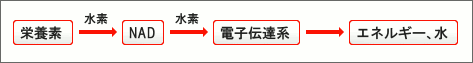
ナイアシンは脂質の代謝にもかかわります。高脂血症や動脈硬化の合剤の成分としてもナイアシンは使われています。
アルコールは体内でアルコール脱水素酵素によりアセトアルデヒドに分解されます。アセトアルデヒドは頭痛や吐き気、悪酔いや二日酔いの元凶となる成分なので、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素により無毒化されます。ナイアシン(ニコチン酸)はアルコール脱水素酵素とアセトアルデヒド脱水素酵素の補酵素として、アルコール代謝に関わります。
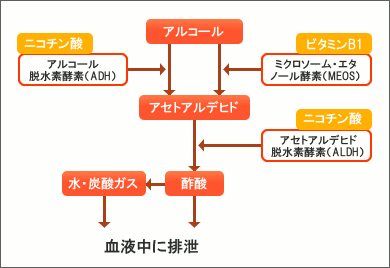
活性酸素により細胞を覆っている細胞膜が酸化されると、老化やがんの誘発などの原因となります。この活性酸素の働きを抑えるのが活性酸素除去酵素です。ナイアシンは活性酸素除去酵素であるグルタチオンペルオキシダーゼを再活性化させるのに関わります。
エネルギー代謝に関与
ナイアシン(NAD)はビタミンB2とともにたんぱく質の代謝過程である解糖系やクエン酸回路、β-酸化により発生したエネルギー豊富な水素を受け取り、それをミトコンドリア内の電子伝達系というところに運び、そこでエネルギー源となるATPが作られます。このようにナイアシンは体内でのエネルギー生産過程に大きくかかわります。
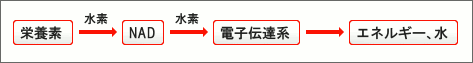
脂質の代謝にも関与
ナイアシンは脂質の代謝にもかかわります。高脂血症や動脈硬化の合剤の成分としてもナイアシンは使われています。
アルコール代謝にもかかわる
アルコールは体内でアルコール脱水素酵素によりアセトアルデヒドに分解されます。アセトアルデヒドは頭痛や吐き気、悪酔いや二日酔いの元凶となる成分なので、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素により無毒化されます。ナイアシン(ニコチン酸)はアルコール脱水素酵素とアセトアルデヒド脱水素酵素の補酵素として、アルコール代謝に関わります。
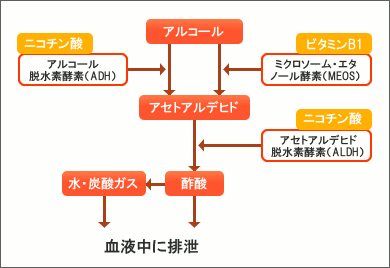
抗酸化作用にもかかわる
活性酸素により細胞を覆っている細胞膜が酸化されると、老化やがんの誘発などの原因となります。この活性酸素の働きを抑えるのが活性酸素除去酵素です。ナイアシンは活性酸素除去酵素であるグルタチオンペルオキシダーゼを再活性化させるのに関わります。
 | ナイアシン摂取の推奨量 | ||
ナイアシンの成人男子の推奨量は15mgNEで、成人女子の推奨量は11mgNEです。NE(niacin equivalent)とはナイアシン当量のことです。ナイアシンを求める計算式は次のようになります。
NE = ニコチン酸(mg) + ニコチンアミド(mg) + { トリプトファン X 1/60(mg)}
ナイアシンとはニコチン酸とニコチンアミドの総称のことで、トリプトファンはアミノ酸の一種で、体内でナイアシンに変換されます。上限量は成年男子がニコチンアミドが300mg、ニコチン酸が80mg、成年女子はニコチンアミドが250mg、ニコチン酸が65mgとなっています。
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。
NE = ニコチン酸(mg) + ニコチンアミド(mg) + { トリプトファン X 1/60(mg)}
ナイアシンとはニコチン酸とニコチンアミドの総称のことで、トリプトファンはアミノ酸の一種で、体内でナイアシンに変換されます。上限量は成年男子がニコチンアミドが300mg、ニコチン酸が80mg、成年女子はニコチンアミドが250mg、ニコチン酸が65mgとなっています。
|
ナイアシン成人男子推奨量:15mgNE ナイアシン成人女子推奨量:11mgNE |
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。
 | 魚介類でナイアシンの多い食品 | ||
魚類全般にナイアシンは豊富
ナイアシンは魚類全般に非常に多く含まれます。魚類は量も取りやすいので魚を毎日の献立に取り入れている食生活ならナイアシンが不足することはまずないでしょう。
かつおやまぐろ、かじきやさば、ぶり、かんぱちなど刺身として10切れほど食べるだけでもどれもほぼ一日の成人のナイアシンの推奨量を満たすだけの量が摂取できます。ご飯のお供としても定番のたらこや辛子明太子も一腹のせてたべるだけで推奨量以上のナイアシンを摂取できます。
たらこや明太子は特にナイアシンが多い

魚介類の中でもたらの卵を塩漬けにしたたらこは、特にナイアシンが豊富です。たらこをだし汁や唐辛子などの調味液でつけた辛子明太子は、たらこほどではありませんが、それでもナイアシンの量は豊富です。ちなみに上の画像はたらこです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| たらこ | 49.5mg | 1腹60g | 29.7mg |
| からしめんたいこ | 19.9mg | 1腹60g | 11.9mg |
かつお節もナイアシンが多い
かつお節もナイアシンの量はかなり豊富です。生のかつお自体も非常にナイアシンの含有量は多く、かつお節はそれを乾燥させることで100gあたりの含有量も高くなっています。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| かつお節 | 45.0mg | 1パック5g | 2.3mg |
| かつお | 19.0mg | 1切れ100g | 19.0mg |
まぐろもナイアシンが豊富
まぐろもナイアシンが豊富な魚です。マグロにも種類がありますが、種類によってナイアシンの量も異なります。最も多いのはマグロの中でも小型のびんながまぐろです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| びんながまぐろ | 20.7mg | 刺身10切れ150g | 31.0mg |
| きはだまぐろ | 17.5mg | 刺身10切れ150g | 26.2mg |
| くろまぐろ | 14.2mg | 刺身10切れ150g | 21.3mg |
| みなみまぐろ | 11.0mg | 刺身10切れ150g | 16.5mg |
するめもナイアシンが多い

するめもナイアシンが多く含まれます。するめはするめいかやけんさきいかを乾燥させたもので、生でもナイアシンの量は比較的多いですが、乾燥させることで100g当たりのナイアシンの量も凝縮されます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| するめ | 14.1mg | 1枚110g | 15.5mg |
| するめいか | 4.0mg | 1杯300g | 12.0mg |
| けんさきいか | 2.5mg | 1杯280g | 7mg |
かじきにもナイアシンがたくさん含まれる
かじきもナイアシンは豊富に含まれます。かじきの中ではくろかじきに特にナイアシンが多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| くろかじき | 13.5mg | 1切れ100g | 13.5mg |
| まかじき | 10.4mg | 1切れ100g | 10.4mg |
| めかじき | 7.6mg | 1切れ100g | 7.6mg |
さばもナイアシンが多い
さばもナイアシンが多いです。特にごまさばに多く含まれます。ごまさばはその名の通り腹側に、ゴマを散らしたような斑点があるのが特徴です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ごまさば | 14.6mg | 1切れ80g | 11.6mg |
| まさば | 10.4mg | 1切れ80g | 8.3mg |
| たいせいようさば | 6.5mg | 1切れ80g | 5.2mg |
いわしやめざしもナイアシンが多い
いわしやめざしもナイアシンが多いです。めざしはいわしの中羽ぐらいの大きさのものを丸干しにして、わら等で目を貫いて、数尾をまとめたもので、名前の由来にもなっています。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| めざし | 10.3mg | 1尾20g(17g) | 1.8mg |
| まいわし | 8.2mg | 1尾150g(68g) | 3.7mg |
ぶりやはまちもナイアシンが豊富
ぶりやはまちもナイアシンが豊富です。ちなみにはまちとぶりの違いは成熟度合いで、成熟したものをぶりといいます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ぶり | 9.5mg | 1切れ100g | 9.5mg |
| はまち | 9.0mg | 1切れ100g | 9.0mg |
さわらもナイアシンが多い

さわらはサバ科の魚で、スーパーでもよく見かける魚の一つです。こちらもナイアシンが多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| さわら | 9.5mg | 1尾80g | 7.6mg |
その他魚介類でナイアシンの多い食品
ほかにもかんぱちやズワイガニ、とびうお、さんま、しろさけ、にじます、きびなご、まだいなど、食卓でもよく見かける魚の多くが、たくさんのナイアシンを含んでいます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| かんぱち | 8.0mg | 刺身10切れ120g | 9.6mg |
| ずわいがに | 8.0mg | 1杯300g(90g) | 7.2mg |
| とびうお | 7.1mg | 1尾300g(180g) | 12.8mg |
| さんま | 7.0mg | 1尾150g(105g) | 7.4mg |
| しろさけ | 6.7mg | 1切れ80g | 5.4mg |
| にじます | 6.5mg | 1切れ100g | 6.5mg |
| きびなご | 6.2mg | 1尾10g(7g) | 0.4mg |
| まだい | 6.0mg | 1尾250g(125g) | 7.5mg |
| とらふぐ | 5.9mg | 刺身10切れ30g | 1.8mg |
| まあじ | 5.4mg | 1尾80g(40g) | 3.3mg |
| さより | 5.2mg | 1尾100g(60g) | 3.1mg |
| ひらめ | 5.0mg | 刺身10切れ80g | 4.0mg |
 | 肉類でナイアシンの多い食品 | ||
肉類全般にナイアシンは豊富
肉類も魚類と並びナイアシンが全般に非常に多く含まれる食品群です。肉はどれも量をとりやすいのでナイアシンをしっかりと摂るのにも適しています。
肉類の中でも特に100gあたりの含有量も高く、食事として量も摂りやすいのは牛肝臓、豚肝臓、くじら肉、ビーフジャーキー、鶏ささみ、鴨肉、鹿肉、鶏むね肉、豚ロース、豚もも肉などです。
肝臓に特にナイアシンが多い

牛や豚の肝臓にはナイアシンが多く含まれます。鶏肝臓は牛や豚に比べるとナイアシンの量は少ないです。豚や鶏肝臓はナイアシンの量が多いだけでなく、ビタミンAであるレチノールのも大量に含まれます。むしろ多すぎて過剰摂取の方が問題になるので、摂るときは少量に抑えた方がいいです。
牛肝臓は豚や鶏に比べるとレチノールの量はそれほどではありません。くわしくはビタミンAの多い食品・食べ物と含有量一覧でも解説しています。ちなみに上の画像は牛肝臓です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 牛肝臓 | 13.5mg | 1切れ40g | 5.4mg |
| 豚肝臓 | 14.0mg | 1切れ30g | 4.2mg |
| 鶏肝臓 | 4.5mg | 1切れ30g | 1.3mg |
クジラ肉もナイアシンが多い
クジラの肉にもナイアシンは多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| くじら肉 | 11.9mg | 刺身1切れ8g | 1.0mg |
牛の加工品もナイアシンが豊富

牛の赤肉を塩漬けにして乾燥させたビーフジャーキーや、牛肉を塩漬けにしてから高温、高圧で加熱し、ほぐして調味したコンビーフ、牛肉に香辛料を刷り込み、野菜などを敷いて焼いたローストビーフなど牛の加工品にもナイアシンは多く含まれます。ちなみに上の画像はビーフジャーキーです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ビーフジャーキー | 11.8mg | 1袋50g | 5.9mg |
| コンビーフ缶詰 | 7.6mg | 1缶100g | 7.6mg |
| ローストビーフ | 6.3mg | 1切れ15g | 0.9mg |
鶏肉はむね肉やささみにナイアシンが多い

鶏肉だとむね肉やささみの部分にナイアシンが多く含まれます。ちなみに上の画像は鶏むね肉です。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 鶏ささみ | 11.0mg | 1本40g | 4.5mg |
| 鶏むね肉 | 7.9mg | 1枚200g | 15.8mg |
豚肉はロースやもも肉にナイアシンが多い
豚肉も全般にナイアシンが多く含まれますが、特にロース肉やもも肉に多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 豚ロース | 7.3mg | 厚1cm1枚100g | 7.3mg |
| 豚もも肉 | 6.2mg | 厚1cm1枚100g | 6.2mg |
| 豚ひき肉 | 5.6mg | 卵大1かたまり50g | 2.8mg |
| 豚ヒレ肉 | 5.3mg | 厚1cm1枚30g | 1.6mg |
ハムもナイアシンが多い
豚の加工品であるハムもナイアシンが豊富に含まれます。豚肉でもナイアシンの多いロースを使ったロースハムや、もも肉を使ったボンレスハムなどが特にナイアシンが多いです。ロースやもも肉を使った生ハムはナイアシンの含有量は多いです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 生ハム | 9.9mg | 薄1枚7g | 0.7mg |
| ロースハム | 6.6mg | 薄1枚20g | 1.3mg |
| ボンレスハム | 6.5mg | 薄1枚20g | 1.3mg |
鴨肉もナイアシンが多い
鴨肉もナイアシンが多く含まれます。かもにはまがもとまがもとアヒルの交雑種である合鴨がありますが、まがものほうがナイアシンが多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| まがも | 9.3mg | 薄1枚40g | 3.7mg |
| 合鴨 | 3.8mg | 薄1枚40g | 1.5mg |
その他肉類でナイアシンが多い食品
その他にも鹿肉や七面鳥、ヤギ肉、馬肉、いのしし肉などもナイアシンが多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 鹿肉 | 8.0mg | 厚1cm1枚100g | 8.0mg |
| 七面鳥 | 7.0mg | 薄1枚40g | 2.8mg |
| ヤギ肉 | 6.7mg | 刺身1切れ10g | 0.7mg |
| 馬肉 | 5.8mg | 刺身1切れ15g | 0.9mg |
| 牛もも肉 | 5.6mg | 薄1枚70g | 3.9mg |
| いのしし | 5.2mg | 薄1枚15g | 0.3mg |
 | きのこ類でナイアシンの多い食品 | ||
きのこも全般にナイアシンが多い
きのこは基本火を通して食べる食材なのでゆでた状態での栄養素を掲載しています。きのこ類も全般にナイアシンの多い食品群です。炒め物やみそ汁の具などに料理して食べられます。量も取りやすいのでナイアシンを摂取しやすい食品群です。
まつたけはナイアシンが豊富
まつたけはナイアシンが豊富に含まれます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| まつたけ | 8.0mg | 1本30g | 2.4mg |
ひらたけもナイアシンが豊富

エリンギにもナイアシンは豊富に含まれます。ちなみに上の画像はひらたけです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ひらたけ(ゆで) | 7.0mg | 1パック85g | 5.9mg |
しめじはナイアシンが多い
しめじもナイアシンは多く含まれます。はたけしめじやほんしめじ、ぶなしめじと種類がありますが、ナイアシンの量はぶなしめじが最も多いです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ぶなしめじ(ゆで) | 5.2mg | 1パック100g | 5.2mg |
| ほんしめじ(ゆで) | 3.7mg | 1パック100g | 3.7mg |
| はたけしめじ(ゆで) | 3.6mg | 1パック100g | 3.6mg |
なめこはナイアシンが多い

なめこもナイアシンが多いです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| なめこ(ゆで) | 4.7mg | 1パック100g | 4.7mg |
 | 藻類でナイアシンの多い食品 | ||

海藻類の中ではあじつけのりやほしのり、焼きのり、あおのり、いわのりなど、のり全般にナイアシンが多く含まれます。のりは100gあたりのナイアシンの含有量自体は高いですが、乾燥した食品なので、重量がそれほどなく、一度の料理で使う量も限られます。そのため取れるナイアシンの量も少量になります。
あおさは一袋では35gですが酢の物やみそ汁の具に使うとして1人前で使う量は5gほどです。5gだと取れるナイアシンの量も0.5mgほどです。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 味付けのり | 12.2mg | 小10枚3g | 0.4mg |
| ほしのり | 11.8mg | 1枚3g | 0.4mg |
| 焼きのり | 11.7mg | 小10枚3g | 0.4mg |
| あおさ | 10.0mg | 1袋35g | 3.5mg |
| あおのり(素干し) | 6.1mg | 大さじ1杯2g | 0.1mg |
| いわのり(素干し) | 5.4mg | 1枚10g | 0.5mg |
 | 種実類でナイアシンの多い食品 | ||

種実類の中ではごまやひまわりの種、落花生などにナイアシンが多く含まれます。それほどたくさん量を食べるものでもないので、一度に摂れる量も限られます。
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| 落花生(いり) | 17.0mg | 10粒9g | 1.5mg |
| バターピーナッツ | 17.0mg | 10粒8g | 1.4mg |
| ひまわりの種(フライ) | 6.7mg | 10粒9g | 0.6mg |
| ごま(いり) | 5.3mg | 大さじ1杯6g | 0.3mg |
 | まとめ | ||
魚、肉、きのこ類をとっていれば不足はまれ
ナイアシンは魚類、肉類、きのこ類全般に多く含まれているので、こうした食品をしっかりと毎日の献立に取り入れている食生活であれば、不足する心配はありません。各食品群の中でも魚類ならたらこやからしめんたいこ、かつおやマグロ、カジキやさば、ブリなど、肉類なら牛や豚の肝臓、鶏ささみ、くじら肉、鴨肉、鶏むね肉、きのこ類ならエリンギ、ほんしめじ、ひらたけなどは100gあたりのナイアシンの含有量も高く、食事としても量を取りやすいので特におすすめです。
藻類や種実類は食事で取れる量が限られる
100gあたりの単位で見れば藻類や種実類も魚や肉、きのこ類に負けないぐらいのナイアシンの含有量はありますが、どちらも食事として量が摂りづらいので、ナイアシンを効率的に摂取するにはむいていません。
ナイアシンを特にとりやすい食品
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| たらこ | 49.5mg | 1腹60g | 29.7mg |
| からしめんたいこ | 19.9mg | 1腹60g | 11.9mg |
| かつお | 19.0mg | 1切れ100g | 19.0mg |
| びんながまぐろ | 20.7mg | 刺身10切れ150g | 31.0mg |
| きはだまぐろ | 17.5mg | 刺身10切れ150g | 26.2mg |
| くろまぐろ | 14.2mg | 刺身10切れ150g | 21.3mg |
| するめ | 14.1mg | 1枚110g | 15.5mg |
| まかじき | 10.4mg | 1切れ100g | 10.4mg |
| まさば | 10.4mg | 1切れ80g | 8.3mg |
| ぶり | 9.5mg | 1切れ100g | 9.5mg |
| さわら | 9.5mg | 1尾80g | 7.6mg |
| かんぱち | 8.0mg | 刺身10切れ120g | 9.6mg |
| ずわいがに | 8.0mg | 1杯300g(90g) | 7.2mg |
| とびうお | 7.1mg | 1尾300g(180g) | 12.8mg |
| さんま | 7.0mg | 1尾150g(105g) | 7.4mg |
| まだい | 6.0mg | 1尾250g(125g) | 7.5mg |
| 牛肝臓 | 13.5mg | 1切れ40g | 5.4mg |
| 豚肝臓 | 14.0mg | 1切れ30g | 4.2mg |
| くじら肉 | 11.9mg | 刺身1切れ8g | 1.0mg |
| ビーフジャーキー | 11.8mg | 1袋50g | 5.9mg |
| 鶏ささみ | 11.0mg | 1本40g | 4.5mg |
| 鴨肉 | 9.3mg | 薄1枚40g | 3.7mg |
| 鹿肉 | 8.0mg | 厚1cm1枚100g | 8.0mg |
| 鶏むね肉 | 7.9mg | 1枚200g | 15.8mg |
| ひらたけ(ゆで) | 7.0mg | 1パック85g | 5.9mg |
 | ナイアシンは体内でも合成される | ||
たんぱく質からも合成される
ちなみにナイアシンは体内でもたんぱく質のトリプトファンから合成されます。日本食品標準成分表に記載されているナイアシン量には食品に含まれるトリプトファンから計算した体内でのナイアシン転換量は考慮されていません。
まず各食品のたんぱく質の内平均して1%がトリプトファン量で、ナイアシンへと転換されるとその量は1/60となります。計算するさいはたんぱく質の量を6000で割るとナイアシンへの転換量を知ることが出来ます。たとえばある食品のたんぱく質が100g辺り20gであれば、ナイアシンの転換量は20を6000で割って33mgとなります。このようにたんぱく質をしっかりと摂っていれば体内での合成によりナイアシンを十分に満たすことができます。
ただしたんぱく質の中にはとうもろこしたんぱく質やコラーゲンなど含まれるトリプトファンの量が少ないものもあります。
ビタミンB2とB6の摂取も
トリプトファンの体内でのナイアシンへの転換には様々な栄養素も関与していて、ビタミンB2やB6も欠かせません。このためビタミンB2やB6もしっかりと摂取することが大切です。
参考文献
 日本食品標準成分表2010 日本食品標準成分表2010 五訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表 五訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表
|
 ページTOPへ ページTOPへ
|
|
最終更新日 2019/09/06 公開日 2004/06/18 |
水溶性ビタミンの多い食品・食べ物一覧
 |
ビタミンB1の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンB2の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
パントテン酸の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンB6の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンB12の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビオチンの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
葉酸の多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンCの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
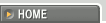
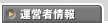
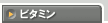
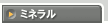
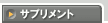
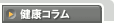



 水溶性ビタミン
水溶性ビタミン
