|
ナイアシンの効果・効能 
|
|
| |
 | |
エネルギー産生を助ける
|
|
ナイアシンとはニコチン酸とニコチン酸アミドの総称で、体内では活性型ニコチン酸であるNAD(ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド)やNADP(ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド・リン酸)となって、脂質や糖質からエネルギーを産生する際に働く酸化還元酵素の補酵素として働きます。
ナイアシンはまず栄養素(グルコース、脂肪酸、アミノ酸などに由来)に存在する水素を奪いNADH2となり、奪った水素をミトコンドリアに存在する電子伝達系に送り込み、そこで水素が受け渡される過程でエネルギーが生成され、最終的に水素は酸素と結合して水となります。
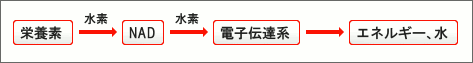
|
| |
 | |
エネルギーの橋渡し
|
|
ナイアシンとエネルギー生産との関係についてもう少し詳しく見て行きます。体内でエネルギーとして使われるATP(アデノシン3リン酸)の生成は主に細胞内に含まれるミトコンドリアの内膜にある電子伝達系で行われます。まずは糖質や脂質、たんぱく質の代謝経路である解糖系やクエン酸回路、β-酸化の過程で脱水素酵素の働きにより水素が放出されます。この水素を受け取るのがナイアシンであるNAD+と同じビタミンであるビタミンB2(FAD:フラビン・アデニンジ・ヌクレオチド)です。
NAD+やFADは水素を受け取りNADHとFADH2となります。これが電子伝達系でまずNADHはNAD+とH+の2つの電子となり、FADH2はFADと2H+の2つの電子となります。それぞれ2つの電子が電子伝達系の中の3つの複合体を経由する際にエネルギー源であるATPが生成されます。複合体には1〜4まで4つの種類があり、NADHは1、3、4の複合体を経由し、FADH2は2、3、4の複合体を経由します。
電子は最後酸素(02)に受け渡され、O2-と水素イオン(2H+)が結合して水(H2O)が生成されます。
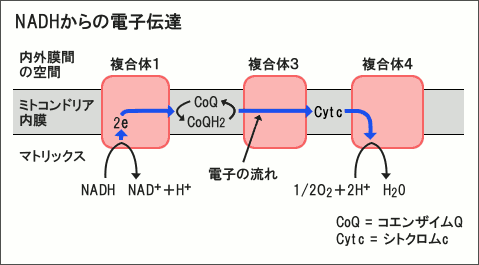
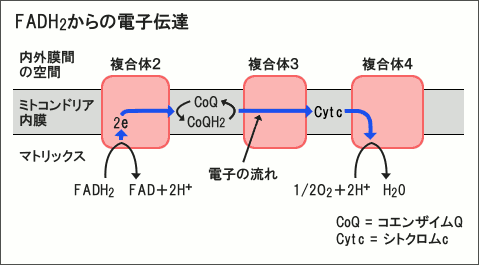
このように生命活動の根幹であるエネルギー源のATPの生産において、糖質、脂質、たんぱく質の代謝過程で発生するエネルギーの豊富な水素を受け取り、それを電子伝達系まで運び段階的にたくさんのエネルギーを取り出してATPを生成するうえでその橋渡しとなるのがナイアシン(NAD+)とビタミンB2(FAD)なのです。ビタミンとエネルギー代謝については疲労とビタミン、エネルギー代謝とビタミンでも詳しく解説しています。
|
| |
 | |
脂質の代謝の促進
|
|
|
ナイアシンには脂質の代謝を促進する働きもあり、1日に1500mgのナイアシン摂取で中性脂肪やコレステロール値が低下することが知られています。ビタミンEとナイアシンの合剤が高脂血症や動脈硬化の医薬品としても使われています。
|
| |
 | |
多くの酵素反応に関与
|
|
|
ナイアシンの活性型であるNAD(P)を補酵素として必要とする酵素は400種類以上にも達し、人における酵素の20%程度を占めています。その栄養素としての必要量も他のビタミンB郡よりもかなり多く、10〜20倍程度となっています。
|
| |
 | |
アルコール分解作用
|
|
ナイアシンはビタミンB1とともにアルコールの分解に密接にかかわります。摂取したアルコールは肝臓でアルコール脱水素酵素(ADH)によりアセトアルデヒトに分解されます。アセトアルデヒドは頭痛や吐き気、悪酔いや二日酔いの元凶となる成分です。アセトアルデヒドはアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)により無毒化されます。ナイアシン(ニコチン酸)はADHやALDHの補酵素としてその働きを助けます。アルコールを飲んだ分だけしっかりとナイアシンも補給しないと、肝臓でのアルコールの代謝に手間取り、肝臓への負担が増してしまいます。
お酒を飲みすぎてADHだけでは分解が追いつかない場合には、肝臓の細胞内にあるミクロソーム・エタノール酵素(MEOS)もアルコールの分解に働きます。このMEOSが働くときにはビタミンB1が大量に消費されます。このようにアルコール分解にはナイアシンとともにビタミンB1も深くかかわっています。
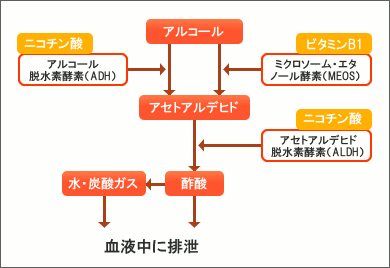
|
| |
 | |
抗酸化作用
|
|
体を構成する細胞は不飽和脂肪酸と呼ばれる細胞膜によって覆われています。活性酸素はこの不飽和脂肪酸を酸化させて過酸化脂質を形成し、その結果細胞は鉄が空気中の酸素の影響でさびるのと同じように、さびて老化の進行やガンの誘発などの原因となります。細胞内に蓄積した過酸化脂質は活性酸素除去酵素であるグルタチオンペルオキシダーゼによって水とアルコールに分解されます。この際グルタチオンが消費され酸化型グルタチオンとなります。ナイアシンはNADPHの形で酸化型グルタチオンをグルタチオンに戻す働きがあります。
|
■活性酸素
体内で酸素を使用する様々な代謝過程において、そのごく一部が反応性の強い活性酸素となります。活性酸素は免疫機能をつかさどる反面、過剰に発生した場合細胞を攻撃して傷つけてしまうこともあります。活性酸素は、スーパーオキシドアニオンラジカル、過酸化水素、ヒドロキシラジカル、一重項酸素などが知られています。
■フリーラジカル
ついになっていない電子(不対電子)を持ち、不安定で反応性に富む原子団を持つものをフリーラジカルと呼びます。ついになっていない電子は安定しようと他から電子を奪おうとします。電子が奪われることを酸化、電子が与えられることを還元と言います。
フリーラジカルによって電子が奪われた側は新たなフリーラジカルとなり、さらに他から電子を奪うという酸化の連鎖が続いてしまいます。
活性酸素のスーパーオキシドアニオンラジカルやヒドロキシラジカルもフリーラジカルの一種です。
|
※関連コラム >>老化の原因、活性酸素とは
|
| |
 | |
ナイアシンの成人推奨量
|
|
ナイアシンの1日の推奨量は成人男子で15mgNE、成人女子で11mgNEです。ナイアシンはナイアシン当量(NE = niacin equivalent)で表されます。計算式は次のとおりです。
NE = ニコチン酸(mg) + ニコチンアミド(mg) + { トリプトファン X 1/60(mg)}
ナイアシンは体内でトリプトファンと呼ばれる必須アミノ酸からも作られその転換率は1/60とされます。ニコチン酸とニコチンアミドはこれらを総称してナイアシンと呼ぶため、それにプラス、トリプトファンからの転換量を合計したものがナイアシン当量(NE)となります。
|
 ナイアシンの年代別食事摂取基準
ナイアシンの年代別食事摂取基準
| 年齢
|
男性(mgNE)
|
女性(mgNE)
|
推定平均
必要量
|
推奨量
|
目安量
|
上限量
|
推定平均
必要量
|
推奨量
|
目安量
|
上限量
|
|
0〜5 (月)
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
|
6〜11 (月)
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
|
1〜2
|
5
|
6
|
-
|
60(15)
|
4
|
5
|
-
|
60(15)
|
|
3〜5
|
6
|
8
|
-
|
80(20)
|
6
|
7
|
-
|
80(20)
|
|
6〜7
|
7
|
9
|
-
|
100(30)
|
7
|
8
|
-
|
100(25)
|
|
8〜9
|
9
|
11
|
-
|
150(35)
|
8
|
10
|
-
|
150(35)
|
|
10〜11
|
11
|
13
|
-
|
200(45)
|
10
|
10
|
-
|
150(45)
|
|
12〜14
|
12
|
15
|
-
|
250(60)
|
12
|
14
|
-
|
250(60)
|
|
15〜17
|
14
|
17
|
-
|
300(70)
|
11
|
13
|
-
|
250(65)
|
|
18〜29
|
13
|
15
|
-
|
300(80)
|
9
|
11
|
-
|
250(65)
|
|
30〜49
|
13
|
15
|
-
|
350(85)
|
10
|
12
|
-
|
250(65)
|
|
50〜64
|
12
|
14
|
-
|
350(85)
|
9
|
11
|
-
|
250(65)
|
|
65〜74
|
12
|
14
|
-
|
300(80)
|
9
|
11
|
-
|
250(65)
|
|
75以上
|
11
|
13
|
-
|
300(75)
|
9
|
10
|
-
|
250(60)
|
|
|
妊婦(付加量)
|
|
+0
|
+0
|
-
|
-
|
|
授乳婦(付加量)
|
+3
|
+3
|
-
|
-
|
※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2020年版)
上限量はニコチンアミドのmg量、( )内はニコチン酸のmg量
各指標の見方について
参考文献
医療従事者のための機能性食品ガイド
わかりやすいからだとビタミンの知識
サプリメントデータブック
基礎栄養学 健康・栄養科学シリーズ
医療従事者のためのサプリメント・機能性食品事典
わかりやすい生化学
栄養科学シリーズNEXT生化学
よくわかる栄養学の基本としくみ
基礎栄養学第3版 スタンダード栄養・食物シリーズ
栄養・健康科学シリーズ生化学
日本人の食事摂取基準(2020年版)
|
この記事を書いた人

kain
ビタミネ管理人のkainと申します。2003年より当サイトを運営。ビタミンやミネラルに関する記事を多くの参考文献をもとに多数執筆。各記事には参考文献一覧も明示。
>> 詳しくはこちら




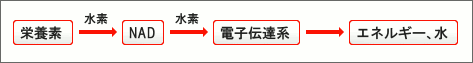

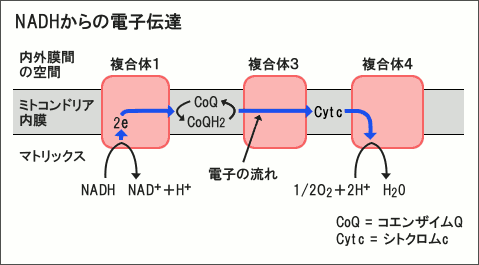
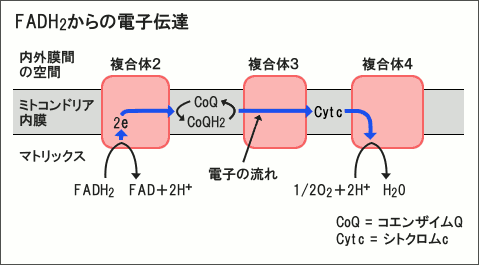



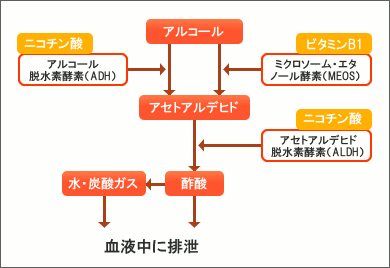


 ナイアシンの年代別食事摂取基準
ナイアシンの年代別食事摂取基準
 ページTOPへ
ページTOPへ
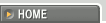
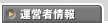
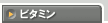
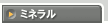
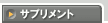
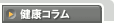



 水溶性ビタミン
水溶性ビタミン
