 |

|
|
ビタミンDの多い食品・食べ物と含有量一覧
 | ビタミンDを多く含む食品 | ||
ビタミンDを摂取できる食品というのはそれほど多くはないのですが、魚類だけは別で全般に多く含まれています。中でもかわはぎやさけ、ます、にしん、うなぎ、しらす干し、からすみなどは特に多くのビタミンDが含まれます。魚類以外だときのこ類のきくらげやまいたけ、卵の卵黄やピータン、鴨肉やすっぽん、マーガリンなどにもビタミンDはよく含まれます。
今回はビタミンDの効能や推奨量からみていき、ビタミンDが多く摂れる食品群を詳しく解説していきます。さらにビタミンDを摂取するうえでのポイントなども見ていきます。
今回はビタミンDの効能や推奨量からみていき、ビタミンDが多く摂れる食品群を詳しく解説していきます。さらにビタミンDを摂取するうえでのポイントなども見ていきます。
 | ビタミンDの主な働き | ||
ビタミンDには次のような働きがあります。
ビタミンDには動物由来のビタミンD3と植物由来のビタミンD2の大きく2種類があります。どちらも太陽からの紫外線により生合成されます。ビタミンD3は人の体内でも生合成されます。皮膚表面でプロビタミンDが紫外線により光化学反応を起こし、さらに体温で熱異性化反応を起こして作られます。このためビタミンDを体内でしっかりと合成するためにも日の光を浴びる生活が重要となります。ちなみにビタミンD3もビタミンD2も体内での生理反応は同じです。
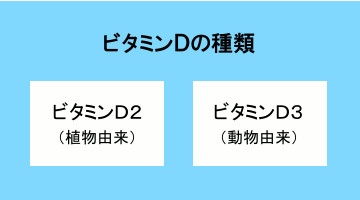
血中のカルシウム濃度が低下すると副甲状腺ホルモンの刺激により酵素が活性化され、その酵素によりビタミンDは活性型ビタミンDへと変化します。活性型ビタミンDは小腸でのカルシウムの吸収や腎臓でのカルシウムの再吸収、骨から血中へのカルシウムの溶出を促進することで、血中のカルシウム濃度を上昇させる働きがあります。血中のカルシウム濃度が正常もしくは高くなると、今度は活性型ビタミンDは酵素の働きにより非活性型のビタミンDへと変化します。
骨は破壊と再生が絶えず繰り返され、一定の骨量が維持されています。ビタミンDは骨の主要成分であるカルシウムを骨から血中へと溶出させる働きと、血中のカルシウムの骨への沈着の両方に作用することで骨のリモデリング(骨の破壊と再構築)の維持に関わります。ビタミンDの欠乏症には骨の形成不全によるくる病や骨軟化症、骨粗しょう症などがあります。くる病とは乳幼児に見られる四肢や背骨などの湾曲が見られる症状のことです。こうした欠乏症を予防する意味でも、ビタミンDはしっかりと摂取することが望まれます。
ビタミンDは2種類ある
ビタミンDには動物由来のビタミンD3と植物由来のビタミンD2の大きく2種類があります。どちらも太陽からの紫外線により生合成されます。ビタミンD3は人の体内でも生合成されます。皮膚表面でプロビタミンDが紫外線により光化学反応を起こし、さらに体温で熱異性化反応を起こして作られます。このためビタミンDを体内でしっかりと合成するためにも日の光を浴びる生活が重要となります。ちなみにビタミンD3もビタミンD2も体内での生理反応は同じです。
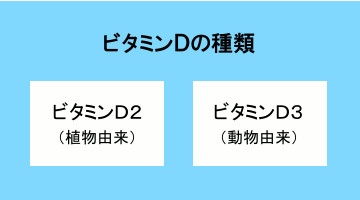
カルシウムの吸収促進
血中のカルシウム濃度が低下すると副甲状腺ホルモンの刺激により酵素が活性化され、その酵素によりビタミンDは活性型ビタミンDへと変化します。活性型ビタミンDは小腸でのカルシウムの吸収や腎臓でのカルシウムの再吸収、骨から血中へのカルシウムの溶出を促進することで、血中のカルシウム濃度を上昇させる働きがあります。血中のカルシウム濃度が正常もしくは高くなると、今度は活性型ビタミンDは酵素の働きにより非活性型のビタミンDへと変化します。
骨の形成に関与
骨は破壊と再生が絶えず繰り返され、一定の骨量が維持されています。ビタミンDは骨の主要成分であるカルシウムを骨から血中へと溶出させる働きと、血中のカルシウムの骨への沈着の両方に作用することで骨のリモデリング(骨の破壊と再構築)の維持に関わります。ビタミンDの欠乏症には骨の形成不全によるくる病や骨軟化症、骨粗しょう症などがあります。くる病とは乳幼児に見られる四肢や背骨などの湾曲が見られる症状のことです。こうした欠乏症を予防する意味でも、ビタミンDはしっかりと摂取することが望まれます。
 | ビタミンD摂取の推奨量 | ||
ビタミンDの目安量
ビタミンDの成人男女の目安量は8.5μgとされています。ビタミンDは日の光を浴びることで体内でも合成されるため、適度に日に当たる生活をしているなら不足することはまれです。日に当たる機会が少ない方は食品からの摂取も大切です。高齢になると体内でのビタミンD合成量も落ちてくるので、高齢者も食事からの摂取が重要となります。
ビタミンDの上限量
ビタミンDは摂りすぎによる過剰症にも注意が必要です。日本食事摂取基準ではビタミンDの成人男女の上限量は100μgと定められています。上限量を超すビタミンDを取り続けると高カルシウム血症や腎障害、組織の石灰化などの過剰症の心配が出てきます。
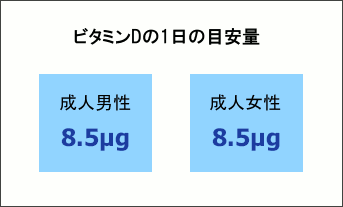
下一覧表の食品目安量では1個や1尾、1枚など食品一単位や一回の食事で使う量などを表しています。そのうちの食べない部分を除いた可食部重量は()内で表示しています。 目安量(可食部)中の成分含有量とはその目安量(可食部)でどの程度栄養成分を含むかを表しています。
 | 魚類でビタミンDの多い食品 | ||
魚類は全般にビタミンDが多い
魚類は全般にビタミンDの含有量の多い食品群です。他の食品群と比べてもビタミンDの含有量が多く、量も取りやすいのでビタミンDの摂取に非常に優れた食品群だといえます。
カワハギはビタミンDが非常に豊富
カワハギはビタミンDが非常に豊富で1尾で30μgものビタミンDを摂取できます。カワハギは白身魚で淡白な味が特徴で、焼き魚、ムニエル、刺身などにして食べるとおいしいです。皮を簡単にはがせることからカワハギという名がついています。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| かわはぎ | 43μg | 1尾200g(70g) | 30μg |
さけ・ますもビタミンDが多い
さけやますにもビタミンDが非常に多く含まれていて、さらに食事として量も摂りやすいのでビタミンDを摂取しやすい食品です。ますは淡水生活するサケ科の魚をさす言葉です。さけ・ますではしろさけ、べにざけ、ぎんざけ、からふとますのどれもビタミンDの量は多いのですが、中でもしろさけがビタミンDの量は多いです。
白さけの卵を塩蔵したイクラにもビタミンDは豊富に含まれます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| イクラ | 44μg | 大さじ1杯17g | 7μg |
| しろさけ(焼き) | 39.4μg | 1切れ59g | 23.2μg |
| べにざけ(焼き) | 38.4μg | 1切れ80g | 30.7μg |
| からふとます(焼き) | 31.2μg | 1切れ75g | 23.4μg |
| ぎんざけ(焼き) | 21.0μg | 1切れ78g | 16.3μg |
かじきもビタミンDが多い
かじきはカジキマグロとも呼ばれますが、マグロとは違う種類の魚です。このかじきにもビタミンDが豊富に含まれます。かじきにはくろかじき、まかじき、めかじきと大きく3種類ありますが、くろかじきが最もビタミンDの量が多いです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| くろかじき | 38μg | 1切れ100g | 38μg |
| まかじき | 12μg | 1切れ100g | 12μg |
| めかじき | 8.8μg | 1切れ100g | 8.8μg |
からすみ、ぼらもビタミンDは豊富
からすみはぼらの卵巣を塩蔵して、塩抜きにしてから乾燥したもので、こちらもビタミンDが多く含まれます。からすみは塩分も多いので摂り過ぎには注意が必要です。ぼら自体も刺身や洗い、焼き魚などにして食べられます。こちらもビタミンDが多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| からすみ | 33μg | 1腹80g | 26.4μg |
| ぼら | 10μg | 1尾600g(300g) | 30μg |
にしんやいわしもビタミンDが多い
にしんもいわしもどちらもにしん科の魚で、ともにビタミンDが多く含まれます。にしんは3月から5月が旬で、焼き魚や味噌煮、ムニエル、マリネ、燻製など様々な料理に利用されます。にしんの卵を塩漬けにしたかずのこにもビタミンDが豊富に含まれます。
いわしにはうるめいわしやかたくちいわし、まいわしなど種類があり、種類によってビタミンDの量も違います。最もビタミンDが多いのはまいわしです。うるめいわしは主に丸干しに、かたくちいわしは主に煮干しとして市場に出回ります。かたくちいわしやまいわしで中羽ほどの大きさのものを丸干しにしためざしにもビタミンDは多く含まれます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| にしん | 22μg | 1尾200g(110g) | 24μg |
| かたくちいわし(煮干し) | 18.0μg | 10尾20g(20g) | 3.6μg |
| かずのこ(塩蔵) | 17μg | 1本20g | 3μg |
| まいわし(焼き) | 14.4μg | 1尾60g(39g) | 5.6μg |
| めざし(焼き) | 11.1μg | 1尾15g(13g) | 1μg |
| うるめいわし(丸干し) | 8.0μg | 1尾10g(9g) | 0.7μg |
| かたくちいわし | 4.0μg | 1尾15g(8g) | 0.3μg |
うなぎもビタミンDが豊富な食品

うなぎもビタミンDが多くて量も摂りやすい食品です。うなぎやたれをつけずにそのまま焼く白焼きや、たれをつけて焼くかば焼きがありますが、ビタミンDは蒲焼きの方が若干多いです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| うなぎ蒲焼き | 19μg | 1串80g | 15.2μg |
| うなぎ白焼き | 17μg | 1串80g | 13.6μg |
かれいもビタミンDが多い
カレイもビタミンDの多い魚です。かれいにもまがれいとまこがれいがありますが、水揚げ量が多いのはまこがれいの方です。ビタミンDの量で言うとまがれいの方がまこがれいの約2倍ほど多く含まれています。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| まがれい(焼き) | 17.5μg | 1尾200g(130g) | 22.8μg |
| まこがれい(焼き) | 9.2μg | 1尾150g(75g) | 6.9μg |
あゆもビタミンDが豊富

あゆにもビタミンDが豊富に含まれます。天然と養殖では養殖物の方が圧倒的にビタミンDの量は多いです。天然だと養殖分の10分の1以下のビタミンDの量しかありません。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| あゆ(養殖・焼き) | 17.4μg | 1尾70g(32g) | 5.6μg |
| あゆ(天然・焼き) | 1.5μg | 1尾55g(25g) | 0.3μg |
しらす干しは少量でも十分な量が

しらす干しもビタミンDの含有量が高いので、大さじ1、2杯など少量でも成年男女の1日の目安量を満たすだけのビタミンDを摂取することができます。しらす干しはよく乾燥させた関西向けの半乾燥品(ちりめんじゃこ)の方が100gあたりのビタミンDの量(61.0μg)は多いです。関東向けの軽く乾燥させた微乾燥品だと100g当たりのビタミンDの量は46.0μgほどです。ちなみに下の画像は半乾燥品(ちりめんじゃこ)です。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| しらす干し(半乾燥品) | 61μg | 大さじ1杯5g | 3μg |
| しらす干し(微乾燥品) | 46μg | 大さじ1杯5g | 2.3μg |
あんこうの肝は摂り過ぎに注意
最も100gあたりの含有量の高いあんこうのきもは一切れ(50g)でも55μgものビタミンDが含まれているので、こちらはむしろ取りすぎに注意したほうがいいでしょう。あんこうの肝はビタミンAのレチノールも豊富です。一切れでもレチノールの上限量を超えてしまうのでやはり少量での利用が望ましいといえます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| あんこう・きも | 110μg | ぶつ切り1切れ50g | 55μg |
貝類、甲殻類にはほとんど含まれない
動物性食品に含まれるビタミンD3は動物の皮膚表面で紫外線を受けることにより化学変化が生じて生成されると考えられています。そのためなのかかたい殻に覆われた貝やエビ、カニなどではビタミンDは0か含まれていてもごく少量です。
その他ビタミンDの多い魚介類
ほかにもいかなごやいさき、こい、たちうお、さんま、さわら、まかじき、まあじ、まさばなどもビタミンDの多い食品です。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| いかなご(佃煮) | 23μg | 大さじ1杯10g | 2μg |
| いさき | 15μg | 1尾200g(110g) | 17μg |
| こい | 14μg | 輪1切れ150g(128g) | 18μg |
| たちうお | 14μg | 1切れ100g | 14μg |
| さんま(焼き) | 13.0μg | 1尾120g(84g) | 10.9μg |
| さわら(焼き) | 12.1μg | 1切れ65g | 7.9μg |
| まあじ(焼き) | 11.7μg | 1尾110g(72g) | 8.4μg |
| まさば | 11μg | 1切れ80g | 9μg |
 | きのこ類でビタミンDの多い食品 | ||
きくらげはビタミンDが多い

きのこ類ではきくらげには特に多くのビタミンDが含まれています。きくらげは、きくらげとあらげきくらげがあり、きくらげは肉質が薄く、あらげきくらげは肉厚なのが特徴です。きくらげは酢の物などによく利用され、あらげきくらげは炒め物などによく利用されます。ビタミンDはあらげきくらげに特に多く含まれていて、油で炒めるとより多くのビタミンDを摂取することができます。あらげきくらげは裏白きくらげ、黒きくらげなどとも呼ばれます。ちなみに上の画像は生のあらげきくらげです。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| あらげきくらげ(油いため) | 37.7μg | 1個34g | 12.8μg |
| あらげきくらげ(ゆで) | 25.3μg | 1個34g | 8.6μg |
| きくらげ(ゆで) | 8.8μg | 10個30g | 2.6μg |
まいたけもビタミンDが多い

まいたけもきくらげに次いできのこ類ではビタミンDが多く含まれる食品です。こちらも油でいためた方がより多くのビタミンDを摂取できます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| まいたけ(油いため) | 7.3μg | 1パック75g | 5.5μg |
| まいたけ(ゆで) | 5.9μg | 1パック75g | 4.4μg |
 | その他食品でビタミンDの多い食品 | ||
肉類でビタミンDの多い食品
肉類にはビタミンDはそれほど多くは含まれていません。1μg以下の含有量のものが多いのが全体的な特徴です。肉類なら鴨やすっぽんには比較的多くのビタミンDが含まれていますが、それでも魚介類全般と比べると見劣りします。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| すっぽん | 3.6μg | 1匹560g(560g) | 22μg |
| かも | 3.1μg | 薄1枚40g | 1μg |
卵類でビタミンDの多い食品

卵類もビタミンDがよく含まれている食品群です。ビタミンDは卵黄の部分が中心で、卵白にはまったく含まれていません。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| ピータン | 6.2μg | 1個100g(55g) | 3μg |
| 卵黄 | 5.9μg | 1個分18g | 1μg |
油脂類でビタミンDの多い食品

油脂類のマーガリンにもビタミンDは多く含まれます。これは添加物としてビタミンDが加えられているからです。ちなみにバターは100gあたりでビタミンDが0.6μg含まれます。
| 食品名 | 含有量(μg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| マーガリン | 11.2μg | 大さじ1杯12g | 1.3μg |
 | ビタミンDを摂取する上でのポイント | ||
体内でも合成される
ビタミンDは体内でも合成することができます。太陽の日を浴びると紫外線からビタミンD3が合成されます。一日に10分から20分日の光を浴びると必要量を満たすビタミンD3が合成されるといいます。このため毎日外にでて日の光を浴びる生活をしていればビタミンDが不足することは稀です。
体内での合成は年とともにその量が減少していき、また皮膚が黒い人もその分紫外線の影響が少なくなるのでビタミンDの合成量は減少します。こうした方は食品からもしっかりとビタミンDを摂取することが重要になります。
 | まとめ | ||
ビタミンDは含まれている食品群と含まれていない食品群がはっきりとわかれるビタミンです。卵類やきのこ類、肉類の一部にはよく含まれていて、中でも魚類には全般に大変多く含まれています。一方で穀類、いも類、豆類、種実類、野菜類、果実類、藻類、貝類などにはほとんど含まれていません。魚類全般に多く含まれていることから魚類をしっかりと取っていれば、ビタミンDが不足することはほぼないでしょう。
ビタミンDを特にとりやすい食品
| 食品名 | 含有量(mg/100g) | 食品目安量(可食部) | 目安量(可食部)中の成分含有量 |
| あんこう・きも | 110μg | ぶつ切り1切れ50g | 55μg |
| かわはぎ | 43μg | 1尾200g(70g) | 30μg |
| しろさけ(焼き) | 39.4μg | 1切れ59g | 23.2μg |
| くろかじき | 38μg | 1切れ100g | 38μg |
| からすみ | 33μg | 1腹140g | 46μg |
| べにざけ(焼き) | 38.4μg | 1切れ80g | 30.7μg |
| からふとます(焼き) | 31.2μg | 1切れ75g | 23.4μg |
| ぎんざけ(焼き) | 21.0μg | 1切れ78g | 16.3μg |
| にしん | 22μg | 1尾200g(110g) | 24μg |
| まがれい(焼き) | 17.5μg | 1尾200g(130g) | 22.8μg |
| さんま(焼き) | 13.0μg | 1尾120g(84g) | 10.9μg |
| うなぎ | 18μg | 1尾200g(150g) | 27μg |
| いさき | 15μg | 1尾200g(110g) | 17μg |
| こい | 14μg | 輪1切れ150g(128g) | 18μg |
| たちうお | 14μg | 1切れ100g | 14μg |
| まかじき | 12μg | 1切れ100g | 12μg |
| すっぽん | 3.6μg | 1/2匹280g(280g) | 11μg |
| あらげきくらげ(ゆで) | 25.3μg | 1個34g | 8.6μg |
|
参考文献
7訂食品成分表2016 五訂完全版 ひと目でわかる日常食品成分表 日本人の食事摂取基準〈2015年版〉 日本人の食事摂取基準(2020年版) オールガイド食品成分表2017 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
|
最終更新日 2021/03/26 |
脂溶性ビタミンの多い食品・食べ物一覧
 |
ビタミンAの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンEの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
 |
ビタミンKの多い食品・食べ物と含有量一覧 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
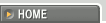
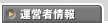
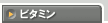
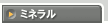
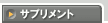
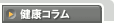



 脂溶性ビタミン
脂溶性ビタミン
