 |

|
|
ビタミンCの構造と種類(アスコルビン酸)
 | 還元性(抗酸化性)が特徴 | ||
ビタミンCの化学名はL-アスコルビン酸(ascorbic acid)です。強い還元性(抗酸化性)を有していて、その還元性はエンジオール基という部分が担っています。酸化と還元は同時に起こるもので(酸化還元反応)、体内でビタミンCは対象物質を還元する一方でビタミンC自体は酸化させられます。そのためビタミンCは体内では還元剤として働きます。血管中では還元型のアスコルビン酸として存在し、対象の物質を還元して自身はデヒドロアスコルビン酸(酸化型)になります。
デヒドロアスコルビン酸は同じく抗酸化物質であるたんぱく質のグルタチオンによって還元されアスコルビン酸に戻ります。デヒドロアスコルビン酸は容易に加水分解されビタミンC活性のない2,3-ジケトグロン酸に変化します。今回取り上げた酸化と還元についてですが、よくわからないという方は酸化・還元についてで詳しく解説しているので参考にしてください。
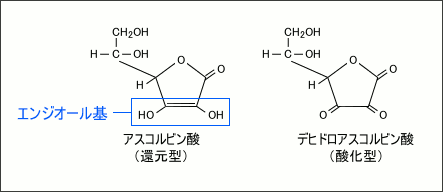
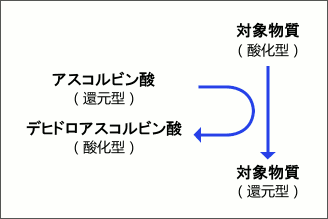
| 酸素 | 水素 | 電子 | |
| 酸化 | 酸素を与える | 水素を奪う | 奪う |
| 還元 | 酸素を奪う | 水素を与える | 与える |
デヒドロアスコルビン酸は同じく抗酸化物質であるたんぱく質のグルタチオンによって還元されアスコルビン酸に戻ります。デヒドロアスコルビン酸は容易に加水分解されビタミンC活性のない2,3-ジケトグロン酸に変化します。今回取り上げた酸化と還元についてですが、よくわからないという方は酸化・還元についてで詳しく解説しているので参考にしてください。
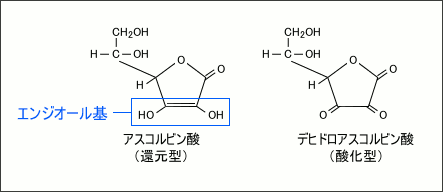
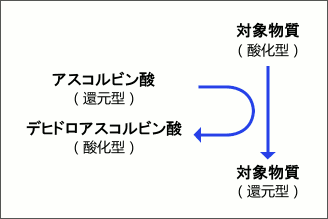
 | 抗酸化物質として活性酸素を還元する | ||
ビタミンCは水溶性で細胞質や血液の水層で、活性酸素などを還元する働きがあります。活性酸素本来細菌やウイルスを攻撃するために必要なものですが、この量が増えすぎると正常な細胞まで攻撃するため、ビタミンCのような抗酸化物質が必要となります。ビタミンCはその還元力により、活性酸素を還元してその働きを抑えます。
 | ビタミンCの還元力でビタミンEの再活性化 | ||
細胞膜の酸化が連鎖していく
同じ抗酸化物質であるビタミンEは脂溶性で、こちらは不飽和脂肪酸で構成される細胞膜中で抗酸化力を発揮します。不飽和脂肪酸は活性酸素により酸化されると脂質ラジカルとなり、さらに酸化されると脂質ペルオキシラジカルとなります。この脂質ペルオキシラジカルは別の不飽和脂肪酸を酸化して脂質ラジカルを作り、不飽和脂肪酸の酸化がドンドンと進んでしまいます。
ビタミンEの還元力で酸化の連鎖を止める
ビタミンEはその還元力により脂質ペルオキシラジカルを還元して安定生成物へとかえ、ビタミンE自体は還元されビタミンEラジカルとなります。ビタミンEラジカル自体は非常に安定しているので、そこで酸化の連鎖が抑えられます。
ビタミンCがビタミンEを還元して再活性化
ビタミンCは還元力で、酸化したビタミンEラジカルを再びビタミンEへと戻し、活性化させる働きがあります。ビタミンC自体もアミノ酸化合物であるグルタチオンによって還元され、再び活性を取り戻すことができます。この関係を図にすると以下のようになります。
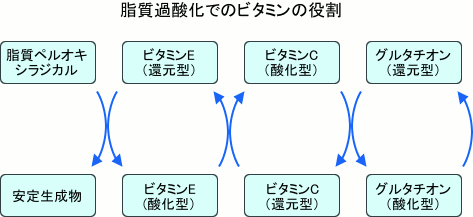
 | 酸化されやすい | ||
酸素や熱、金属イオンなどにより酸化が促進
ビタミンCは水溶性で、水に溶かすと酸性をしめします。水溶液中のビタミンCは溶存する酸素により容易に酸化され、微量の金属イオン(CU2+など)が存在すると、酸化は著しく促進されます。ドリンク類の製造に際しては、酸素を除去しているので1年間は安定です。乾燥状態にある錠剤などのビタミンCは3年間は安定です。熱やアルカリ性では非常に不安定で分解されやすいです。
低温で高湿度の環境なら損失も少ない
逆にビタミンCは低温で湿度が高く、酸素が少なく酸性度の強い環境ほど安定して分解も少なくなります。例えばグリーンピースは室温だと1日12%のビタミンCが失われますが、冷蔵庫内なら4%にとどまります。
 | 体内で合成できない | ||
多くの動植物では生体内でグルコースからアスコルビン酸を合成することが出来ますが、ヒトやサル、モルモットではこの代謝過程で必要となる酵素(L-グロノラクトンオキシターゼ)が遺伝的に欠如しているので合成することが出来ません。
|
参考文献
サプリメントデータブック よくわかる栄養学の基本としくみ 基礎栄養学 基礎栄養学 健康・栄養科学シリーズ 基礎栄養学 (スタンダード栄養・食物シリーズ)第3版 栄養・健康化学シリーズ 生化学 ポケットアトラス栄養学 |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
| 最終更新日 2019/01/16 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
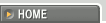
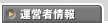
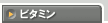
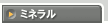
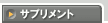
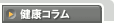



 水溶性ビタミン
水溶性ビタミン
