 |

|
|
ビタミンB2の効果・効能
| |
 | ビタミンB2の種類 | ||
ビタミンB2は別名リボフラビンとも呼ばれ、狭義ではこのリボフラビンがビタミンB2となります。広義ではリボフラビンにリン酸が結合したフラビンモノヌクレオチド(FMN)やアデノシン二リン酸(ADP)が結合したフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)もビタミンB2に含まれます。食品中に含まれるビタミンB2の多くはこのFMNとFADです。生体内でもFMN、FADとして存在し、様々生理反応に関わります。
 | 皮膚・粘膜を正常に保つ | ||
ビタミンB2には皮膚や各器官の粘膜を正常に保つ働きがあります。不足すると油っぽい肌や脂漏性皮膚炎などの症状が現れ、さらに進行すると舌炎や口唇炎、眼精疲労や白内障などに至ることもあります。
 | エネルギー代謝に関与 | ||
ビタミンB2はエネルギー生産に使われる炭水化物、タンパク質、脂質全ての代謝に関係します。具体的には代謝過程で必要な酵素(酸化還元酵素、脱水素酵素)の補酵素として補助的に関わることで円滑なエネルギー代謝を支えています。
下の図はエネルギー代謝の図です。摂取した炭水化物、たんぱく質、脂質は体内で様々な化学変化をへたのちエネルギーとして利用されます。この図でビタミンB12がかかわるのは脂肪酸からアセチルCoAへの変化、アラニンからピルビン酸への変化、ピルビン酸からアセチルCoAへの変化、グルタミン酸からα-ケトグルタミン酸への変化です。
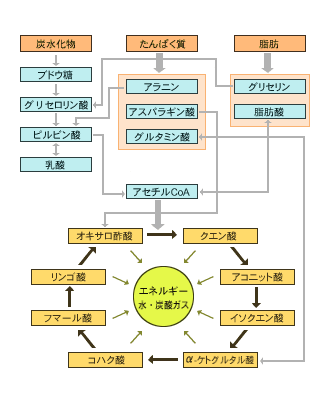
酸化還元酵素や脱水素酵素とは反応別に分類した酵素の種類のことで詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
※詳細 >>疲労とビタミン、エネルギー代謝とビタミン
>>酵素について2
下の図はエネルギー代謝の図です。摂取した炭水化物、たんぱく質、脂質は体内で様々な化学変化をへたのちエネルギーとして利用されます。この図でビタミンB12がかかわるのは脂肪酸からアセチルCoAへの変化、アラニンからピルビン酸への変化、ピルビン酸からアセチルCoAへの変化、グルタミン酸からα-ケトグルタミン酸への変化です。
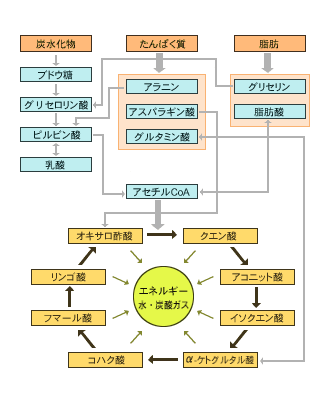
酸化還元酵素や脱水素酵素とは反応別に分類した酵素の種類のことで詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
※詳細 >>疲労とビタミン、エネルギー代謝とビタミン
>>酵素について2
 | ATP生産とビタミンB2 | ||
ビタミンB2とエネルギー生産についてもう少し詳しく見て行きます。糖質や脂質、たんぱく質は体内でエネルギー源として利用されますが、そのままではエネルギーとして使えません。そのため様々な代謝過程を経てエネルギーを取り出し、ATP(アデノシン3リン酸)として体内で使える形にしなければなりません。
ATPの生成では解糖系やクエン酸回路、脂肪酸のβ-酸化などの過程でまず脱水素酵素の働きにより高エネルギーを含んだ水素が取り出されます。この水素はビタミンB2であるFADと同じくビタミンのナイアシン(NAD:ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド)が受け取り、それぞれFADH2、NADHとなって電子伝達系と呼ばれる部位まで運ばれます。
電子伝達系は細胞内のミトコンドリアの内膜にあり、ここでまずFADH2はFADと2H+、2つの電子に変化し、NADHはNAD+とH+と2つの電子に分かれます。この電子が電子伝達系ないの3つの複合体を経由する際に電子から段階的にエネルギーが消費され、ADP(アデノシン2リン酸)とリン酸からATPが生成されます。FADH2からは2つのATPが、NADHからは3つのATPが生成されます。電子は電子伝達系を経由し最後は酸素(02)へと渡され、電子を受け取ったO2は水素(H+)と結合して水(H20)となります。
このようにビタミンB2はエネルギー源であるATP生産において水素を受け取り電子伝達系まで送るという非常に重要な役割を担っているのです。
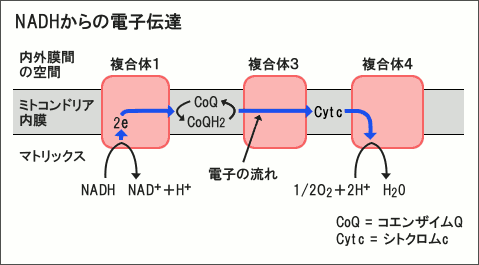
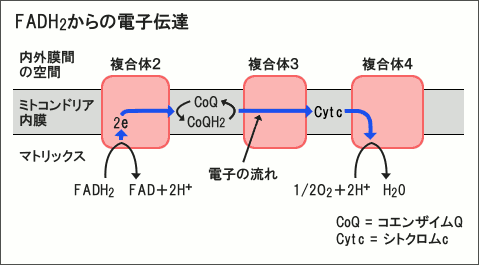
ATPの生成では解糖系やクエン酸回路、脂肪酸のβ-酸化などの過程でまず脱水素酵素の働きにより高エネルギーを含んだ水素が取り出されます。この水素はビタミンB2であるFADと同じくビタミンのナイアシン(NAD:ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド)が受け取り、それぞれFADH2、NADHとなって電子伝達系と呼ばれる部位まで運ばれます。
電子伝達系は細胞内のミトコンドリアの内膜にあり、ここでまずFADH2はFADと2H+、2つの電子に変化し、NADHはNAD+とH+と2つの電子に分かれます。この電子が電子伝達系ないの3つの複合体を経由する際に電子から段階的にエネルギーが消費され、ADP(アデノシン2リン酸)とリン酸からATPが生成されます。FADH2からは2つのATPが、NADHからは3つのATPが生成されます。電子は電子伝達系を経由し最後は酸素(02)へと渡され、電子を受け取ったO2は水素(H+)と結合して水(H20)となります。
このようにビタミンB2はエネルギー源であるATP生産において水素を受け取り電子伝達系まで送るという非常に重要な役割を担っているのです。
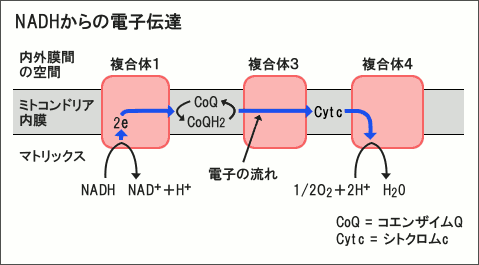
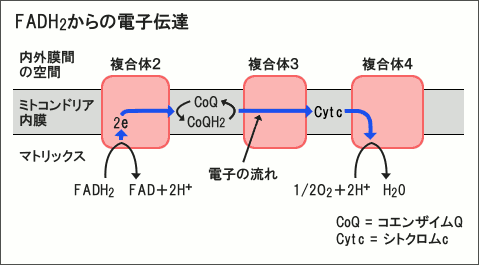
 | 成長の促進に関与 | ||
ビタミンB2は成長に必要なエネルギーの代謝に関わっているため、正常な成長の促進には欠かせない栄養素の1つです。成長期の子供や妊婦は特に十分な摂取がもとめられます。
 | 過酸化脂質の分解に関与 | ||
ビタミンB2は過酸化脂質を分解するグルタチオンやグルタチオンペルオキシターゼの働きを助ける酵素であるグルタチオン還元酵素の補酵素として過酸化脂質の分解に関わります。過酸化脂質とは細胞膜内の不飽和脂肪酸が活性酸素により酸化して出来るもので、これにより細胞膜は傷つけられ、さらに隣り合う細胞膜へと連鎖的に酸化が続いていきます。過酸化脂質は動脈硬化や心筋梗塞などの原因のひとつとしても問題視されている物質です。
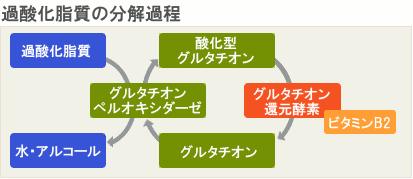
※詳細 >>酵素について
>>脂質について
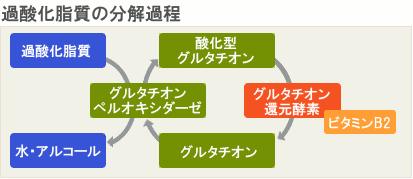
※詳細 >>酵素について
>>脂質について
 | 他のビタミンの生合成に関与 | ||
ビタミンB2はビタミンB6の補酵素型や葉酸の補酵素型、ナイアシンの生合成に必要です。
 | ビタミンB2が多く含まれる食品 | ||
ビタミンB2には上記のように様々な働きや効果、効能がありますが、こうしたビタミンB2を効率的に摂るには多く含まれる食品を知っておくことも重要です。ビタミンB2が肉類や魚類などに多く含まれます。肉類では特にレバーに多く含まれますが、豚や鶏のレバーは取りすぎによるビタミンA過剰症の心配があるので、摂るなら牛レバーがいいでしょう。魚類ではキャビアやからすみ、たらこやイクラなど、卵や卵巣を使った食品に多く含まれます。他にもどじょうやウナギ、ズワイガニや魚肉ソーセージなどにも多く含まれます。ビタミンB2の多い食品についてはビタミンB2の多い食品・食べ物と含有量一覧でも詳しく解説しています。
 | ビタミンB2の成人推奨量 | ||
ビタミンB2の1日の推奨量は成人男子で1.6mg、成人女子で1.2mgです。
 ビタミンB2の年代別食事摂取基準
ビタミンB2の年代別食事摂取基準
| 年齢 | 男性(mg) | 女性(mg) | ||||||
|
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
| 0〜5 (月) | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - |
| 6〜11 (月) | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | - |
| 1〜2 | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 3〜5 | 0.7 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.8 | - | - |
| 6〜7 | 0.8 | 0.9 | - | - | 0.7 | 0.9 | - | - |
| 8〜9 | 0.9 | 1.1 | - | - | 0.9 | 1.0 | - | - |
| 10〜11 | 1.1 | 1.4 | - | - | 1.0 | 1.3 | - | - |
| 12〜14 | 1.3 | 1.6 | - | - | 1.2 | 1.4 | - | - |
| 15〜17 | 1.4 | 1.7 | - | - | 1.2 | 1.4 | - | - |
| 18〜29 | 1.3 | 1.6 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
| 30〜49 | 1.3 | 1.6 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
| 50〜64 | 1.2 | 1.5 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
| 65〜74 | 1.2 | 1.5 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
| 75以上 | 1.1 | 1.3 | - | - | 0.9 | 1.0 | - | - |
| 妊婦(付加量) | +0.2 | +0.3 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +0.5 | +0.6 | - | - | ||||
※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2020年版)
各指標の見方について
|
参考文献
わかりやすいからだとビタミンの知識 医療従事者のための機能性食品ガイド 日本人の栄養所要量―食事摂取基準 サプリメントデータブック エキスパートのためのビタミン・サプリメント 専門医が教えるビタミン・ミネラル早わかり ビタミン・ミネラルBOOK 基礎栄養学第3版 栄養科学シリーズNEXT生化学 わかりやすい生化学 栄養・健康科学シリーズ生化学 日本人の食事摂取基準(2020年版) |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
|
最終更新日 2021/03/26 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
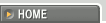
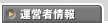
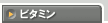
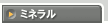
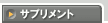
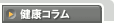



 水溶性ビタミン
水溶性ビタミン
