 |

|
|
ビタミンAの効果・効能、レチノール、β-カロテンとは | |
 | ビタミンAとは | ||
ビタミンAにはA1とA2の2種類があり、A1にはレチノール、レチナール、レチノイン酸が、A2にはA1の類縁化合物である3-デヒドロレチノール、3-デヒドロレチナール、3-デヒドロレチノイン酸があります。A1、A2を総称してビタミンAといいます。動物性食品に含まれるビタミンAは脂肪酸(主にパルミチン酸)と結合したレチニルエステルで、これが小腸吸収上皮細胞の酵素の働きにより、レチノールに変換されて細胞内に取り込まれます。レチノールは体内では化学変化でレチナールやレチノイン酸へと変化します。レチナールは視紫紅(ロドプシン)の構成成分として視覚作用と関わり、また粘膜や上皮細胞の機能の維持にも関わっています。レチノイン酸は発ガン抑制作用や胚発生の形態形成作用があることが明らかになっています。
|
ビ タ ミ ン A | A1 | レチノール(アルコール型) |
| レチナール(アルデヒド型) | ||
| レチノイン酸(カルボン酸型) | ||
| A2 | 3-デヒドロレチノール | |
| 3-デヒドロレチナール | ||
| 3-デヒドロレチノイン酸 |
 | カロテノイド | ||
分子内にレチノールを含む
カロテノイドとは色素の一種で植物性食品に含まれるもので、その数は約600種類にもなります。カロテノイドの中でもβ-カロテン、α-カロテン、γ-カロテンは分子内にビタミンA(レチノール)が含まれていて、体内でビタミンAに変換されることからプロビタミンAと呼ばれます。その中でもβ-カロテンは分子内に2個のレチノールが含まれている事からもっとも高いビタミンA活性があるのが特徴です。食品中にもβ-カロテンは最も多く含まれています。
ビタミンA過剰症の心配はない
ビタミンAは脂溶性ビタミンなので取りすぎると過剰症の心配が出てきますが、β-カロテンは体内で必要量のみビタミンAへと変換されるのでビタミンA過剰症の心配はありません。β-カロテンを過剰に摂取してもよほど大量に摂取した場合においても手のひらや足の裏が黄色に変色することがある程度なので過剰症の心配はほとんどないでしょう。またβ-カロテンにはビタミンAとは異なる独自の生理活性があることもわかっています。
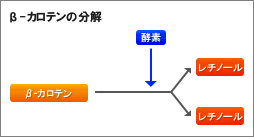
 | ビタミンAの発見の歴史 | ||
ホプキンスがビタミンを発見
ビタミンAの発見は1906年にイギリスのホプキンスがたんぱく質、脂質、糖質、無機質(ミネラル)の混合飼料でシロネズミを飼育してもうまく発育せず、牛乳を加えるとしっかりと成長したことから、牛乳には未知の成長促進因子が含まれていると示唆したことが始まりで、これが後にビタミンAだと判明します。1915年にマッカラムはこの未知の成長促進因子には、バターや卵黄に含まれるものと、粗製乳糖中に含まれるものがあることを発見し、前者が油に溶けることから脂溶性Aと、後者は水に溶けることから水溶性Bと命名します。
ドラモンドがビタミンAと命名
1920年にはドラモンドにより脂溶性AはビタミンAと水溶性BはビタミンBと命名されます。ビタミンAにはA1とA2の2種類があることは上でも説明しましたが、まずはレチノールがドイツのカラーにより1931年にその構造が決定され、1934年にはワルドが動物の網膜よりレチナールの単離に成功しました。その後レチノイン酸や3-デヒドロ類似体も発見されます。
ビタミンAの欠乏症では1913年にオズボーンとメンデルによりラットの発育障害と目の感染症状が報告され、1917年にはマッカラムにより眼感染症、角膜乾燥症、眼水腫が報告されています。
カロテノイドは1831年に発見
ビタミンAは体内でカロテノイドの一部からも合成されますが、カロテノイドが発見されたのは1831年で、1930年にβ-カロテンが体内でビタミンAに合成されることがアメリカのモーアらによって発見されました。詳しくはビタミンA発見の歴史で解説しています。
 | 目の明暗の感受性を維持する | ||
目の網膜の視細胞には、明暗を感知する杆体(かんたい)細胞と色彩を感知する錐体(すいたい)細胞があります。杆体細胞には光受容体であるロドプシンが含まれていて、その中にレチナールが構成成分として存在します。ロドプシンの中のレチナールは光を受けると化学変化を起こし、さえぎられるともとに戻るという性質があるため、この刺激により明暗の識別が行われます。レチナールが不足するとあたりが薄暗くみえる夜盲症や、急に暗い場所に入ったときになかなか目がなれない暗順応遅延と言った症状がでてきます。
錐体細胞にも光の三原色の受容体であるアイオドプシンというたんぱく質がありその構成成分として同じくレチナールが存在します。感知機構もロドプシンと似たようなものだと考えられています。
錐体細胞にも光の三原色の受容体であるアイオドプシンというたんぱく質がありその構成成分として同じくレチナールが存在します。感知機構もロドプシンと似たようなものだと考えられています。
 | 遺伝子発現の調節 | ||
ビタミンAには上皮細胞の機能維持や成長促進、発ガン抑制作用、免疫機能、味覚機能など様々な生理作用があることがわかっていますが、どのように関与しているのかはこれまでよくわかっていませんでした。しかしながら近年以下の機構が関係している事がわかってきました。
細胞の核内にはビタミンA受容体(レセプター)であるRAR(レチノイン酸受容体)とRXR(レチノイン酸X受容体)があり、ビタミンAとレセプターが結合する事で遺伝子の発現・制御が行われています。上記の生理作用もこのようなビタミンAによる遺伝子の発現・制御機構により実現されています。他にもビタミンD受容体や甲状腺ホルモン受容体などが核内にはあり、ビタミンA受容体はそれらとも相互に影響し合って様々な生理作用に関係していますが、その生理作用については非常に複雑なためすべての機構の解明には至っていません。
細胞の核内にはビタミンA受容体(レセプター)であるRAR(レチノイン酸受容体)とRXR(レチノイン酸X受容体)があり、ビタミンAとレセプターが結合する事で遺伝子の発現・制御が行われています。上記の生理作用もこのようなビタミンAによる遺伝子の発現・制御機構により実現されています。他にもビタミンD受容体や甲状腺ホルモン受容体などが核内にはあり、ビタミンA受容体はそれらとも相互に影響し合って様々な生理作用に関係していますが、その生理作用については非常に複雑なためすべての機構の解明には至っていません。
 | 皮膚や粘膜を正常に保つ | ||
上記でも述べた通りビタミンAは皮膚や口・鼻・のど・肺・胃・腸などの粘膜の健康維持にはか欠かせません。皮膚や粘膜は上皮細胞といい、傷や感染症から身体を守ってくれる働きがあります。また肌の潤いを保ち乾燥から身を守る働きもあります。かさかさ肌の人はビタミンAの不足が原因かもしれません。
 | ガンの抑制 | ||
アポトーシスの促進でがんを抑制
ガンとは細胞が異常増殖する事がひとつの特徴ですが、これはアポトーシス不全を起こした状態だともいえます。アポトーシスとは細胞をより良い状態に保つために、管理・調節された細胞自身の死のプログラムすなわち自殺の事で、これにより細胞が異常増殖する事を防いでいます。ガンがアポトーシスの機能不全であるなら、アポトーシスを誘導する物質であるレチノイドの存在がガンの抑制に有効ではないかという事が注目され様々な研究も行われており、実際その効果もいくつかの研究結果により実証されています。
分化の促進でがんを抑制
ビタミンAは細胞の成長と臓器への分化にもかかわっています。分化とはある細胞が構造機能的に変化することです。例えば卵細胞は細胞分裂により様々な組織へと別れ、各種臓器が作られていきますが、こうした過程を分化といいます。がん細胞には分化したものと未分化のものがあります。がん細胞は完全に分化するとそこで増殖は止まります。ビタミンAは細胞の分化を促進する働きがあるのである種の悪性腫瘍の治療薬にも用いられています。
例えば前骨髄性白血病でレチノイン酸の投与により完全完解したケースやがん治療をほどこした肝癌患者への合成レチノイドの投与で再発率の著しい低下が見られたといった事例などの報告があります。
 | β-カロテンの抗酸化作用 | ||
プロビタミンAであるβ-カロテンばかりが注目されがちなカロテノイドですが、α-カロテンやリコピン、ルテインをはじめとしたその他のカロテノイドにも重要な働きがあります。約600種類にもなるカロテノイドですがこれらには優れた抗酸化作用が認められ、さらにカロテノイドの種類によって抗酸化作用も異なり、対応する活性酸素も異なることがわかってきました。したがって抗酸化作用をしっかりと働かせるためにはβ-カロテンだけでなくカロテノイドをまんべんなく摂取することが大切となります。ちなみにリコピンやルテインは体内でレチノールにはならずそのまま利用されます。
カロテノイドの抗酸化作用には紫外線の照射によって体内の酸素と反応して発生する活性酸素である一重項酸素の消去とフリーラジカルの補足による酸化の進行防止の2つがあげられます。
カロテノイドの抗酸化作用には紫外線の照射によって体内の酸素と反応して発生する活性酸素である一重項酸素の消去とフリーラジカルの補足による酸化の進行防止の2つがあげられます。
| ※関連コラム |
>>老化の原因、活性酸素とは |
 | β-カロテン動脈硬化予防 | ||
動脈硬化は血管を通ってコレステロールを細胞まで運ぶLDL(悪玉コレステロール)が活性酸素により酸化され酸化LDLへと変化し、それが血管内に付着することが発症原因の1つといわれています。β-カロテンがもつ優れた抗酸化作用はLDLの酸化を抑えることで動脈硬化を予防する働きがあるのです。動脈硬化は心疾患や脳血管疾患の原因ともなりますのでβ-カロテンはこれら疾患の予防にも効果を発揮することが期待されます。
| ※関連コラム |
>>老化の原因、活性酸素とは |
 | カロテノイドの発ガン抑制作用 | ||
β-カロテンをはじめとしたカロテノイドですがその発ガン抑制効果にも注目が集まっています。例えばカロテノイドを豊富に含む緑黄色野菜を摂取しているグループにガンの発生率が低いという疫学調査での研究結果が報告されています。またα-カロテンには肺がんの抑制効果が、β-カロテンには脾臓ガンの抑制効果が、リコピンには肝臓ガンや乳腺ガンの抑制効果がみられるといった研究報告もあり、カロテノイドの種類によっても抑制効果のあるガンの種類が異なるという事も明らかになってきています。
 | ビタミンAの成人推奨量 | ||
|
ビタミンAの成分レチノールは動物性食品からしか摂取できません。ただし植物性食品に含まれるカロテンという成分は体内でレチノールへと変換されるので、植物性食品からもビタミンAを補給することは可能です。カロテンは腸での吸収が1/6、そこからのレチノール変換が1/2といわれているのでカロテンのレチノールとしての利用量は、摂取分の1/12程度だとされています。 通常必要量として表記されているレチノール活性当量(RAE:retinol activity equivalents)という指数は、レチノールの量と、カロテンのレチノール換算量の合計の数値です。ビタミンAの1日の推奨量は成人男性で850μgRAE、成人女性で650μgRAEです。 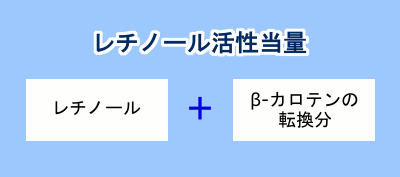
|
 ビタミンAの年代別食事摂取基準
ビタミンAの年代別食事摂取基準
| 年齢 | 男性(μgRAE) | 女性(μgRAE) | ||||||
|
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
| 0〜5 (月) | - | - | 300 | 600 | - | - | 300 | 600 |
| 6〜11 (月) | - | - | 400 | 600 | - | - | 400 | 600 |
| 1〜2 | 300 | 400 | - | 600 | 250 | 350 | - | 600 |
| 3〜5 | 350 | 450 | - | 700 | 350 | 500 | - | 850 |
| 6〜7 | 300 | 400 | - | 950 | 300 | 400 | - | 1200 |
| 8〜9 | 350 | 500 | - | 1200 | 350 | 500 | - | 1500 |
| 10〜11 | 450 | 600 | - | 1500 | 400 | 600 | - | 1900 |
| 12〜14 | 550 | 800 | - | 2100 | 500 | 700 | - | 2500 |
| 15〜17 | 650 | 900 | - | 2500 | 500 | 650 | - | 2800 |
| 18〜29 | 600 | 850 | - | 2700 | 450 | 650 | - | 2700 |
| 30〜49 | 650 | 900 | - | 2700 | 500 | 700 | - | 2700 |
| 50〜64 | 650 | 900 | - | 2700 | 500 | 700 | - | 2700 |
| 65〜74 | 600 | 850 | - | 2700 | 500 | 700 | - | 2700 |
| 75以上 | 550 | 800 | - | 2700 | 450 | 650 | - | 2700 |
| 妊婦(初期) | +0 | +0 | - | - | ||||
| 妊婦(中期) | +0 | +0 | - | - | ||||
| 妊婦(後期) | +60 | +80 | - | - | ||||
| 授乳婦 | +300 | +450 | - | - | ||||
※RAE レチノール活性当量
※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2020年版)
各指標の見方について
 | ビタミンAの多い食品 | ||
レチノールが多く含まれる食品
ではビタミンAが多く含まれている食品にはどのようなものがあるのでしょうか。ビタミンAは動物性食品ならレチノールとして、植物性食品ならβ-カロテンとして含まれています。まずはレチノールから見て行くと鶏、豚、牛などの肝臓に多く含まれています。このうち鶏と豚は含まれるレチノールの量が非常に多すぎるため少量の摂取にしないと過剰症の心配が出てきます。うなぎやぎんだら、ホタルイカやアナゴといった食品にもレチノールは多く含まれます。

β-カロテンの多い食品
β-カロテンや緑黄色野菜に多く含まれます。そもそもβ-カロテンが多い食品を緑黄色野菜といいます。緑黄色野菜ではにんじんやホウレン草、春菊やモロヘイヤ、かぼちゃや大根の葉、あしたばやルッコラなどにたくさんのβ-カロテンが含まれます。他にもほしのりや岩のり、抹茶などにもβ-カロテンは多く含まれます。詳しくはビタミンAの多い食品・食べ物と含有量一覧で解説しています。

|
参考文献
医療従事者のための機能性食品 わかりやすいからだとビタミンの知識 「ビタミン伝説」の真実 基礎栄養学 健康・栄養科学シリーズ サプリメントデータブック ビタミン・ミネラルBOOK―ストレス解消!体に効く! エキスパートのためのビタミン・サプリメント 基礎栄養学 基礎栄養学 スタンダード栄養・食物シリーズ ビタミン・ミネラルの本 よくわかる栄養学の基本としくみ 日本人の食事摂取基準2015年版 日本人の食事摂取基準(2020年版) |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
|
最終更新日 2021/03/26 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
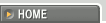
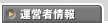
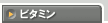
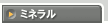
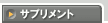
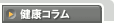



 脂溶性ビタミン
脂溶性ビタミン
