 |

|
|
ビタミンDの効果・効能

 | ビタミンDの種類 | ||
ビタミンDには動物起源のビタミンD3と植物起源のビタミンD2があります。
ビタミンD3はコレステロールが生合成される際の代謝産物である7-デヒドロコレステロール(コレステロールの1段階前の代謝物)に紫外線が照射されることで起る光化学反応と、その後の体温によって起る熱異性化反応によって作られます。この反応は動物の皮膚表面で進行すると考えられています。
ビタミンD2は植物ステロールであるエルゴステロールが植物体のなかで紫外線照射を受けることで光化学反応を起こして作られます。7-デヒドロコレステロールはプロビタミンD3と呼ばれますが、エルゴステロールをプロビタミンD2と呼ぶのは正しくはありません。プロビタミンとは本来体内でビタミンに変化する物質のことです。エルゴステロールは植物体の中で化学変化を起こすので、プロビタミンD2ではなくたんなる前駆体と呼ぶ方が正確です。
供給源としては体外から摂取するビタミンD2とビタミンD3、体内で合成するビタミンD3の3パターンある事になります。人の体内においてはビタミンD2、ビタミンD3ともに同等の生理活性を示します。
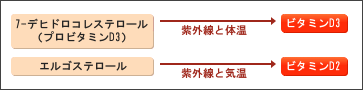
ビタミンD2は植物ステロールであるエルゴステロールが植物体のなかで紫外線照射を受けることで光化学反応を起こして作られます。7-デヒドロコレステロールはプロビタミンD3と呼ばれますが、エルゴステロールをプロビタミンD2と呼ぶのは正しくはありません。プロビタミンとは本来体内でビタミンに変化する物質のことです。エルゴステロールは植物体の中で化学変化を起こすので、プロビタミンD2ではなくたんなる前駆体と呼ぶ方が正確です。
供給源としては体外から摂取するビタミンD2とビタミンD3、体内で合成するビタミンD3の3パターンある事になります。人の体内においてはビタミンD2、ビタミンD3ともに同等の生理活性を示します。
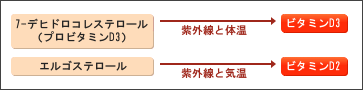
| ※関連コラム |
>>誘導脂質について2(ステロイド) |
 | 活性型ビタミンD | ||
3パターンの経路で供給されたビタミンDはビタミンD結合たんぱく質(DBP:vitamin D-binding protein)と結合し血流に乗って肝臓まで運ばれ、肝臓で25-ヒドロキシビタミンDに代謝されます。25-ヒドロキシビタミンDはDBPと結合して腎臓まで運ばれ、血中カルシウム濃度が低い場合には副甲状腺ホルモンの刺激により、腎臓で1α,25-ジヒドロキシビタミンDへと代謝されます。これを活性型ビタミンDと呼びます。血中カルシウム濃度が正常もしくは高い場合は、非活性型の24,25-ジヒドロキシビタミンDへと代謝されます。非活性型は生理活性をほとんど持たない不活性代謝物です。
活性型ビタミンDは小腸でのカルシウムの吸収の促進や腎臓でのカルシウムの再吸収、他のカルシウム関連ホルモン(副甲状腺ホルモン、カルシトニン)と協力して血中のカルシウム濃度を一定に保つなどの働きをしています。
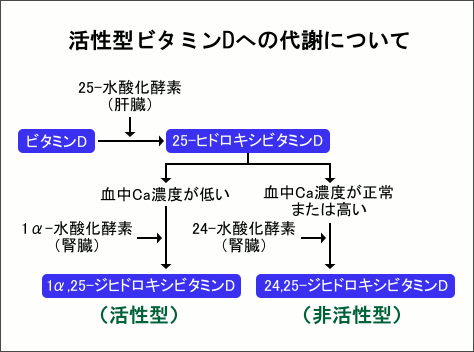
活性型ビタミンDは小腸でのカルシウムの吸収の促進や腎臓でのカルシウムの再吸収、他のカルシウム関連ホルモン(副甲状腺ホルモン、カルシトニン)と協力して血中のカルシウム濃度を一定に保つなどの働きをしています。
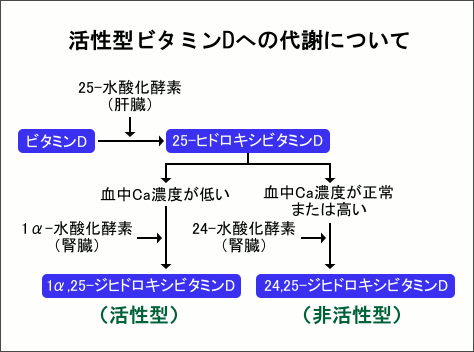
 | 遺伝子の発現の制御 | ||
ビタミンAの所でも記述しましたがビタミンDも遺伝子の発現の制御に深く関わっています。活性型ビタミンDは標的細胞の核内に存在するビタミンD受容体(VDR:vitamin D receptor)と結合し、さらにレチノイドX受容体(RXR:retinoid X receptor)と結合して異種二量体を形成します。異種二量体とは異なる分子が結合したものです。この異種二量体が遺伝子の発現を促進させます。ビタミンDの生理作用の多くもこの遺伝子の発現によって実現しています。
ビタミンDによって遺伝子の発現が促進されるたんぱく質には硬組織(骨や歯など)に存在するオステオポンチンやオステオカルシン、小腸や腎臓でカルシウムの吸収に関与するカルビンデインD、そのほかビタミンD24位水酸化酵素などがあります。
ビタミンDによって遺伝子の発現が促進されるたんぱく質には硬組織(骨や歯など)に存在するオステオポンチンやオステオカルシン、小腸や腎臓でカルシウムの吸収に関与するカルビンデインD、そのほかビタミンD24位水酸化酵素などがあります。
| ※関連コラム |
>>ビタミンAの効果・効能 |
 | 血中のカルシウム濃度の維持 | ||
血中カルシウム濃度が低い場合は副甲状腺ホルモン(PTH:parathyroid hormone)が分泌され腎臓で1α-水酸化酵素を活性化させます。1α-水酸化酵素はビタミンDを活性型ビタミンDへと代謝させます。活性型ビタミンDは小腸でのカルシウムの吸収促進作用、腎臓でのカルシウム再吸収促進作用、骨塩動員作用により血中カルシウム濃度を上昇させます。活性型ビタミンDは標的細胞で生理作用を発揮したあとは、主に24-水酸化酵素により生理活性をほとんど持たない不活性代謝物である24,25-ジヒドロキシビタミンDへと代謝され、尿中へ排泄されます。
血中カルシウム濃度が正常になるとカルシトニンによって1α-水酸化酵素の活性は抑えられ、ビタミンDを不活性型の24,25-ジヒドロキシビタミンD3に代謝する24-水酸化酵素の働きが活性化します。こうして血中カルシウム濃度の上昇が抑えられます。血中カルシウム濃度が高い場合も24-水酸化酵素の働きが活性化されます。このようにビタミンDは各種ホルモン(PTH、カルシトニン)と協力してカルシウム濃度が低い場合はカルシウム濃度を上昇させるよう働き、正常もしくは高い場合は不活性化して血中カルシウム濃度の上昇を抑制するよう働きます。その結果血中カルシウム濃度は一定に維持されます。
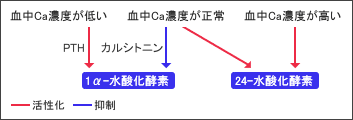
血中カルシウム濃度が正常になるとカルシトニンによって1α-水酸化酵素の活性は抑えられ、ビタミンDを不活性型の24,25-ジヒドロキシビタミンD3に代謝する24-水酸化酵素の働きが活性化します。こうして血中カルシウム濃度の上昇が抑えられます。血中カルシウム濃度が高い場合も24-水酸化酵素の働きが活性化されます。このようにビタミンDは各種ホルモン(PTH、カルシトニン)と協力してカルシウム濃度が低い場合はカルシウム濃度を上昇させるよう働き、正常もしくは高い場合は不活性化して血中カルシウム濃度の上昇を抑制するよう働きます。その結果血中カルシウム濃度は一定に維持されます。
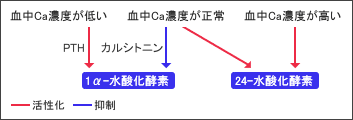
 | 骨の形成に関与 | ||
骨は骨芽細胞による骨組織の形成と破骨細胞による骨組織破壊(骨吸収)により一定の骨量が維持されています。活性型ビタミンDは破骨細胞の活性化による骨塩動因作用(骨吸収)の促進により骨の破壊に関与することで骨リモデリング(骨の破壊と再構築)を正常に維持するよう働きます。
ビタミンDは骨の主要成分であるカルシウムの吸収促進と骨リモデリングに必要な栄養素であるため、不足すると乳児・幼児・小児などの成長期においてくる病を引き起こします。くる病とは骨が軟化して脊椎や四肢骨の湾曲や変形がおこる病気です。骨格形成が完了した成人以降では骨軟化症を引き起こし、閉経後の女性や高齢者で、ビタミンD不足が長期間に渡ると骨粗鬆症のリスクが高まります。
ビタミンDは骨の主要成分であるカルシウムの吸収促進と骨リモデリングに必要な栄養素であるため、不足すると乳児・幼児・小児などの成長期においてくる病を引き起こします。くる病とは骨が軟化して脊椎や四肢骨の湾曲や変形がおこる病気です。骨格形成が完了した成人以降では骨軟化症を引き起こし、閉経後の女性や高齢者で、ビタミンD不足が長期間に渡ると骨粗鬆症のリスクが高まります。
 | 骨粗鬆症の治療に使われる | ||
骨粗鬆症の治療ではビタミンDが投与されることが有ります。ビタミンDは骨塩動因作用により骨から血管へのカルシウムの溶出を促進させる働きがあるので、ビタミンDを投与すると返って骨粗鬆症が悪化するのではないかと思う方もいるかもしれません。
しかしながらビタミンDにはこのほか小腸でのカルシウムの吸収促進や腎臓の尿細管でのカルシウムの再吸収を促進する働きがあるので、血中のカルシウム濃度の上昇に働きます。血中のカルシウム濃度が上がるとカルシトニンという甲状腺ホルモンが分泌されます。カルシトニンは小腸でのカルシウムの吸収を抑制する働きや、カルシウムの尿中への放出を促進する働きとともに、骨へのカルシウムの沈着を促進する働きが有ります。ビタミンD自身が骨からのカルシウムの溶出を促進する働きがあっても、ビタミンDの血中カルシウム濃度を上昇させる働きにより、カルシトニンを介して骨へのカルシウムを沈着させる働きもあるのです。カルシウムの溶出よりも沈着させる作用のほうが強いので結果として、ビタミンDの投与が骨へのカルシウムの沈着する方に向かいます。
しかしながらビタミンDにはこのほか小腸でのカルシウムの吸収促進や腎臓の尿細管でのカルシウムの再吸収を促進する働きがあるので、血中のカルシウム濃度の上昇に働きます。血中のカルシウム濃度が上がるとカルシトニンという甲状腺ホルモンが分泌されます。カルシトニンは小腸でのカルシウムの吸収を抑制する働きや、カルシウムの尿中への放出を促進する働きとともに、骨へのカルシウムの沈着を促進する働きが有ります。ビタミンD自身が骨からのカルシウムの溶出を促進する働きがあっても、ビタミンDの血中カルシウム濃度を上昇させる働きにより、カルシトニンを介して骨へのカルシウムを沈着させる働きもあるのです。カルシウムの溶出よりも沈着させる作用のほうが強いので結果として、ビタミンDの投与が骨へのカルシウムの沈着する方に向かいます。
 | 非カルシウム作用 | ||
これまで述べてきた小腸でのカルシウム吸収促進や腎臓でのカルシウム再吸収の促進、骨塩動因作用をまとめてビタミンDのカルシウム作用といいます。ビタミンDにはこれ以外にも非カルシウム作用と呼ばれる生理作用もあります。非カルシウム作用にはがん細胞、および正常細胞の増殖抑制・分化誘導作用、副甲状腺ホルモン産生・分泌抑制作用、発毛調節作用、免疫調節作用などがあります。
■カルシウム作用
小腸カルシウム吸収促進
腎臓カルシウム再吸収促進
骨塩動因作用
■非カルシウム作用
がん細胞の増殖抑制・正常細胞への分化誘導作用
副甲状腺ホルモン産生・分泌抑制作用
発毛調節作用
免疫調節作用
■カルシウム作用
小腸カルシウム吸収促進
腎臓カルシウム再吸収促進
骨塩動因作用
■非カルシウム作用
がん細胞の増殖抑制・正常細胞への分化誘導作用
副甲状腺ホルモン産生・分泌抑制作用
発毛調節作用
免疫調節作用
 | がん細胞の増殖抑制・分化誘導 | ||
ビタミンDには非カルシウム作用としてがん細胞の増殖を抑制し、ガン化しかけた細胞を正常細胞へと分化誘導する働きが認められています。骨髄性白血病細胞への治療効果も確認されていて、ビタミンD摂取量と結腸癌などの悪性腫瘍発症率との間の負の相関関係も認められています。しかしながら悪性腫瘍の治療にビタミンDを用いると高カルシウム血症を引き起こすリスクが高くなるため、現在カルシウム作用と非カルシウム作用を構造的に分離したビタミンD誘導体の開発が進められているところです。
 | ビタミンDの成人目安量 | ||
ビタミンDは推定平均必要量や推奨量ではなく目安量が定められています。目安量とは推定平均必要量や推奨量を設定できない場合に代わりに設定されるものです。1日の目安量は年齢とともに増加していき、成人男女では8.5μgとなります。0〜11カ月の乳児のビタミンDの目安量が高く設定されていますが、これはくる病などの予防の観点からです。
 ビタミンDの年代別食事摂取基準
ビタミンDの年代別食事摂取基準
| 年齢 | 男性(μg) | 女性(μg) | ||||||
|
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |
推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
| 0〜5 (月) | - | - | 5.0 | 25 | - | - | 5.0 | 25 |
| 6〜11 (月) | - | - | 5.0 | 25 | - | - | 5.0 | 25 |
| 1〜2 | - | - | 3.0 | 20 | - | - | 3.5 | 20 |
| 3〜5 | - | - | 3.5 | 30 | - | - | 4.0 | 30 |
| 6〜7 | - | - | 4.5 | 30 | - | - | 5.0 | 30 |
| 8〜9 | - | - | 5.0 | 40 | - | - | 6.0 | 40 |
| 10〜11 | - | - | 6.5 | 60 | - | - | 8.0 | 60 |
| 12〜14 | - | - | 8.0 | 80 | - | - | 9.5 | 80 |
| 15〜17 | - | - | 9.0 | 90 | - | - | 8.5 | 90 |
| 18〜29 | - | - | 8.5 | 100 | - | - | 8.5 | 100 |
| 30〜49 | - | - | 8.5 | 100 | - | - | 8.5 | 100 |
| 50〜64 | - | - | 8.5 | 100 | - | - | 8.5 | 100 |
| 65〜74 | - | - | 8.5 | 100 | - | - | 8.5 | 100 |
| 75以上 | - | - | 8.5 | 100 | - | - | 8.5 | 100 |
| 妊婦 | - | - | 8.5 | - | ||||
| 授乳婦 | - | - | 8.5 | - | ||||
※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2020年版)
各指標の見方について
 | ビタミンDの多い食品 | ||
魚類は全般にビタミンDが豊富
ではこうした働きや効果のあるビタミンDはどのような食品に多く含まれるのでしょうか。ビタミンDは魚類全般に多く含まれます。かわはぎやさけ、ます、にしん、うなぎ、いくら、しらす干しなどは特に多くのビタミンDが含まれます。魚類は含有量も多く食品として量も取れるのでビタミンDの補給先としては最適です。どれもビタミンDの目安量である5.5μgを軽く補うことができる食品ばかりです。
その他食品でビタミンDが多いもの
魚類意外だときくらげやまいたけ、卵黄やすっぽん、鴨肉などにビタミンDは含まれます。ビタミンDの多い食品についてはビタミンDの多い食品・食べ物と含有量一覧でも詳しく解説しています。
|
参考文献
わかりやすいからだとビタミンの知識 サプリメントデータブック エキスパートのためのビタミン・サプリメント 専門医が教えるビタミン・ミネラル早わかり 日本人の食事摂取基準〈2005年版〉 日本人の食事摂取基準〈2015年版〉 日本人の食事摂取基準(2020年版) よくわかる栄養学の基本としくみ |
 ページTOPへ ページTOPへ
|
| 最終更新日 2021/03/25 |
|
since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |
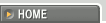
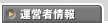
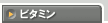
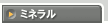
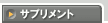
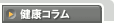



 脂溶性ビタミン
脂溶性ビタミン
